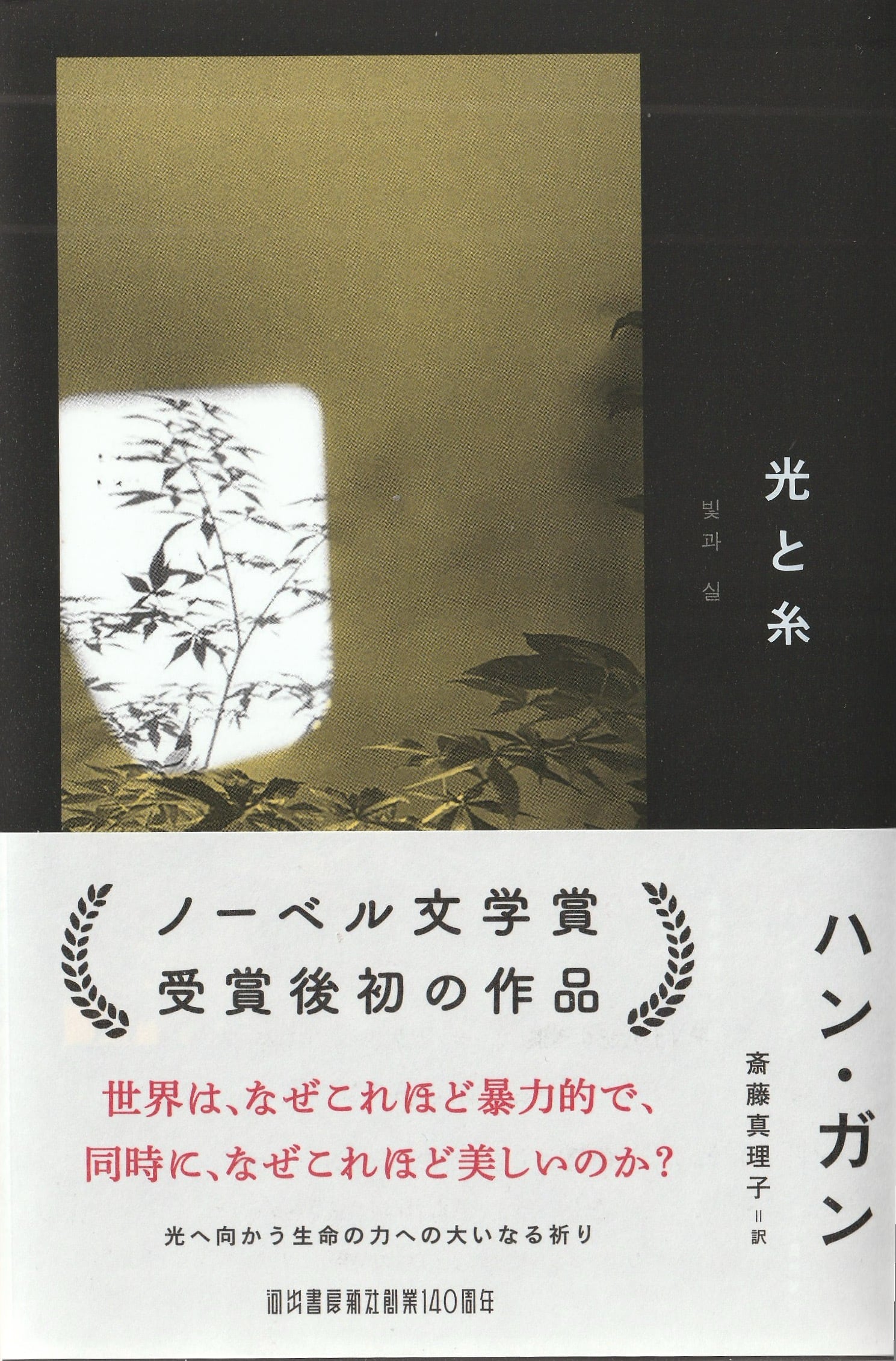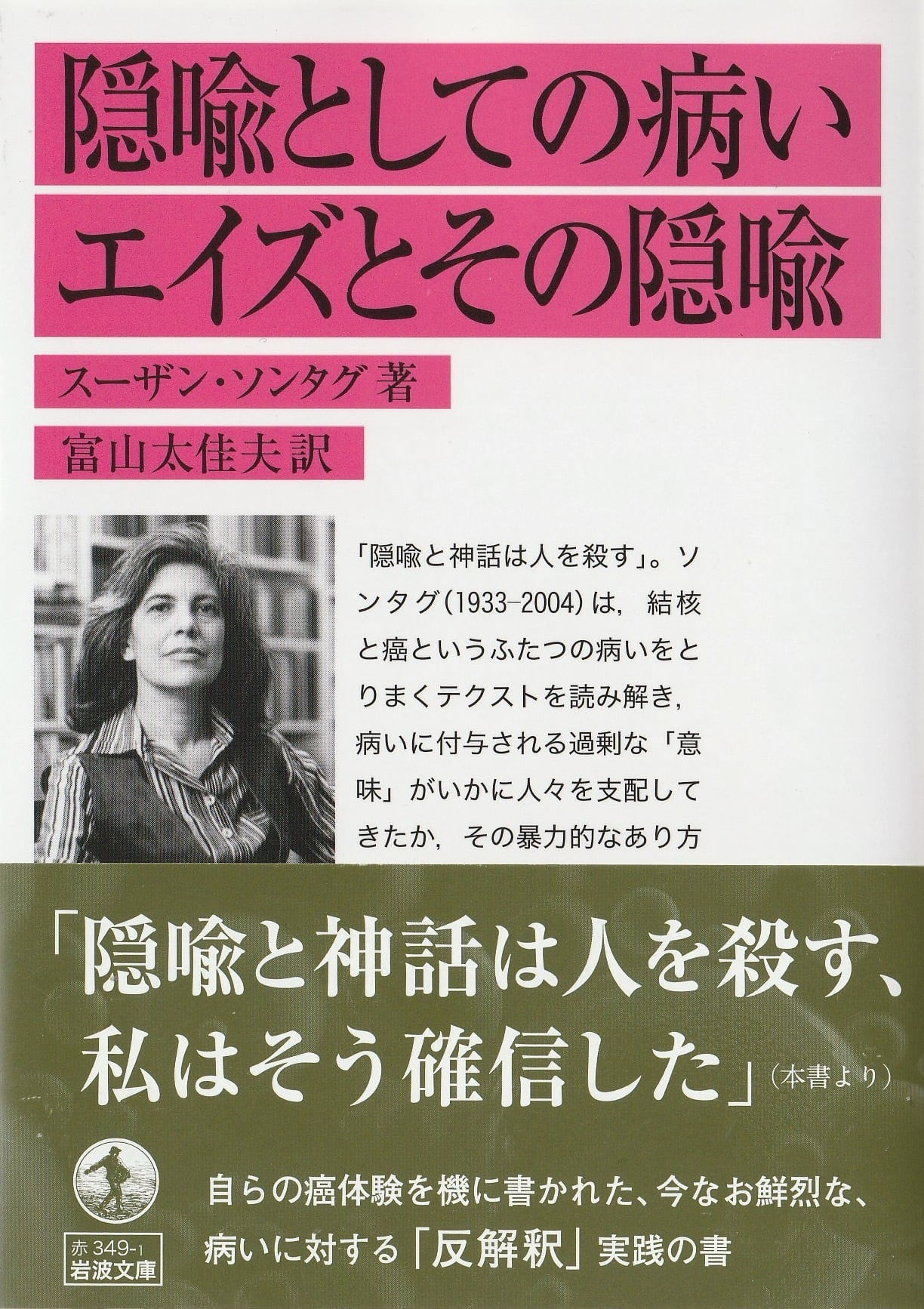出版社別
- 亜紀書房
- アダチプレス
- アルテスパブリッシング
- イースト・プレス
- 岩波書店
- 英明企画編集
- エトセトラブックス
- 太田出版
- 河出書房新社
- 共和国
- 苦楽堂
- 月曜社
- ゲンロン
- 講談社
- 国書刊行会
- コトニ社
- ころから
- 作品社
- 里山社
- 左右社
- 三輪舎
- 集英社
- 晶文社
- 書肆侃侃房
- 書肆子午線
- 新潮社
- 人文書院
- 森話社
- 青弓社
- 青幻舎
- 青土社
- 夕書房
- ソリレス書店
- 田畑書店
- タバブックス
- 筑摩書房
- 中央公論新社
- つかだま書房
- トポフィル
- 土曜社
- トランスビュー
- パブリブ
- ハモニカブックス
- Pヴァイン
- 百万年書房
- フィルムアート社
- ブルーシープ
- 平凡社
- 堀之内出版
- ヘウレーカ
- マイブックサービス
- ミシマ社
- みすず書房
- 夜光社
- よはく舎
- ART DIVER
- NUMABOOKS
- WAKO WORKS OF ART
- others
- カンパニー社
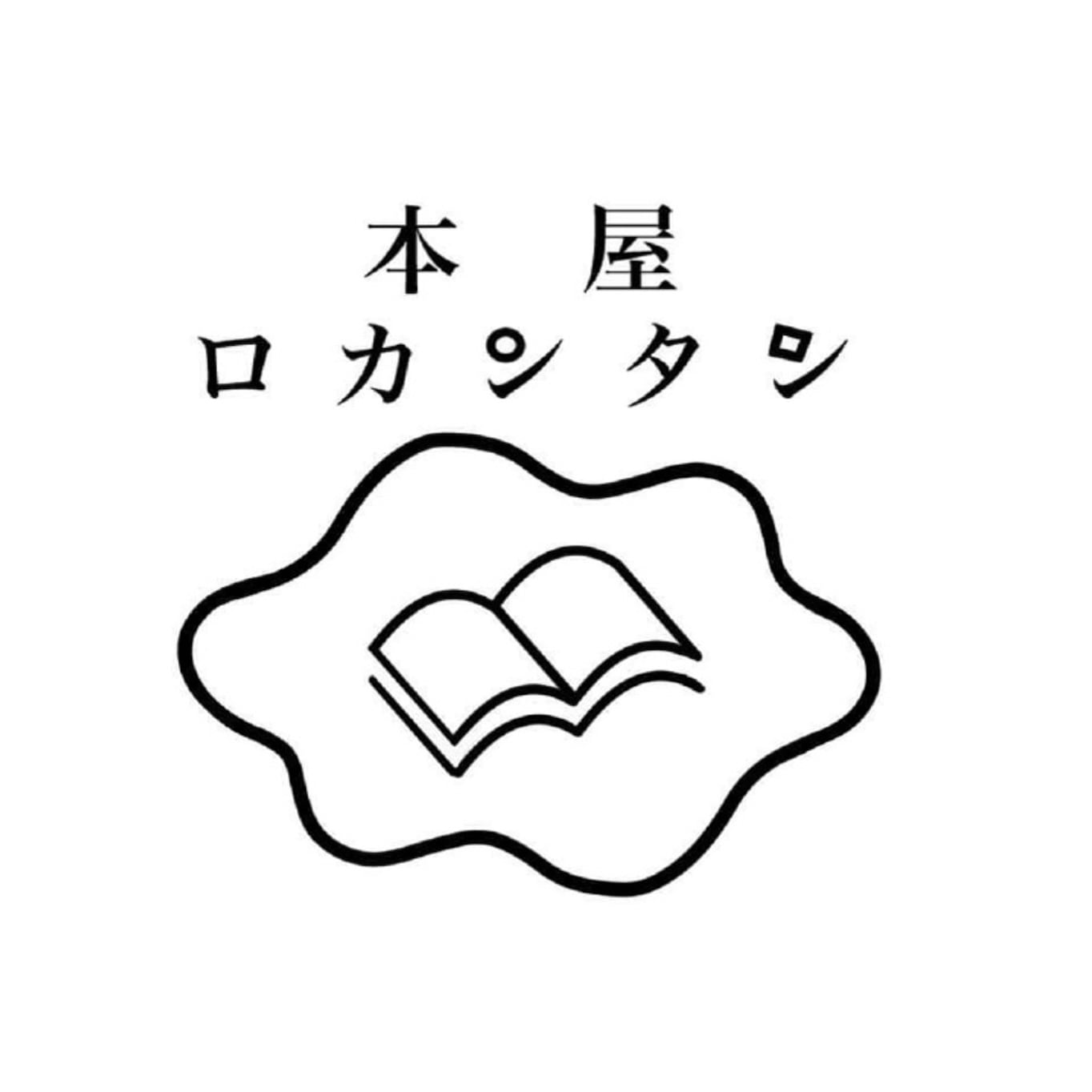

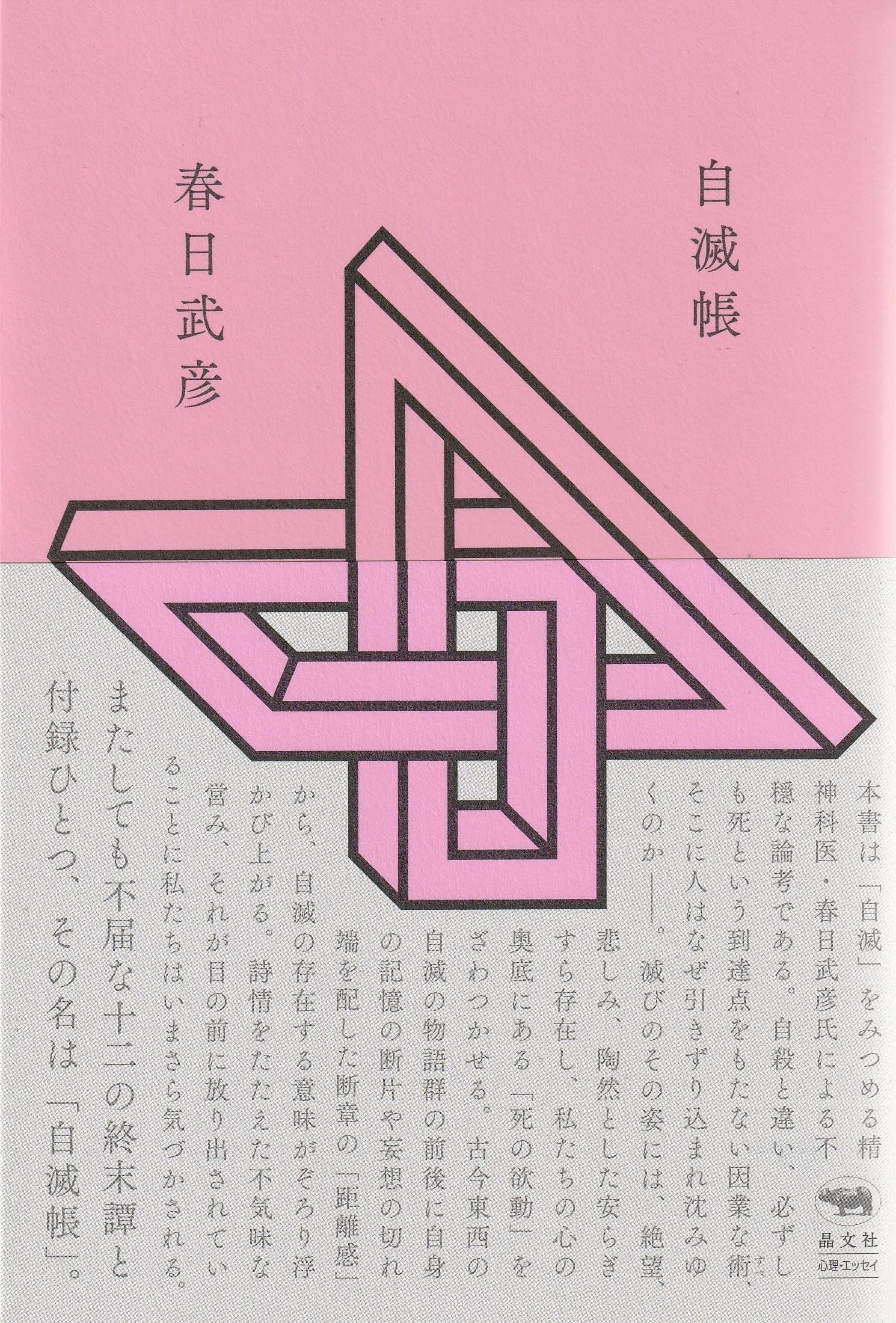
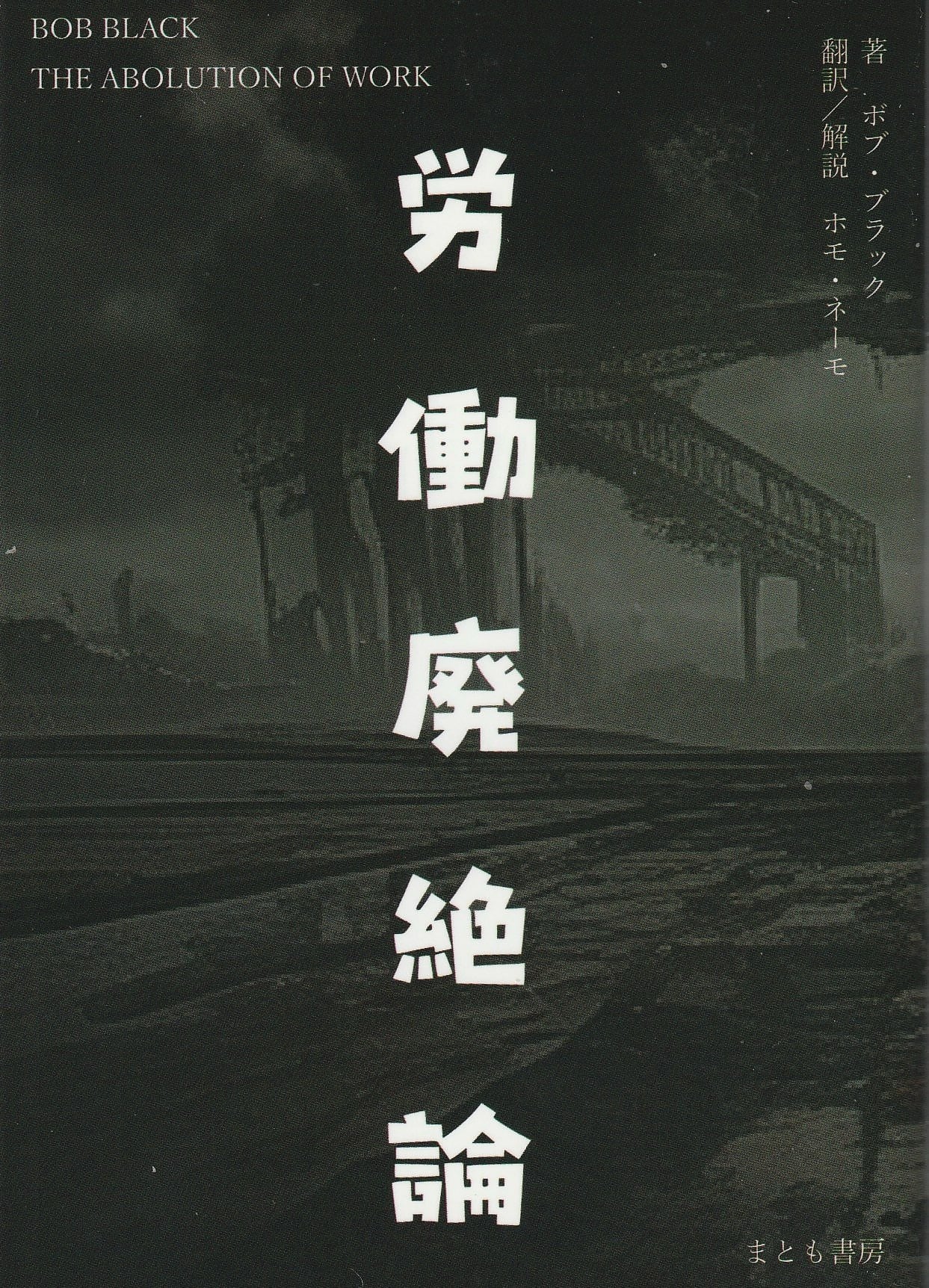
![中国のマンガ〈連環画〉の世界[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/6b4a05b6e825bd8c7b09f2edee237589.jpg?imformat=generic)
![戦争と一人の作家 坂口安吾論[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/305f004747c9fadd9e670871cfde5e04.jpg?imformat=generic)
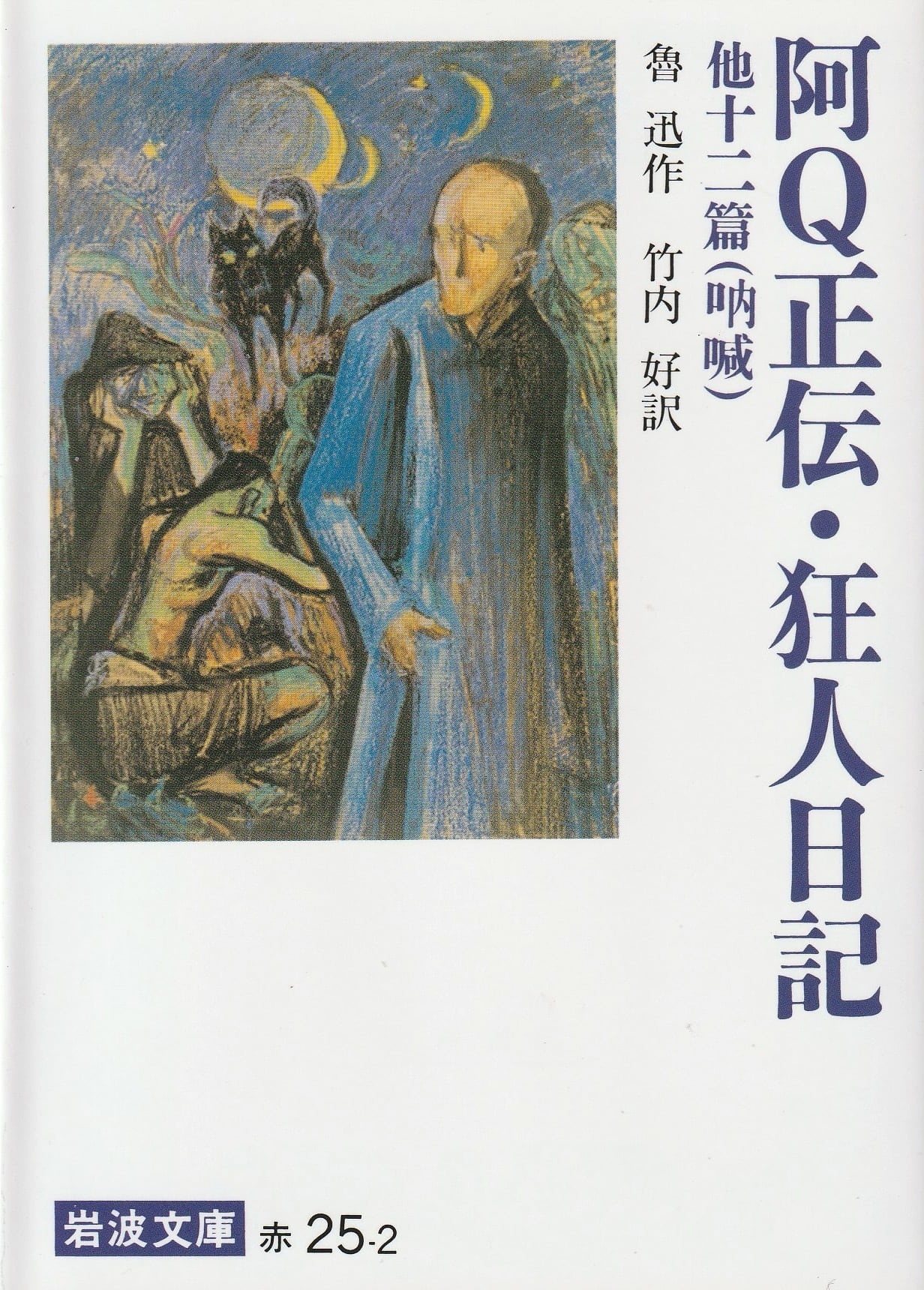

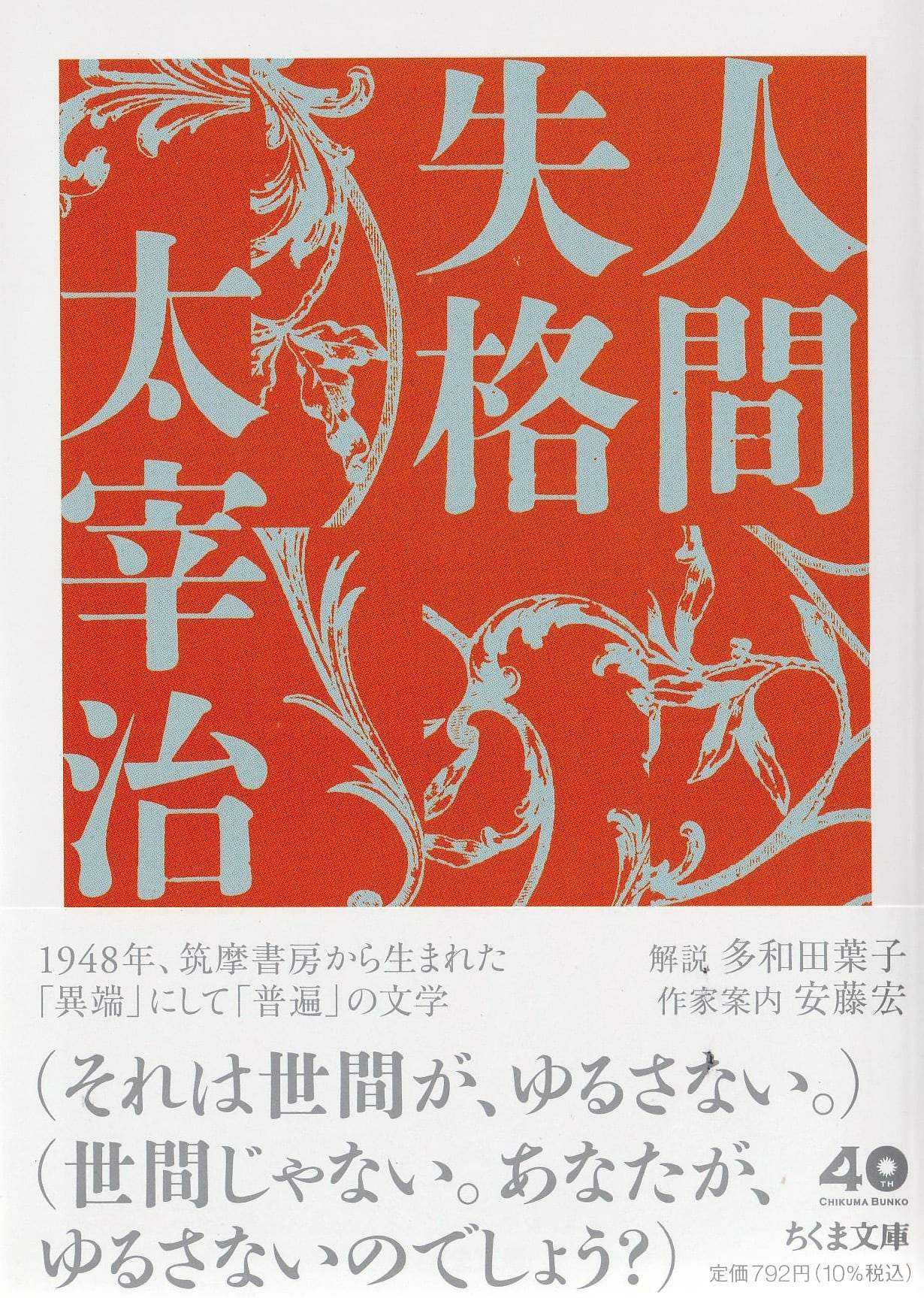
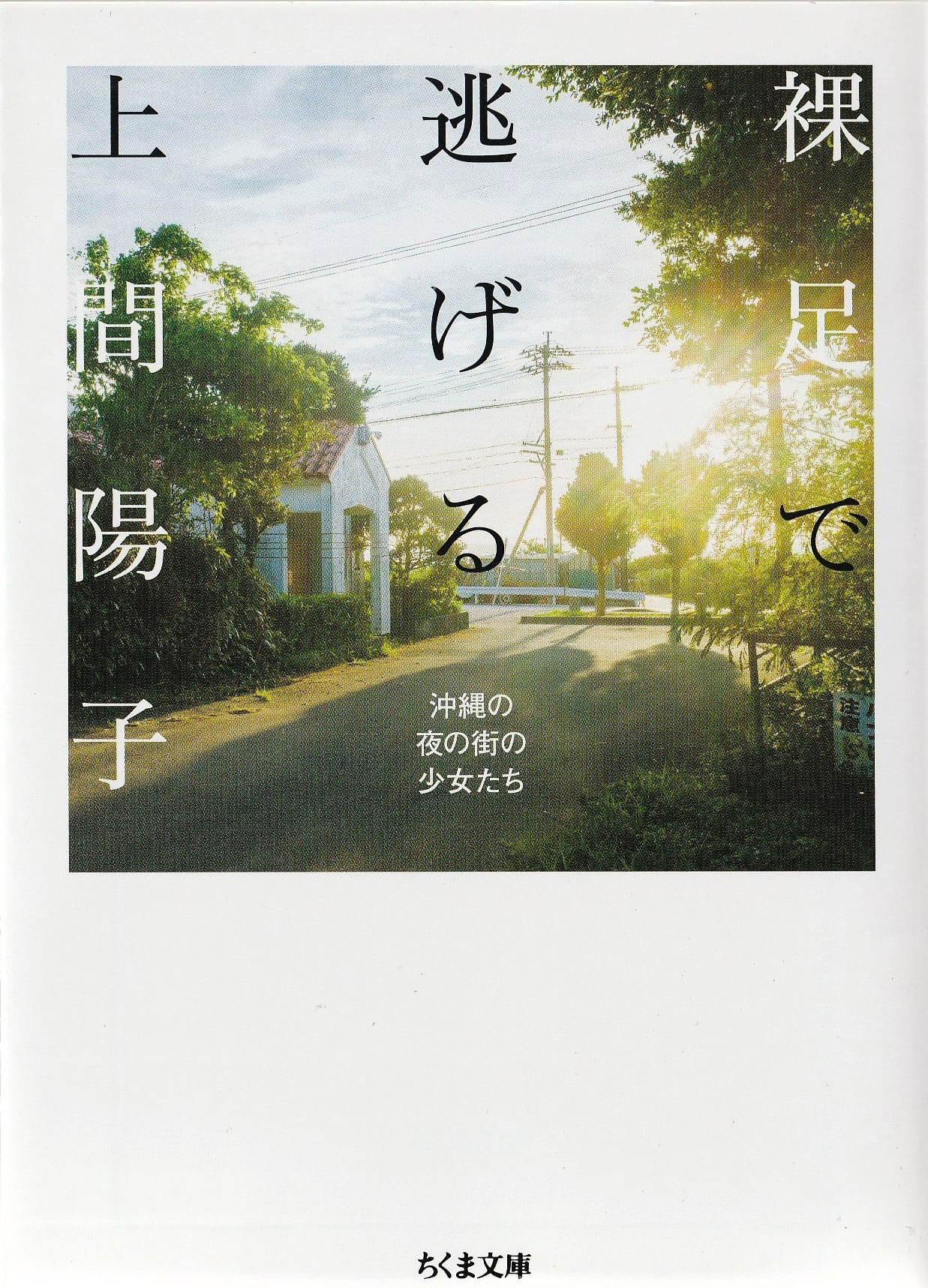
![通天閣 ——新・日本資本主義発達史 決定版[上]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/838f531303e96b4a5d310065f1e8f6e5.jpg?imformat=generic)
![通天閣 ——新・日本資本主義発達史 決定版[下]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/b1dce9402577dce6f31c7c89b26ce2c2.jpg?imformat=generic)
![シン・論——おたくとアヴァンギャルド[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/82ea07ef161edff5abe260c379d78087.jpg?imformat=generic)
![感情化する社会[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/15d4f72af55aef451f9c1922b2de4f07.jpg?imformat=generic)
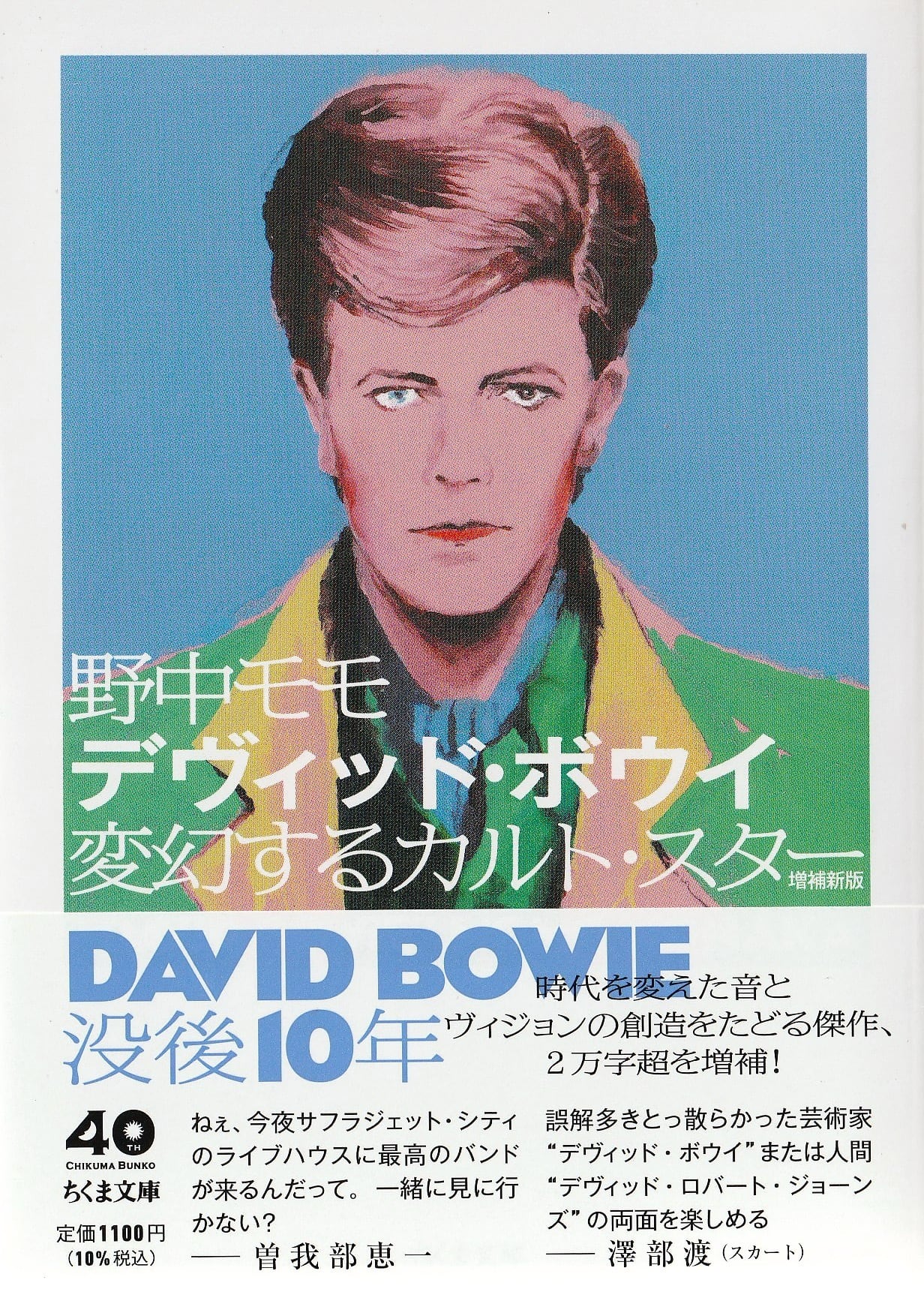
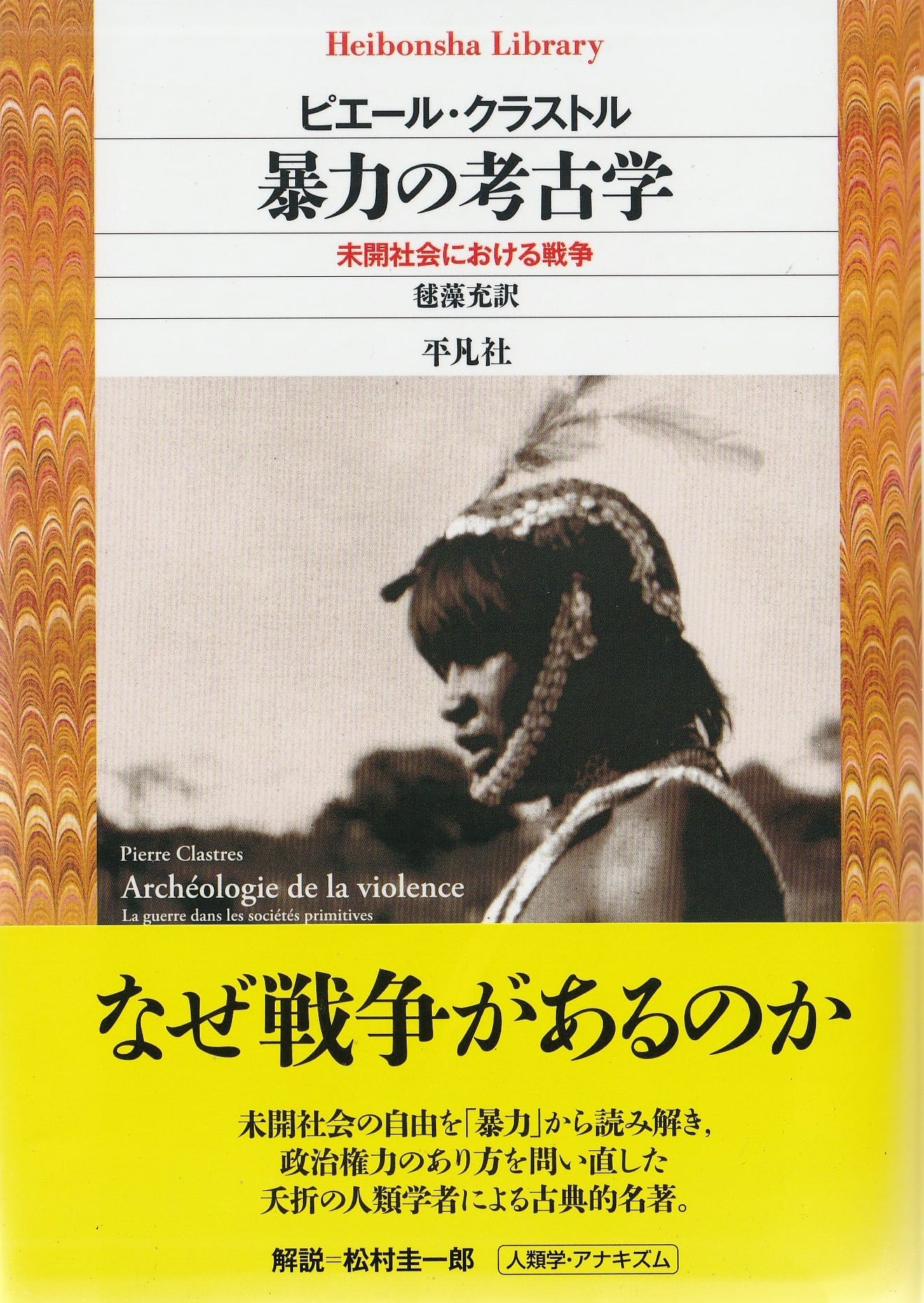
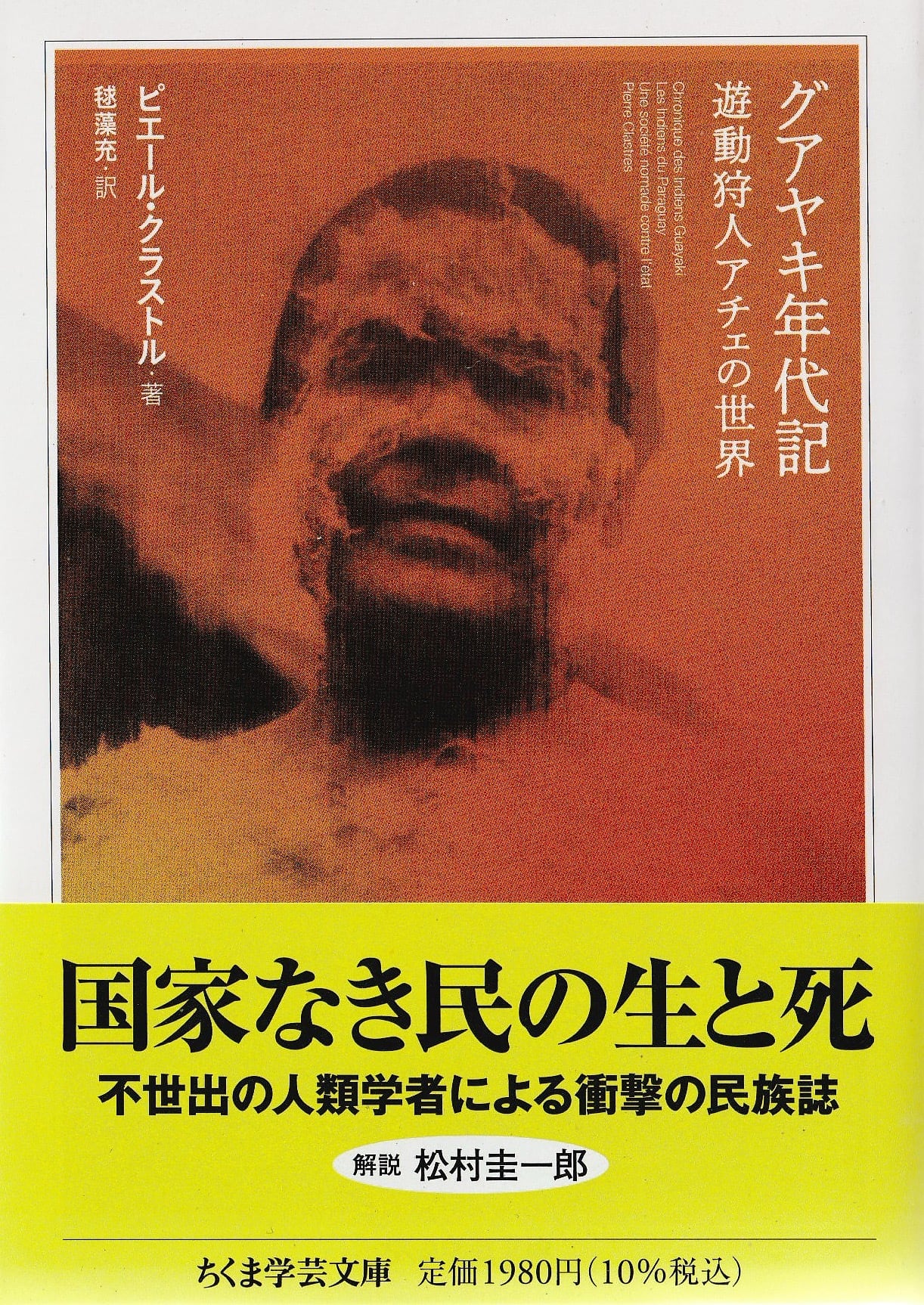
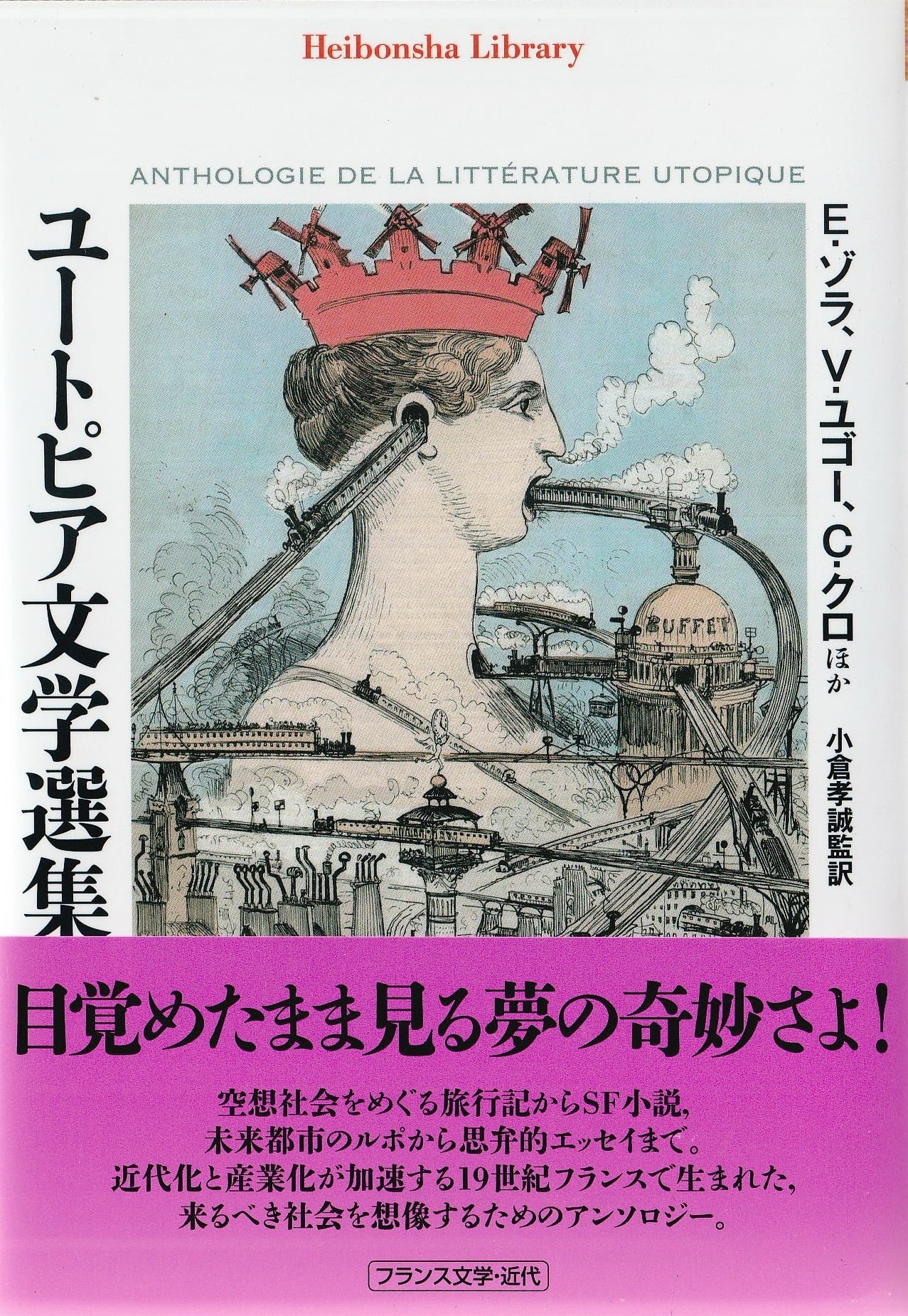
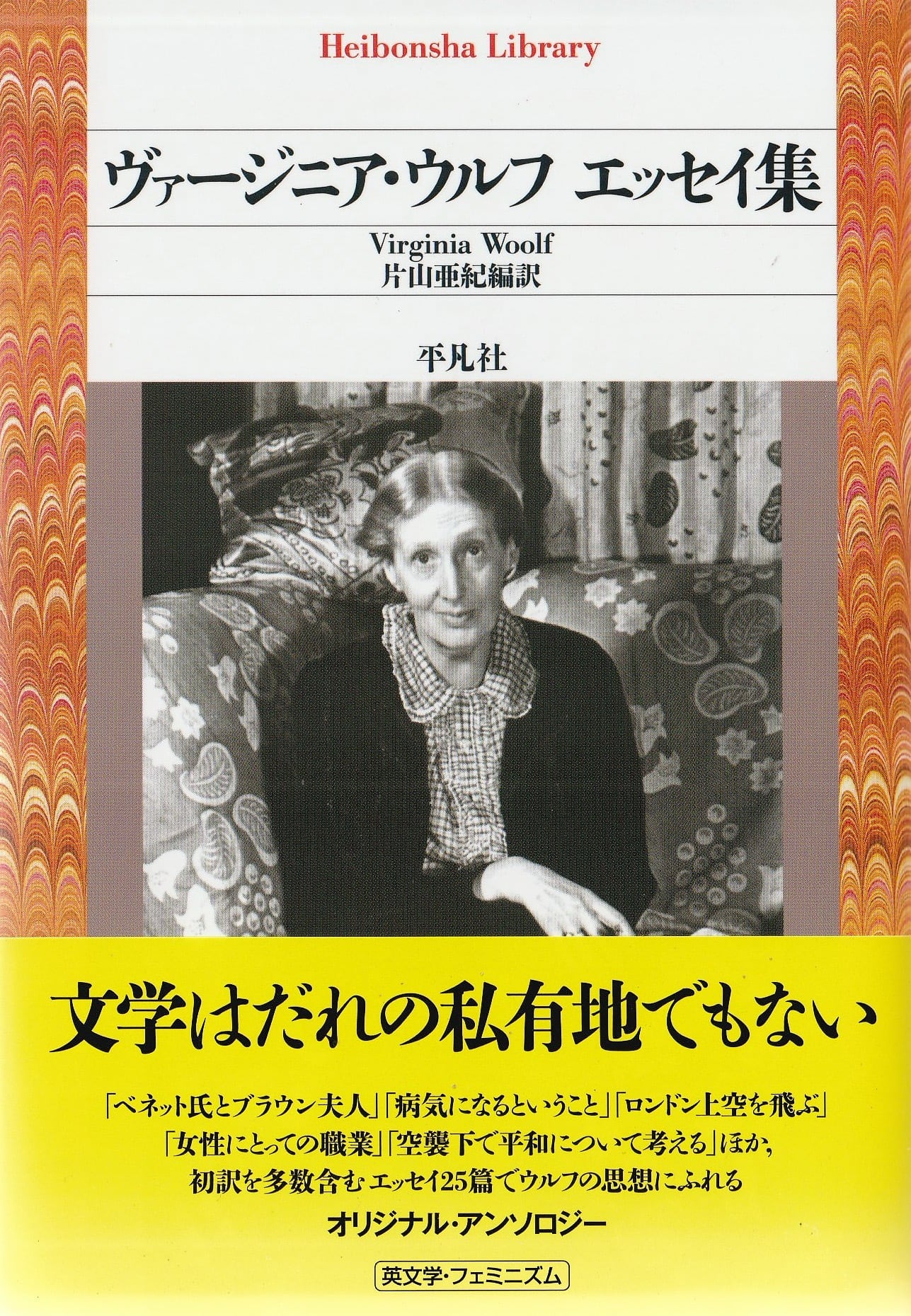
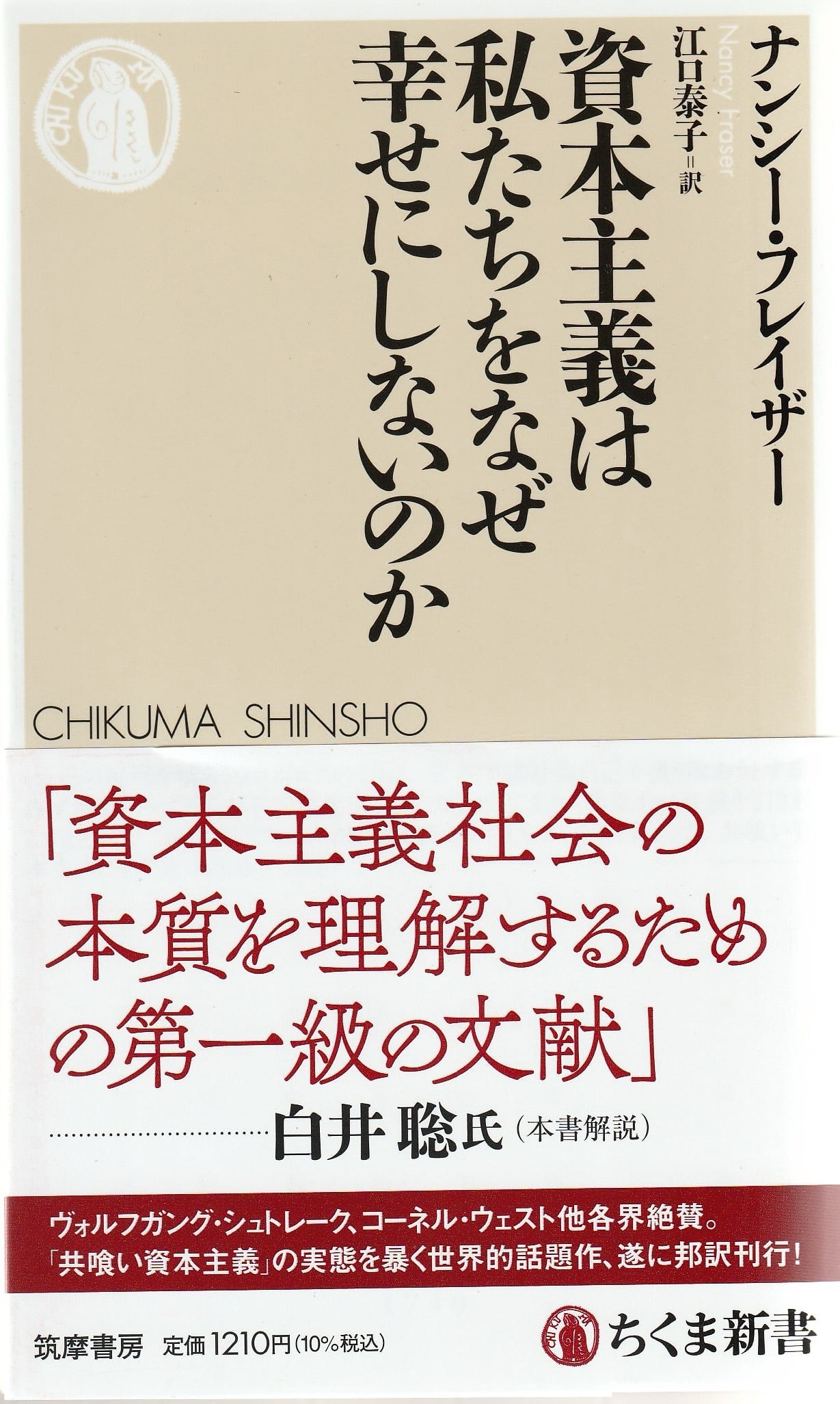
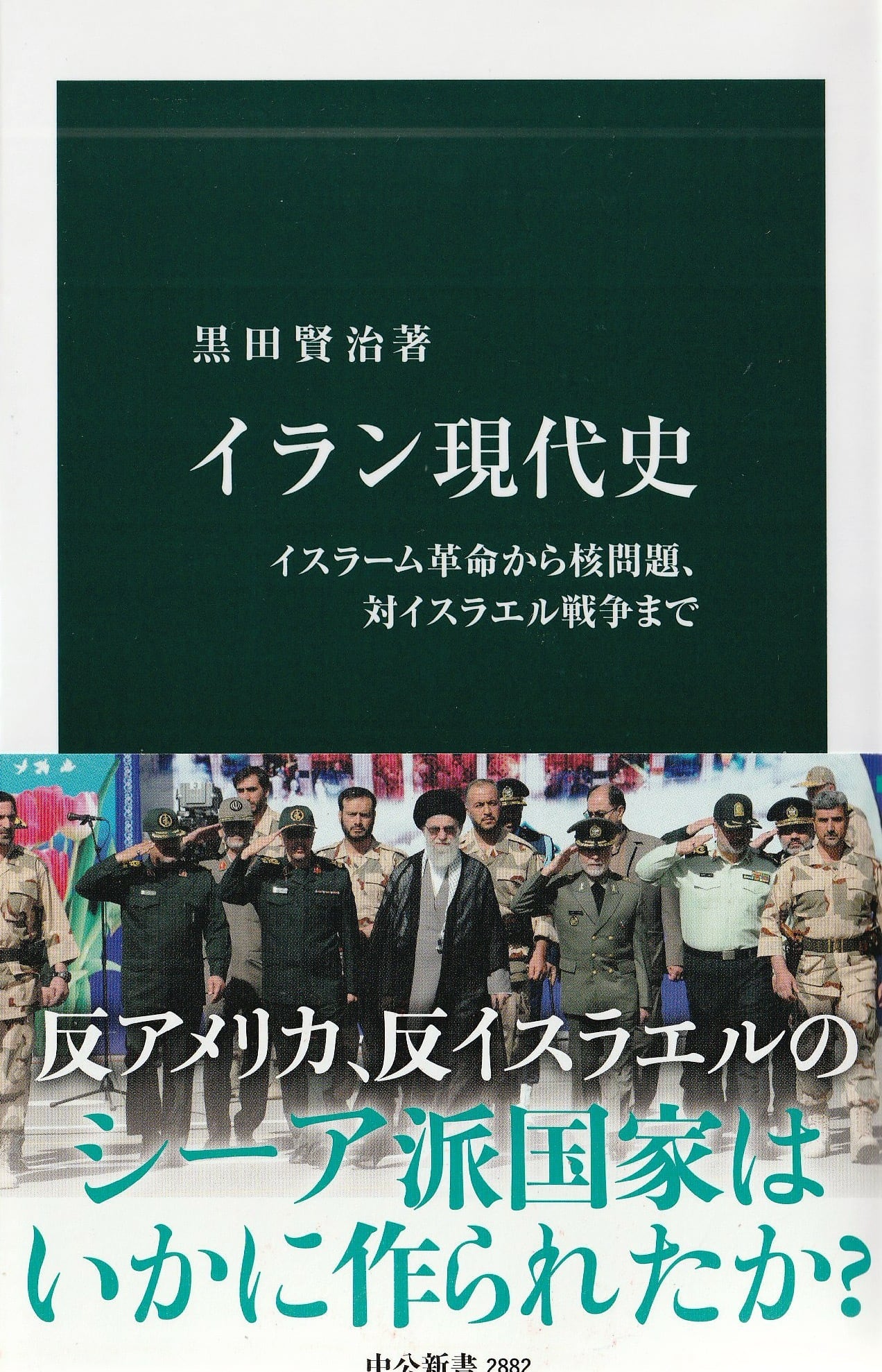
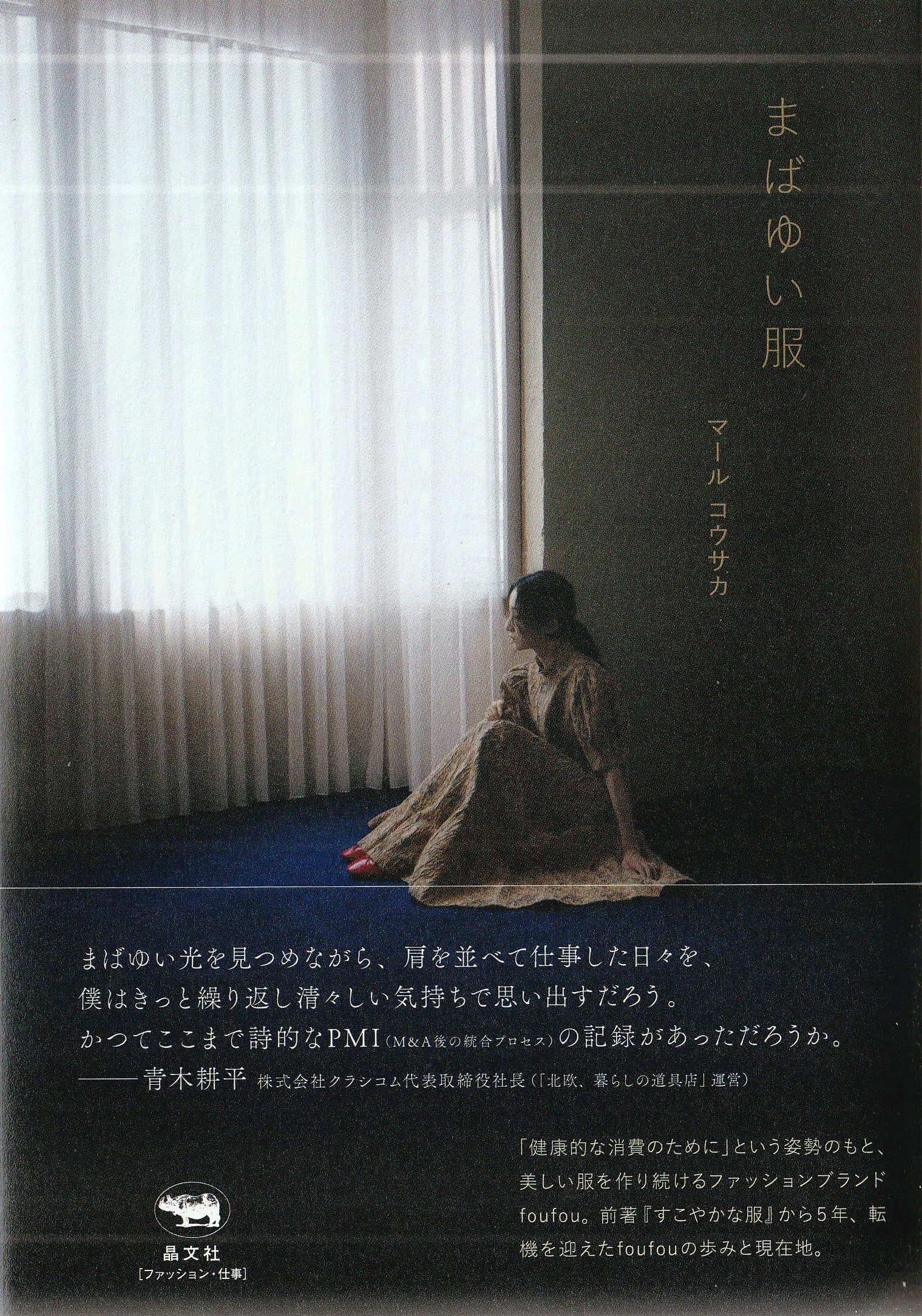
![そばかすの少年[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/e4d0eb120688dc9aa2da1d11625de16f.jpg?imformat=generic)
![ロビンソン・クルーソー[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/40e253b28585ee1b350eb234bee9454f.jpg?imformat=generic)
![正直[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/ebc327e36239001e6ee3234b3914f9c5.jpg?imformat=generic)