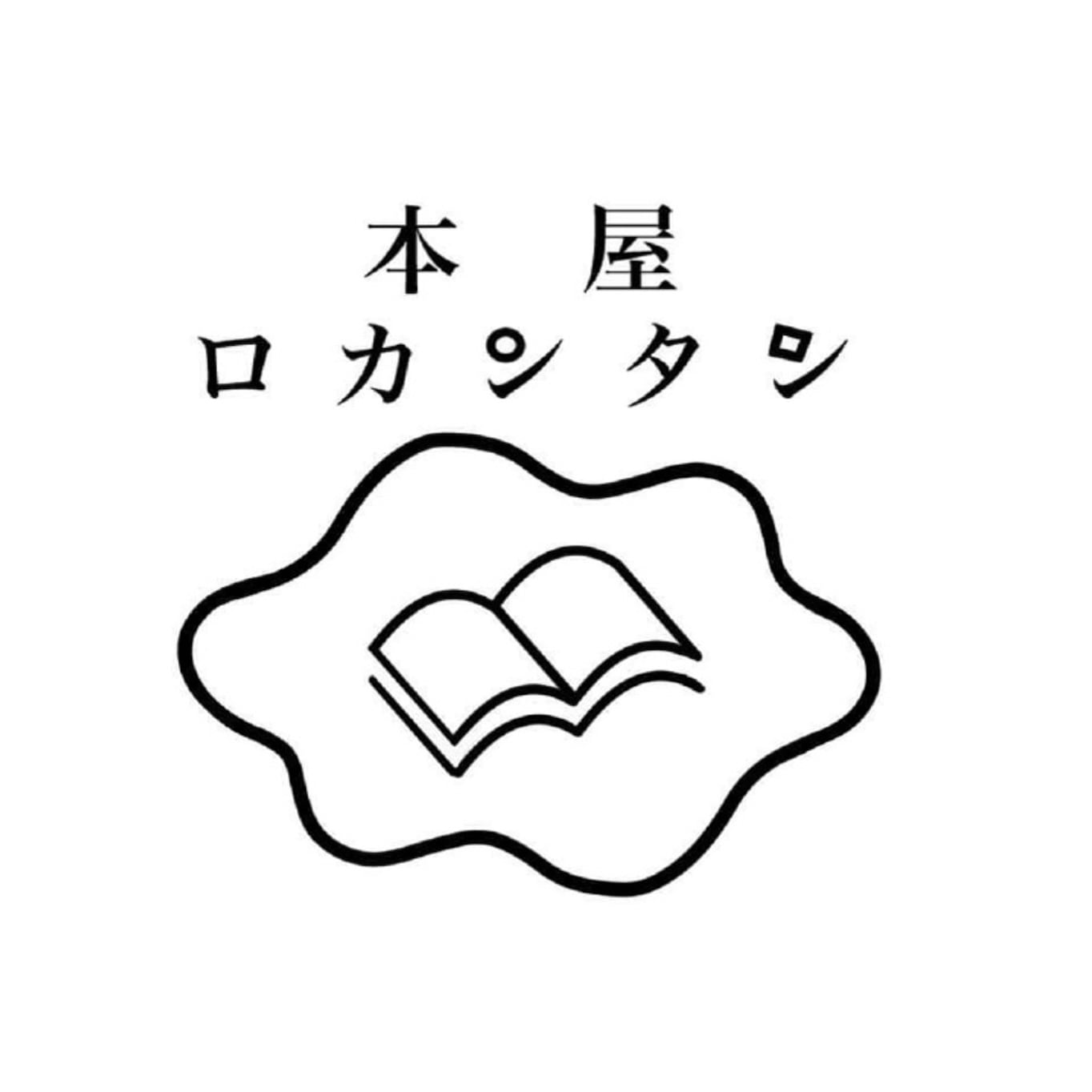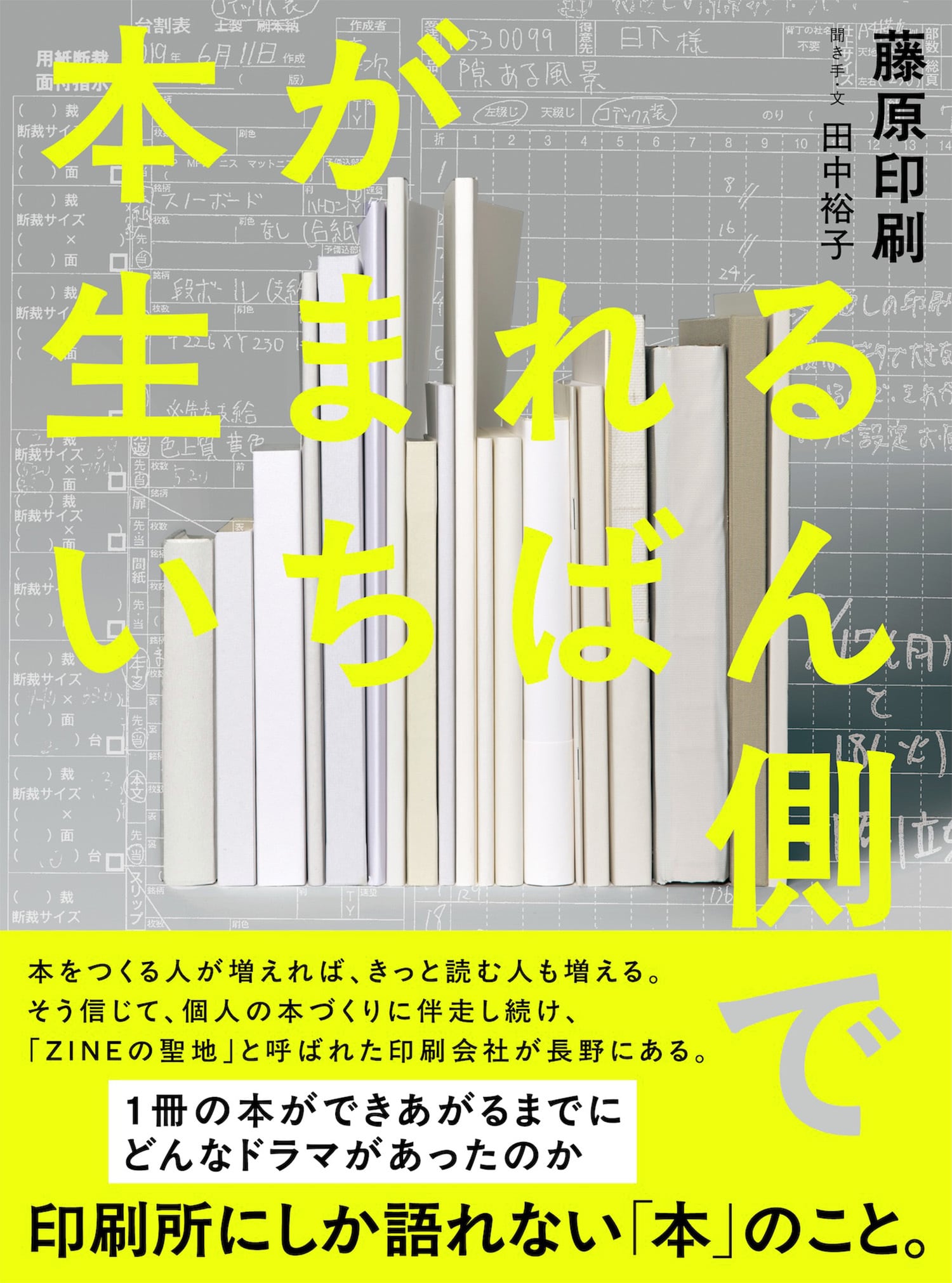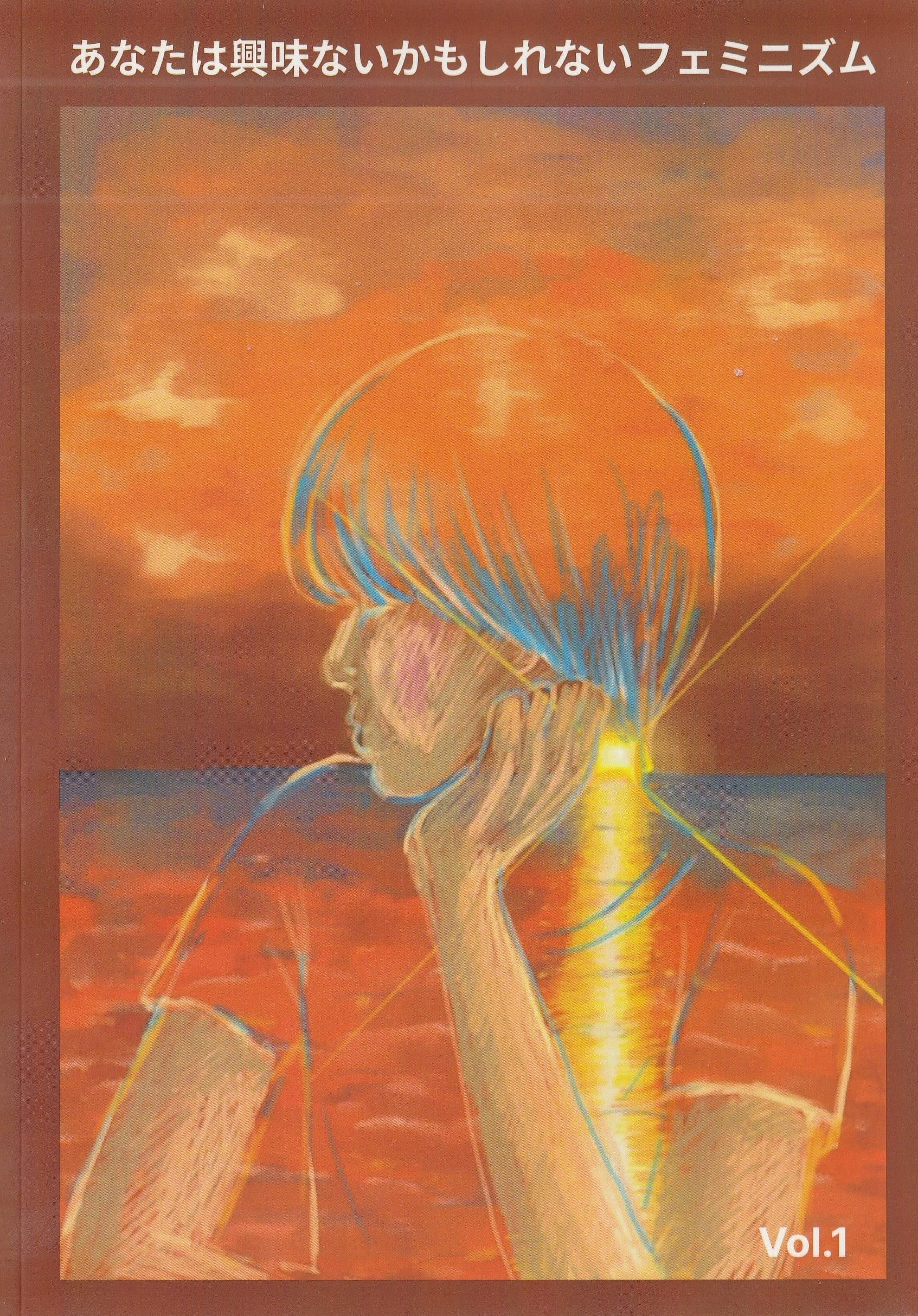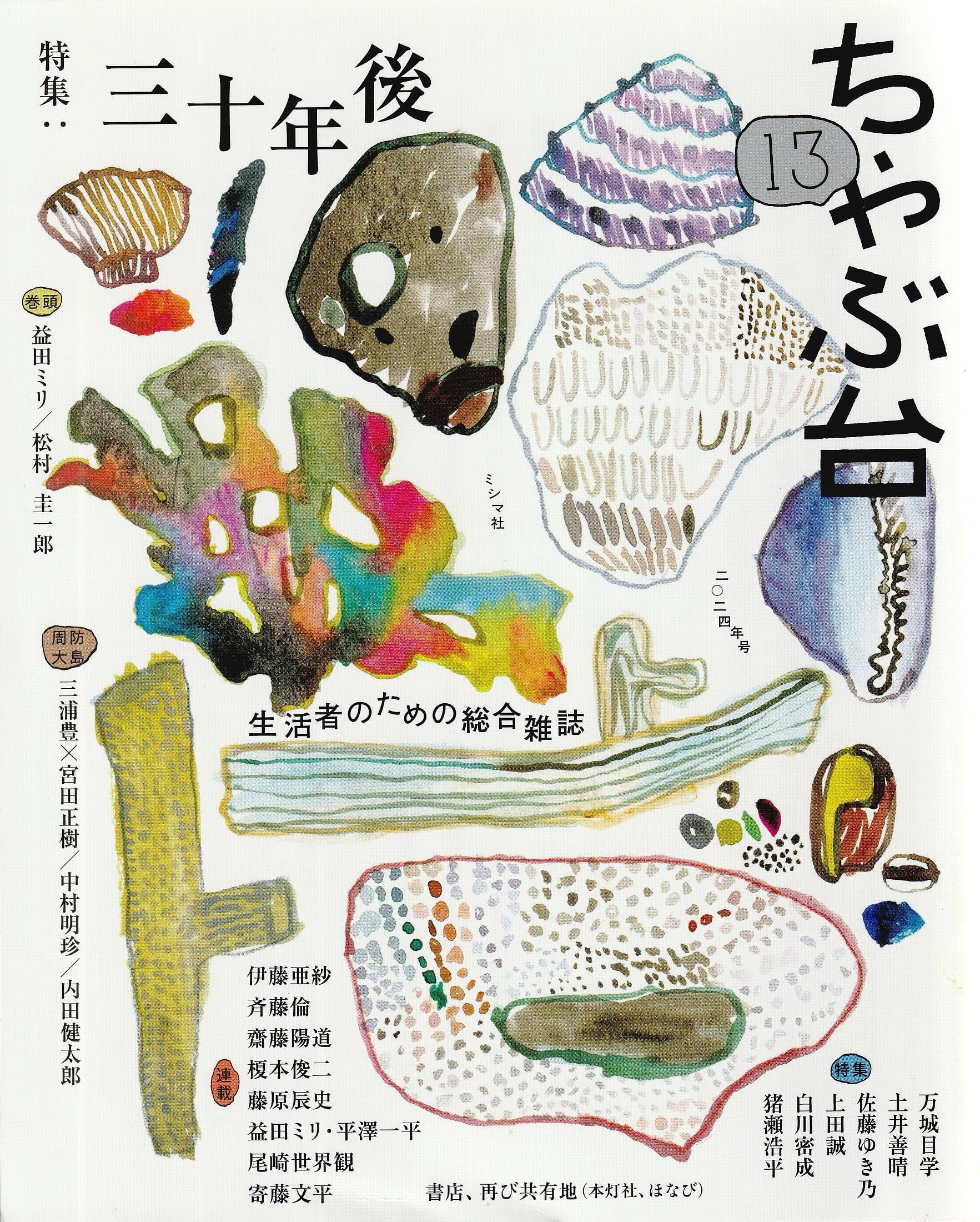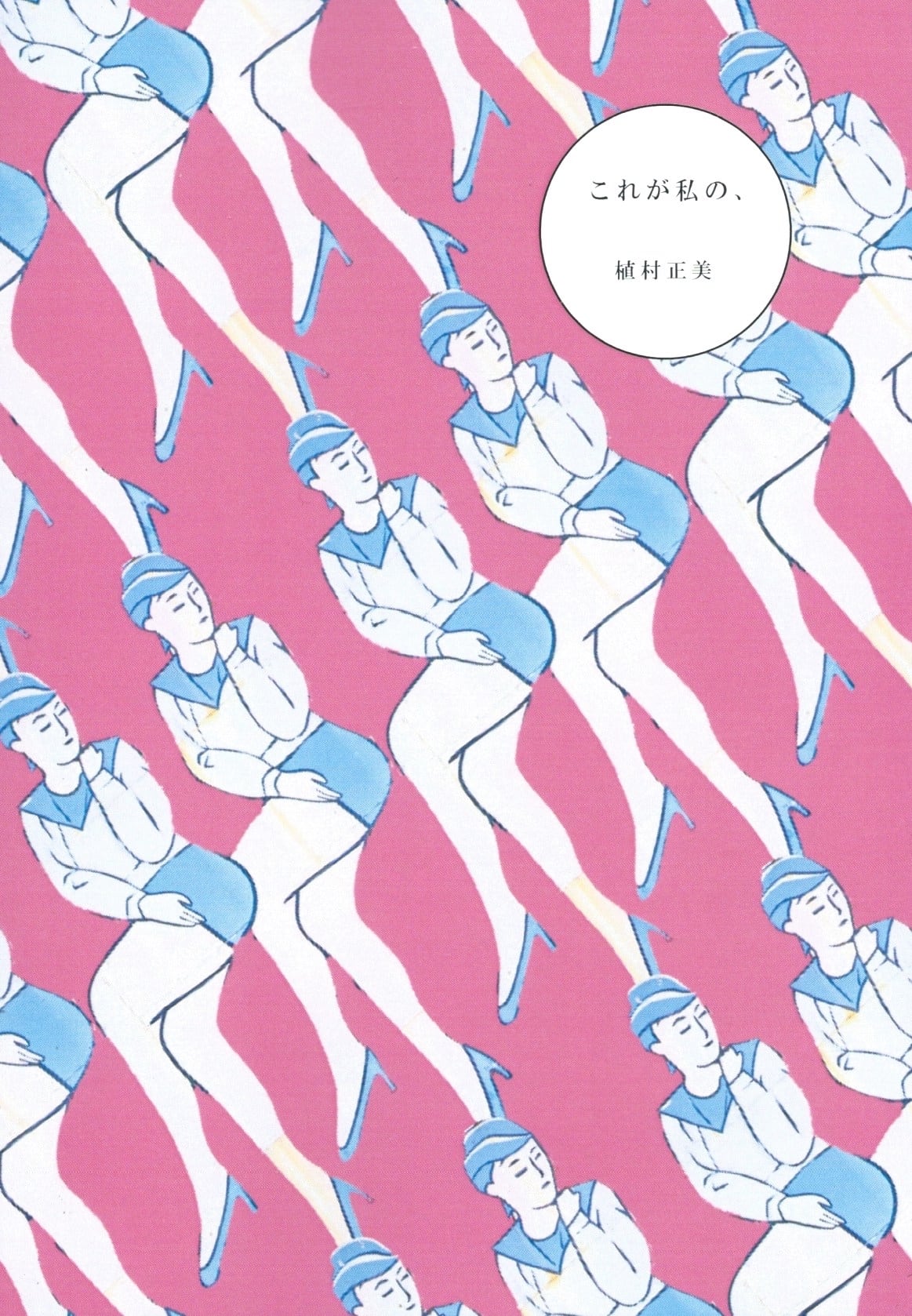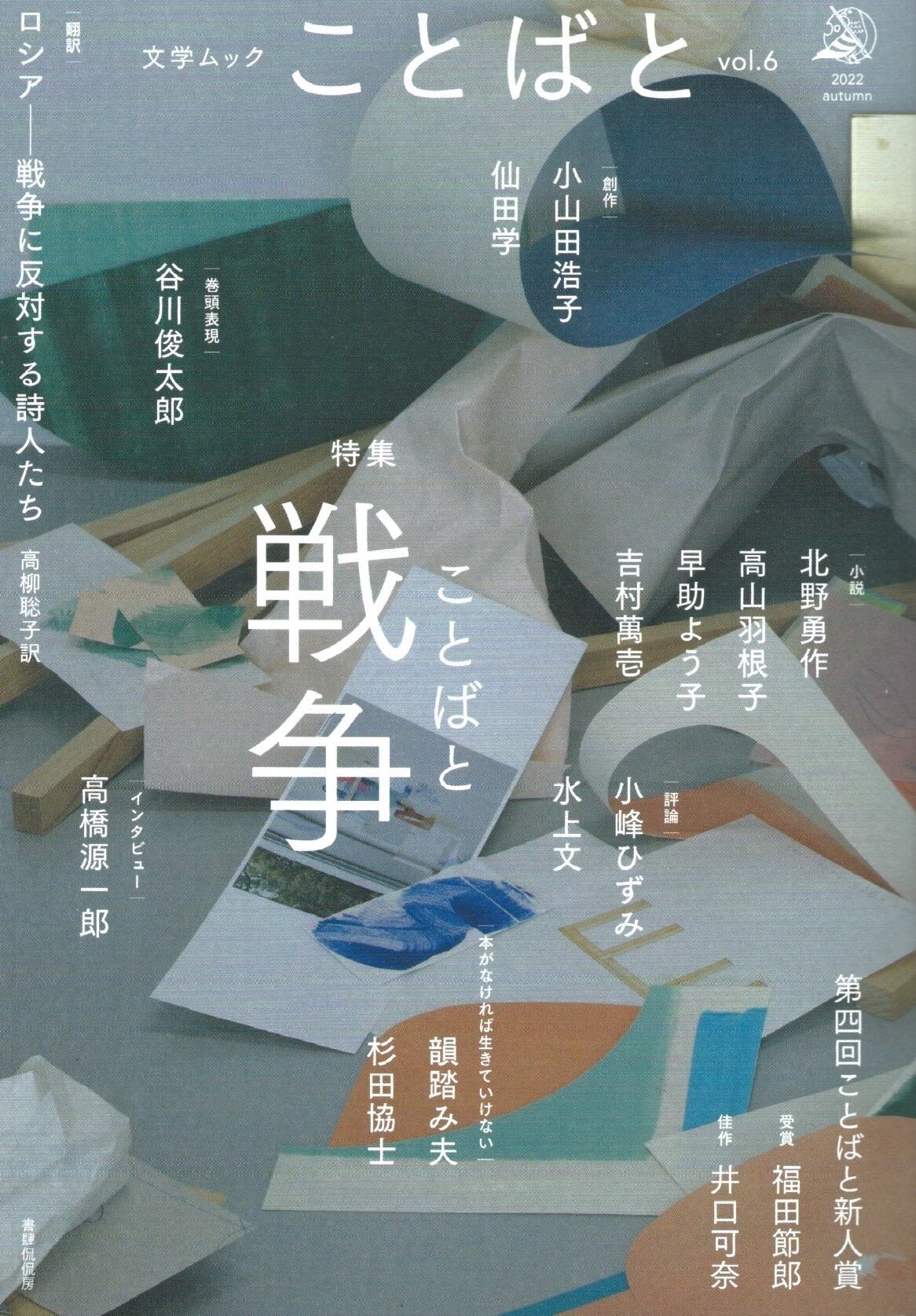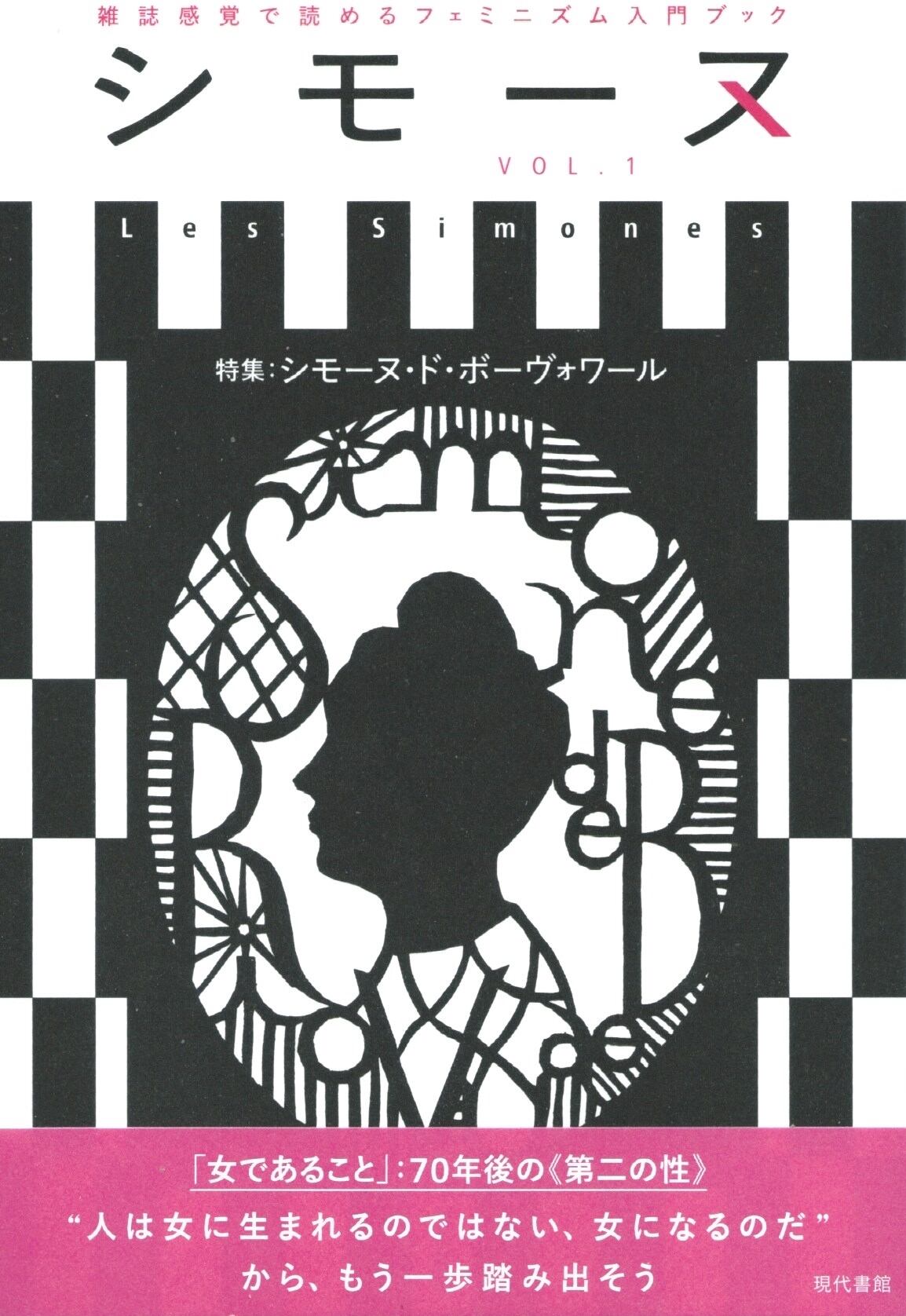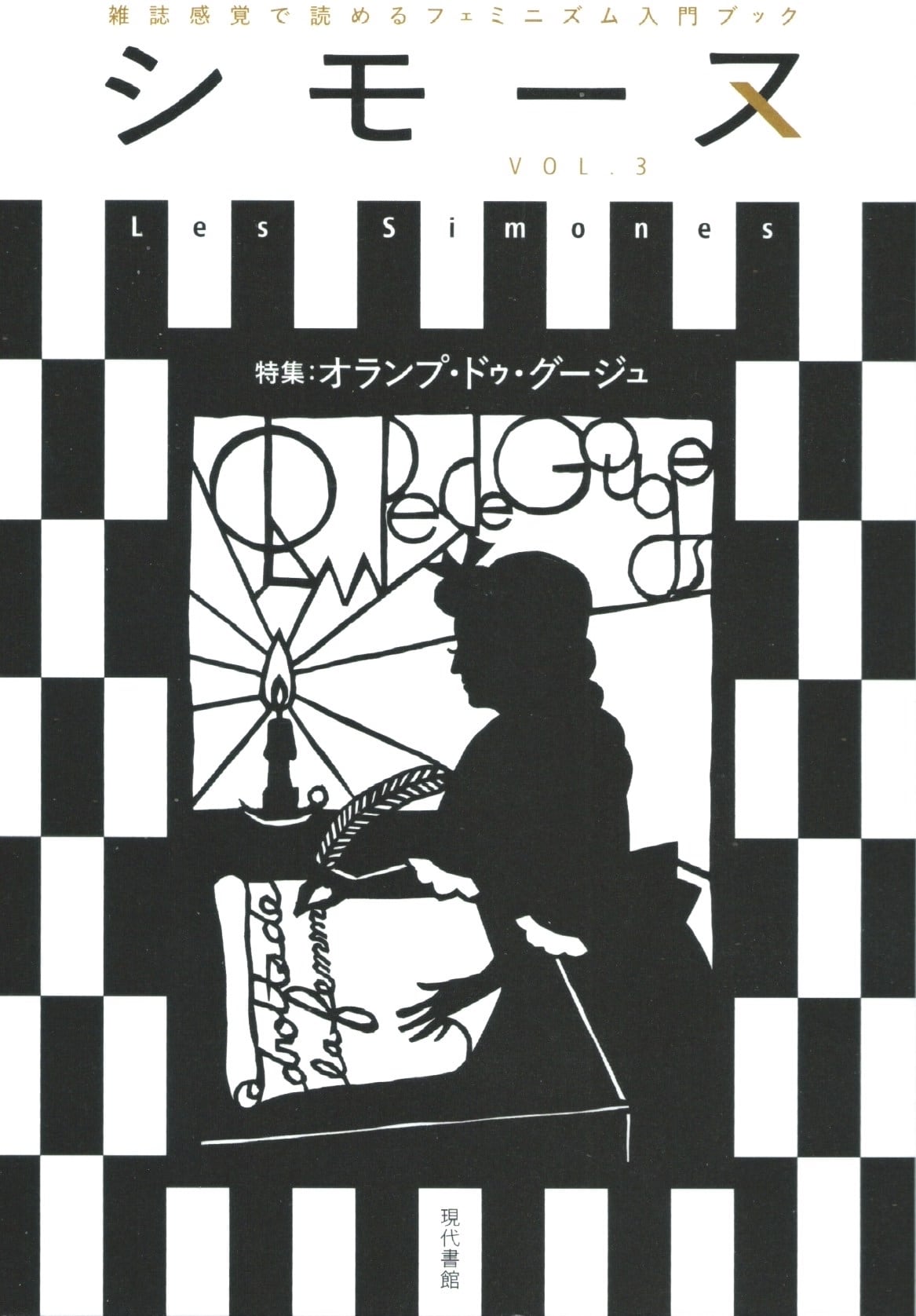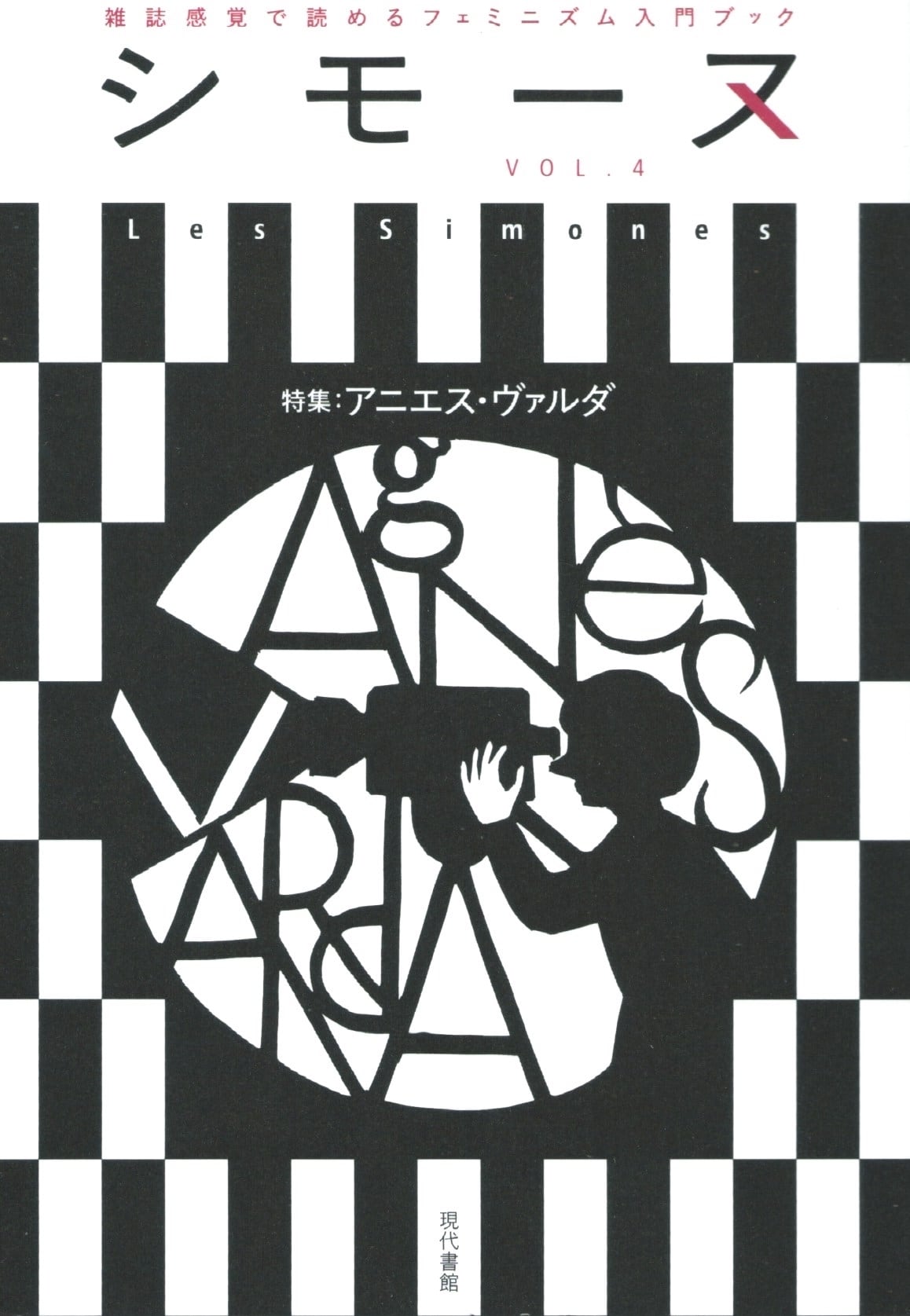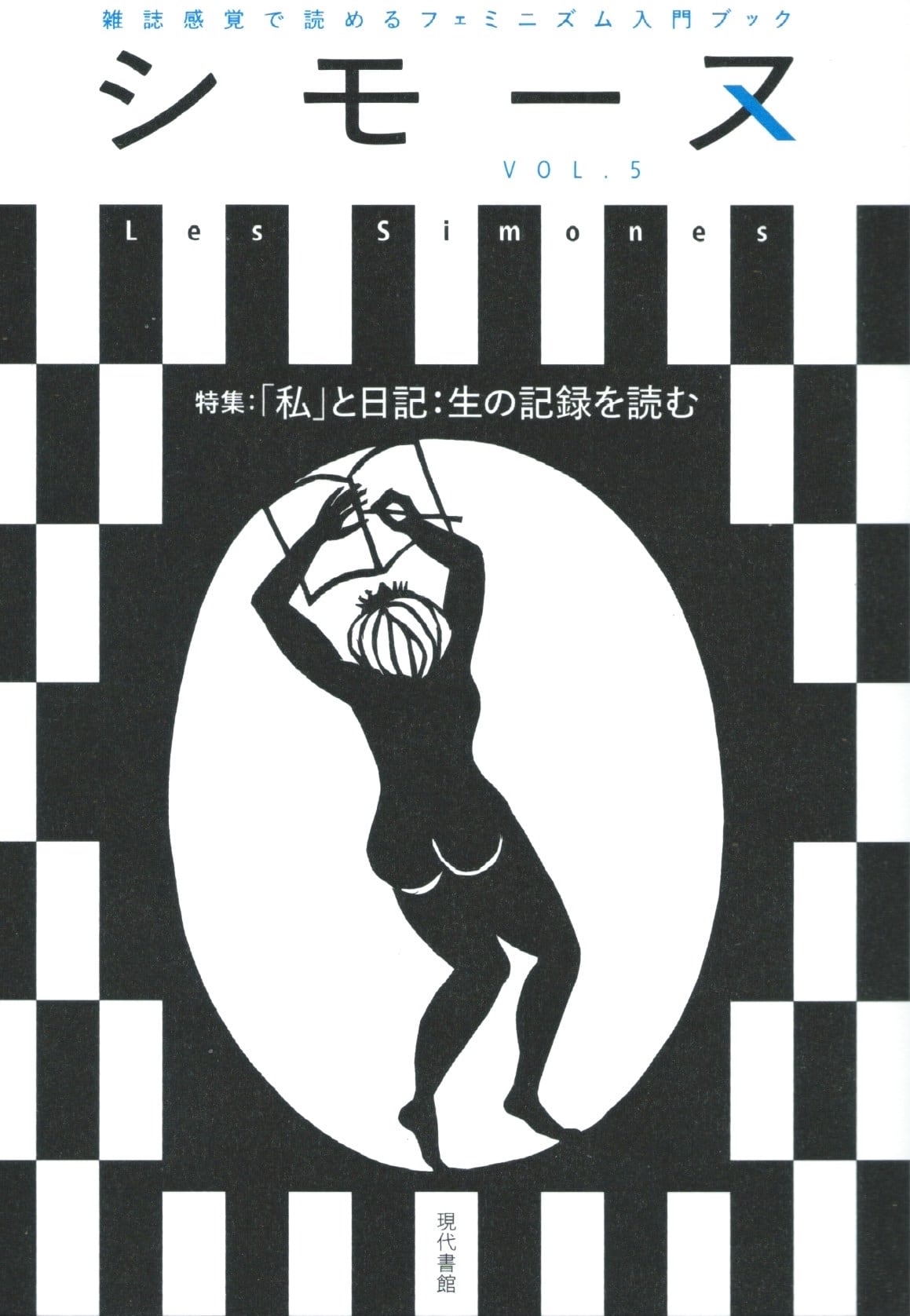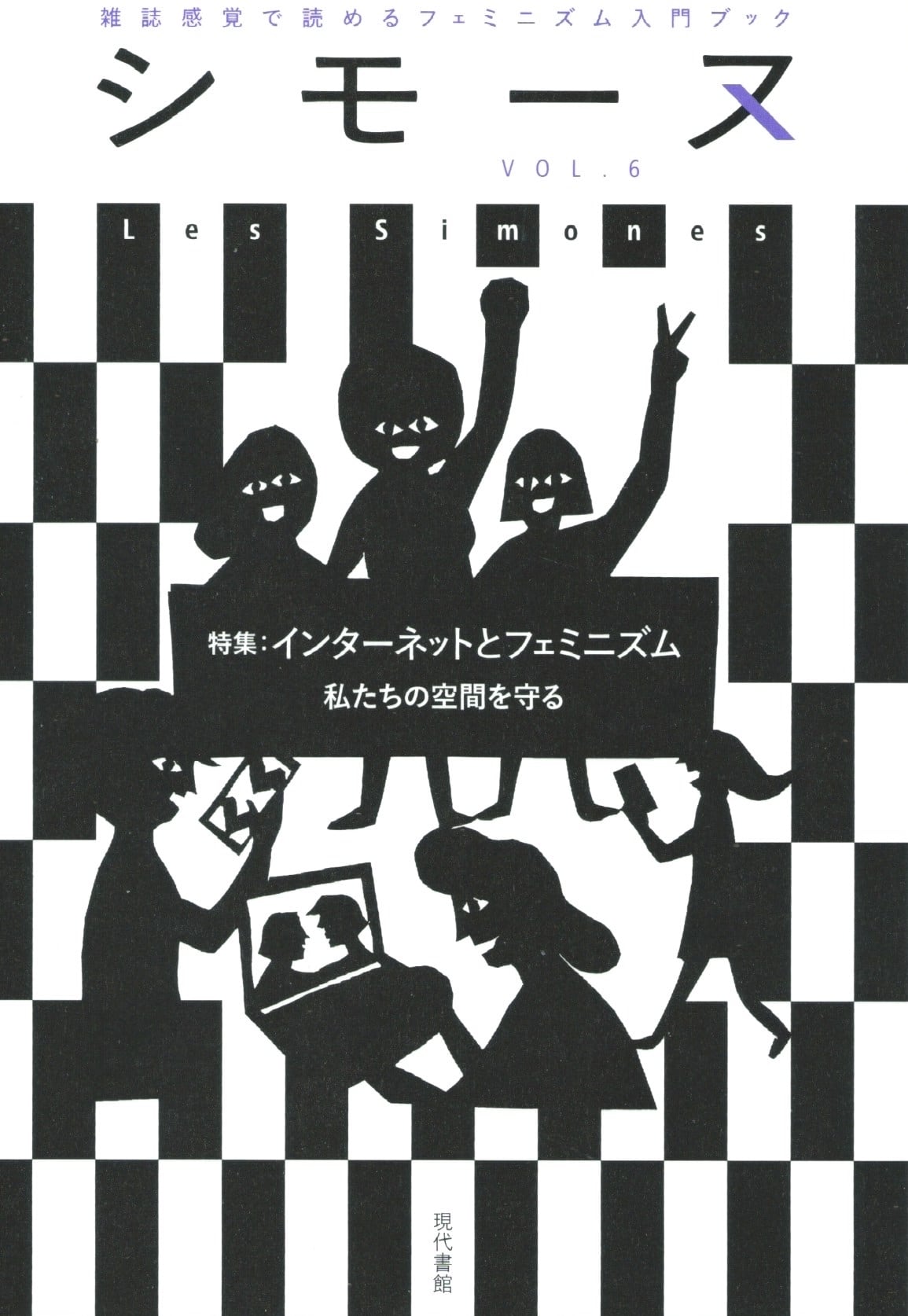zine / mook
- 磯ZINE
- イリュミナシオン
- ウィッチンケア
- 映画横丁
- ヱクリヲ
- エステティーク
- エトセトラ
- ゲンロン
- ことばと
- シモーヌ
- 写真 Sha Shin Magazine
- 新百姓
- ちゃぶ台
- トラベシア
- ビンダー
- 地の文のような生活と/融
- るるるるん
- Art Trace Press
- COUCHONS
- DISTANCE
- f/22
- HAPAX
- IWAKAN
- Jodo Journal
- neoneo
- NEUTRAL COLORS
- nobody
- nyx
- LOCUST
- LOOP 映像メディア学
- PATU
- photographers' gallery press
- THINKING「O」
- TRAVEL UNA
- USO
- vanitas