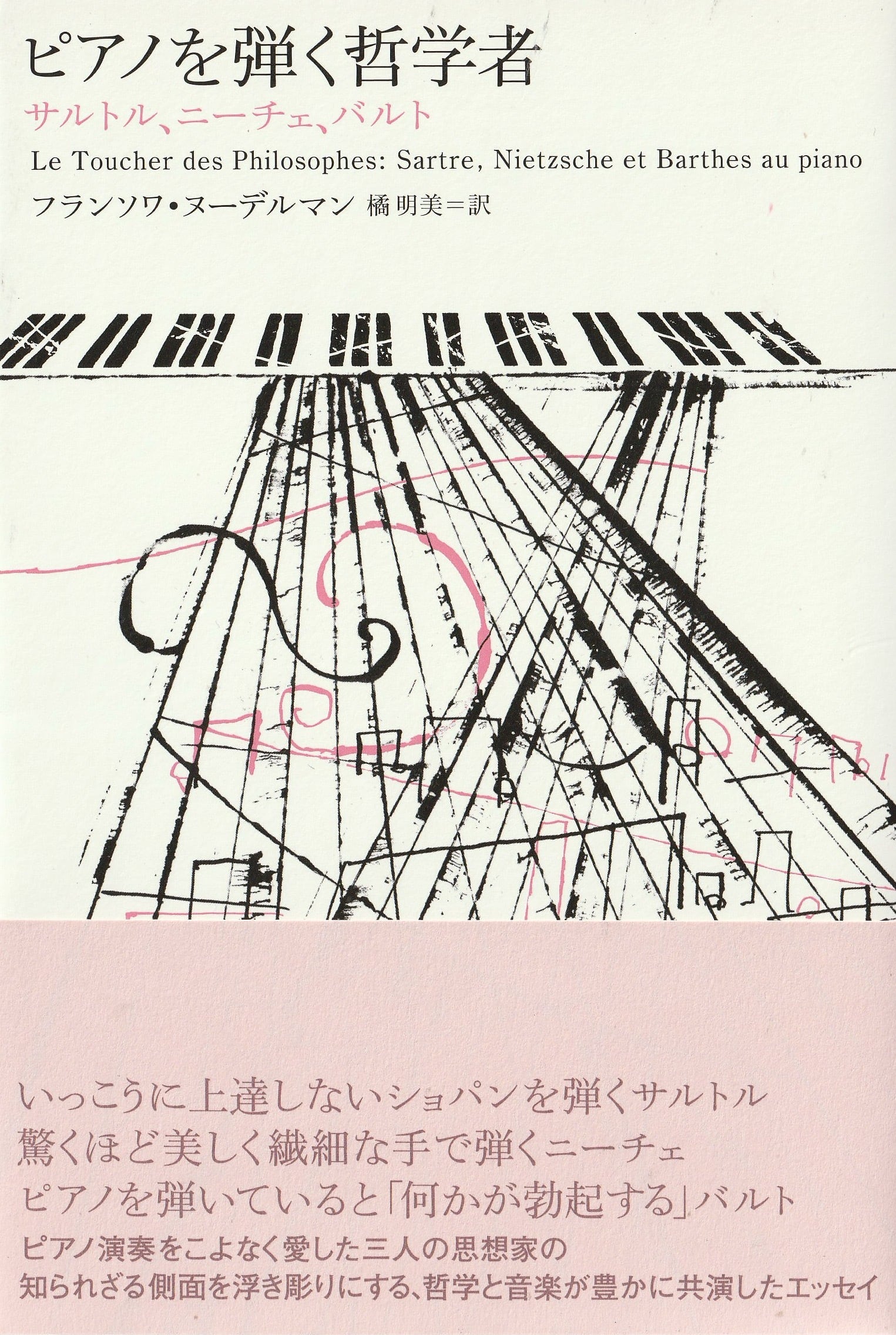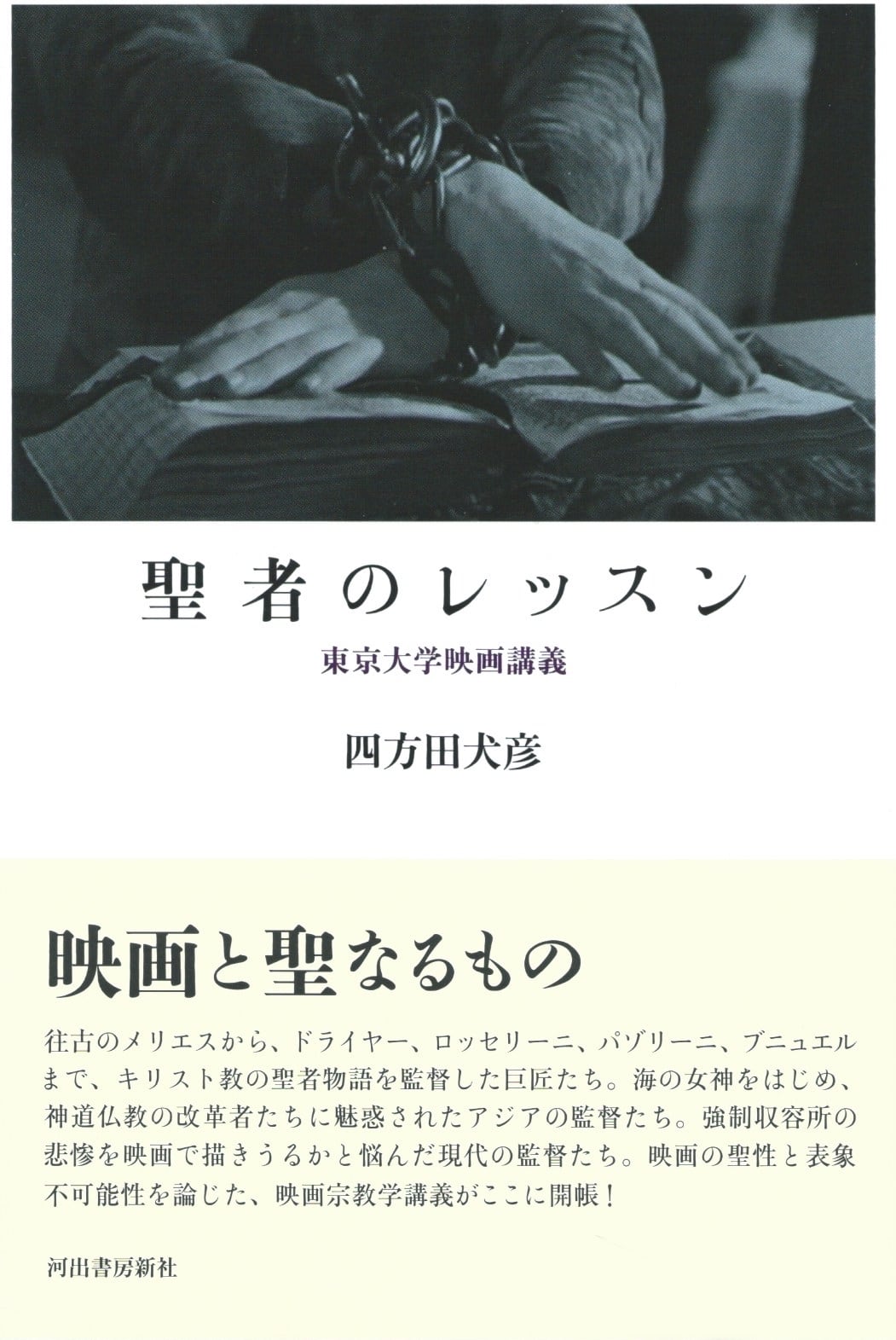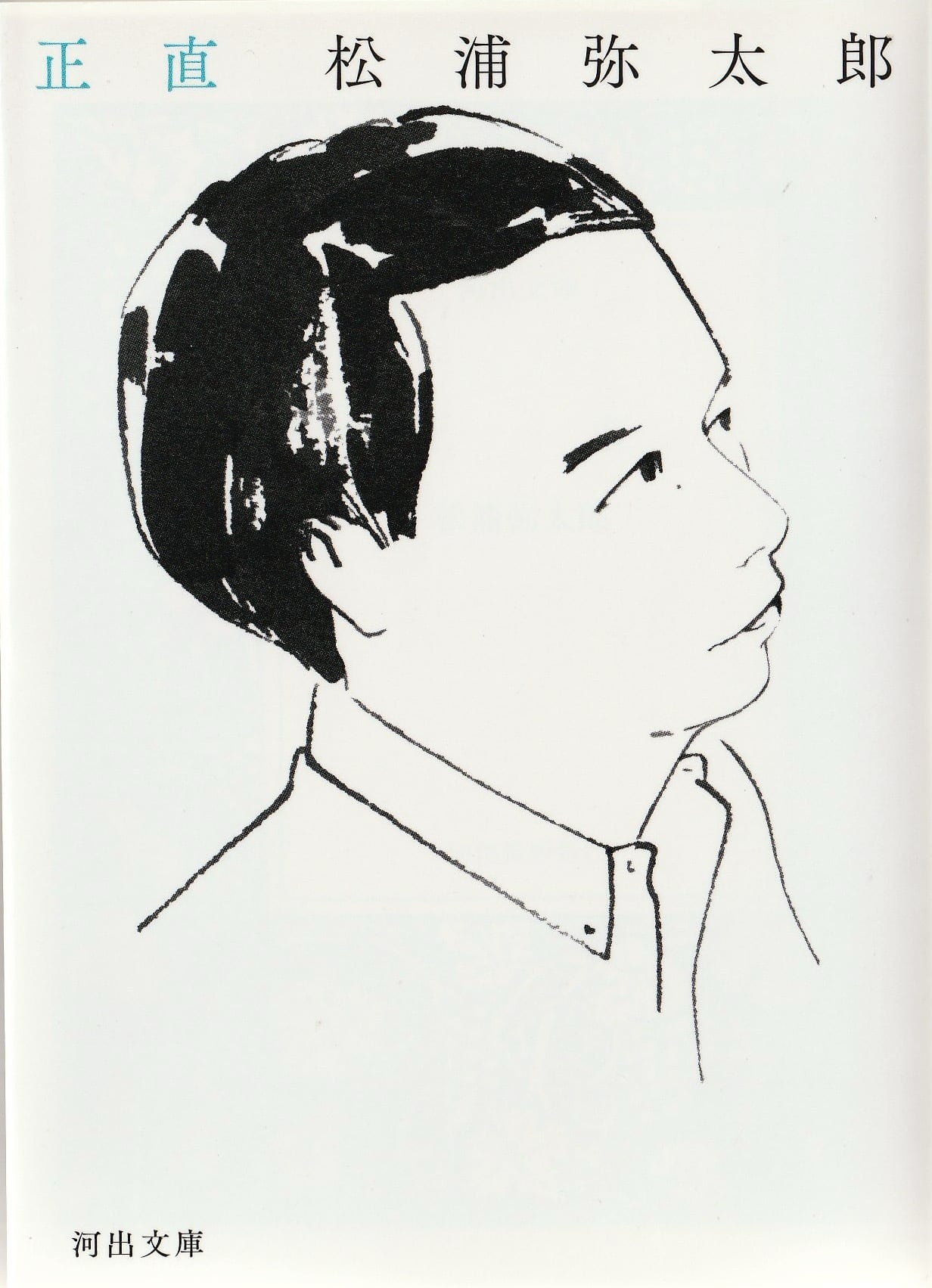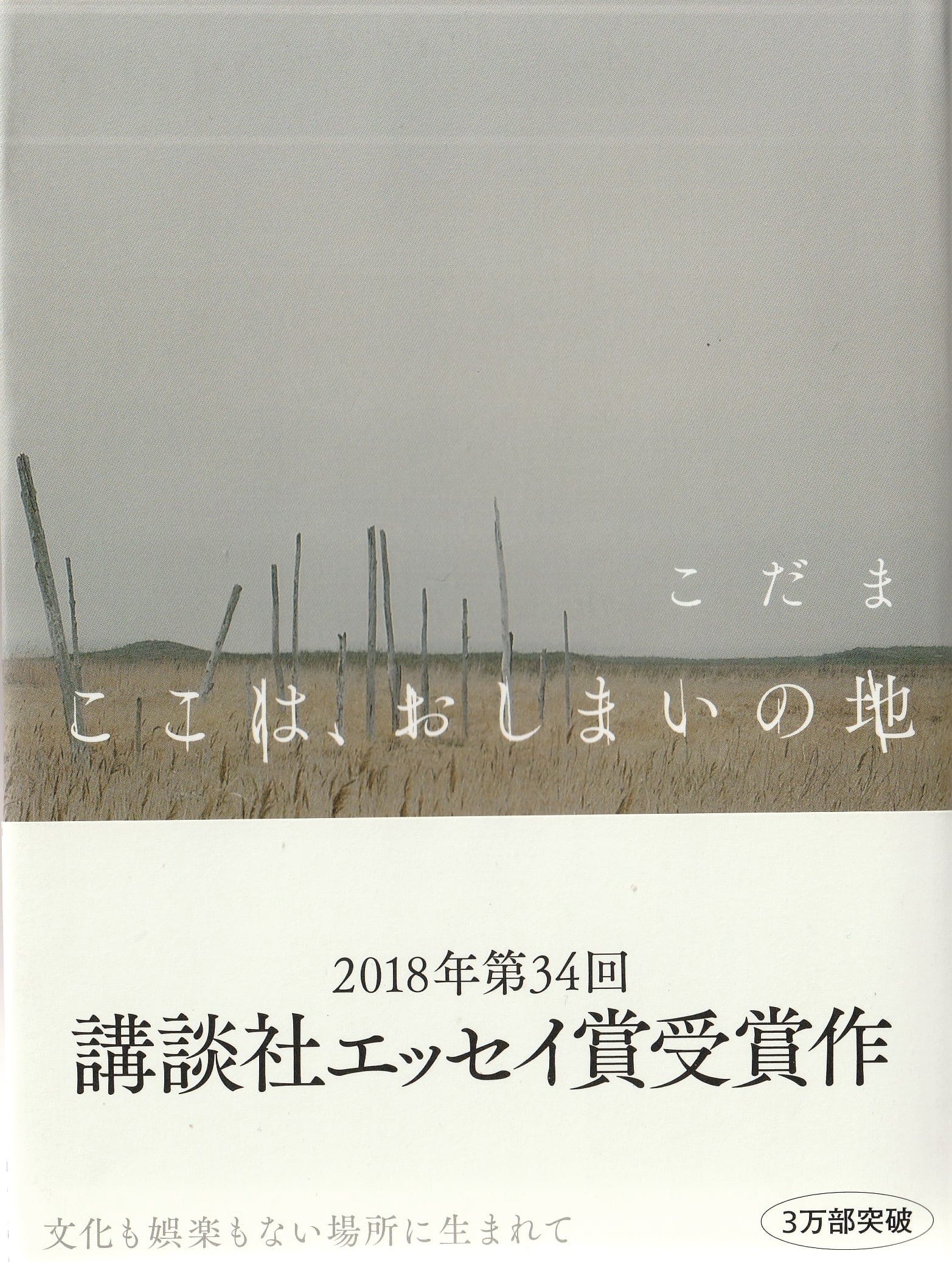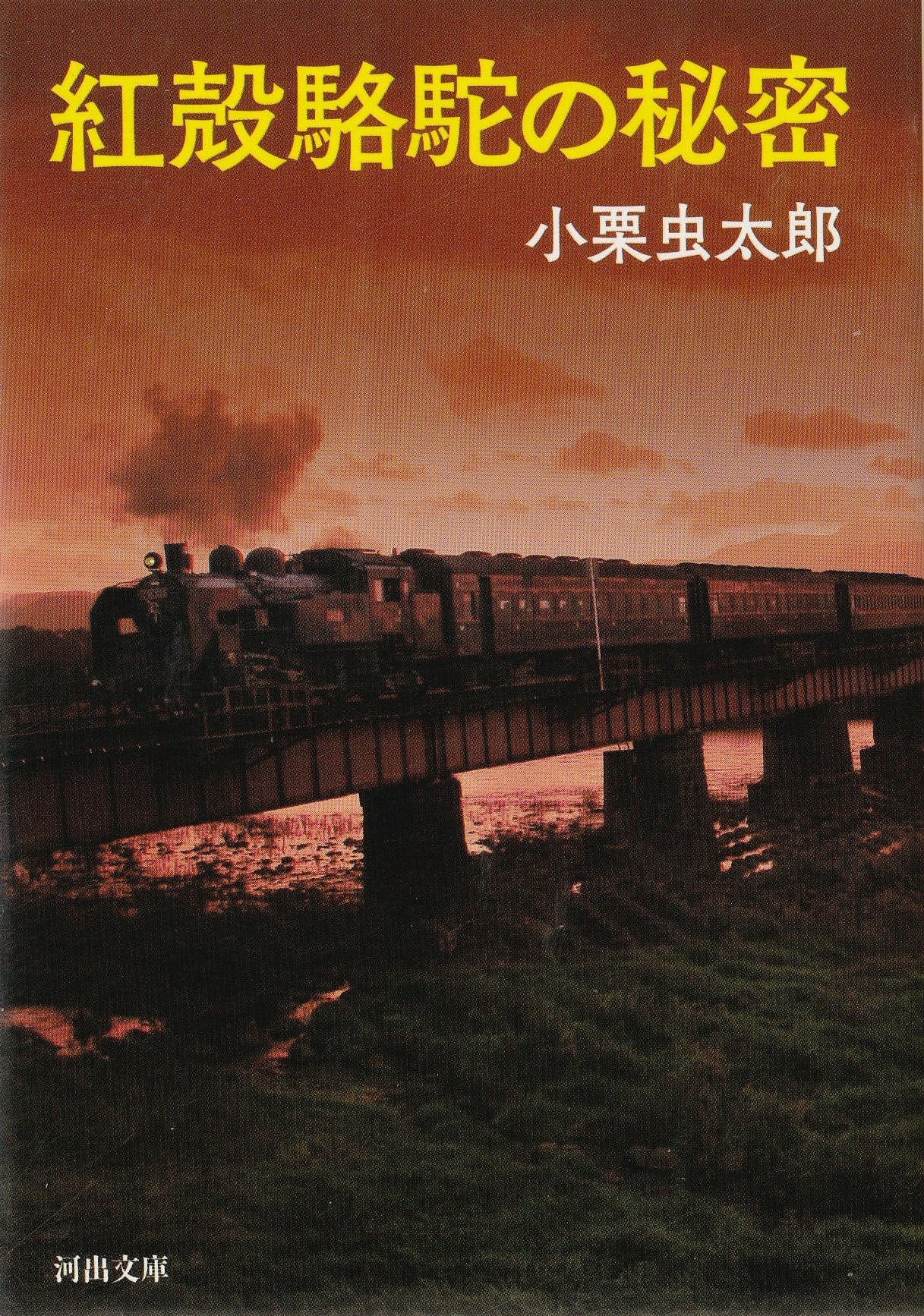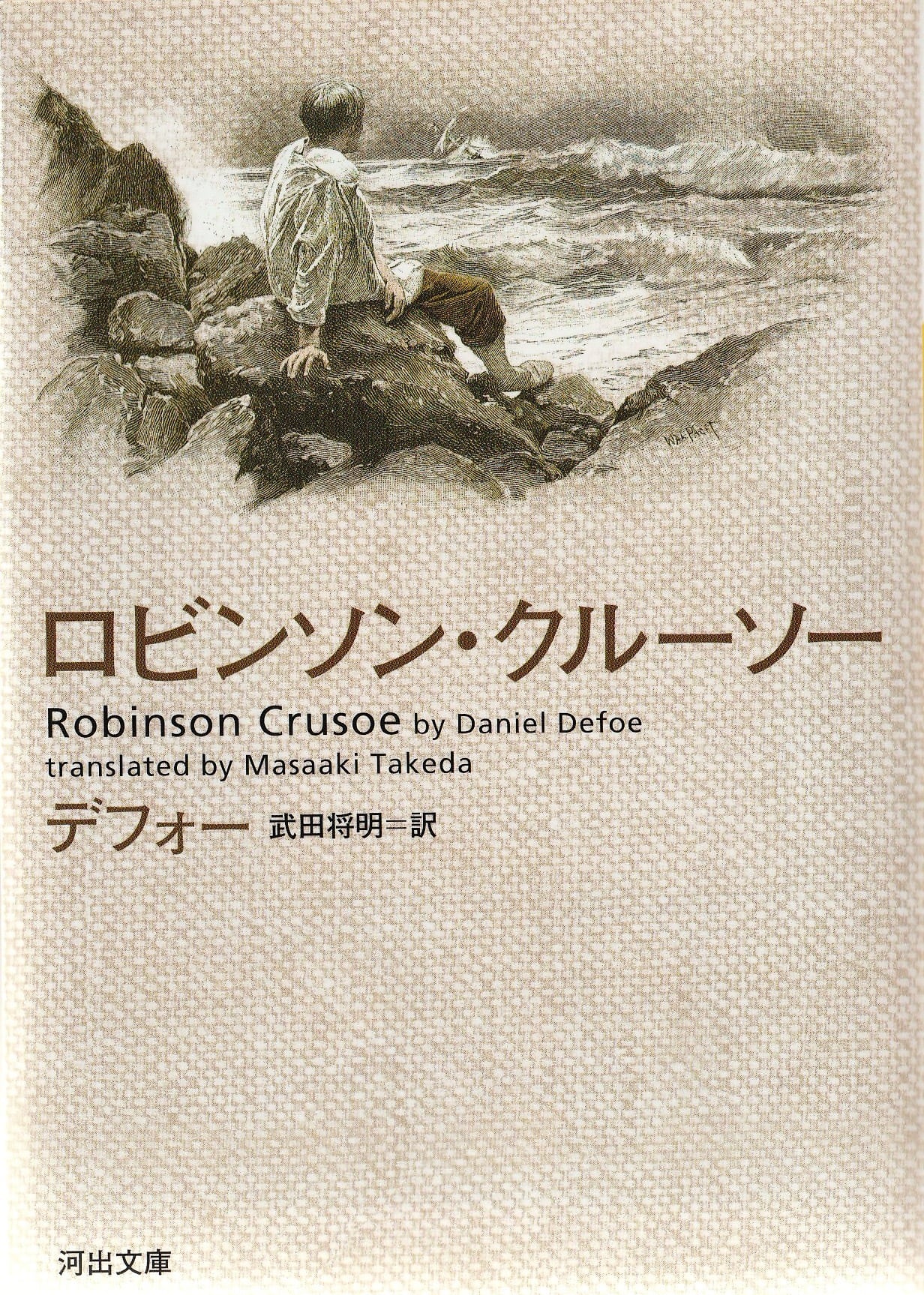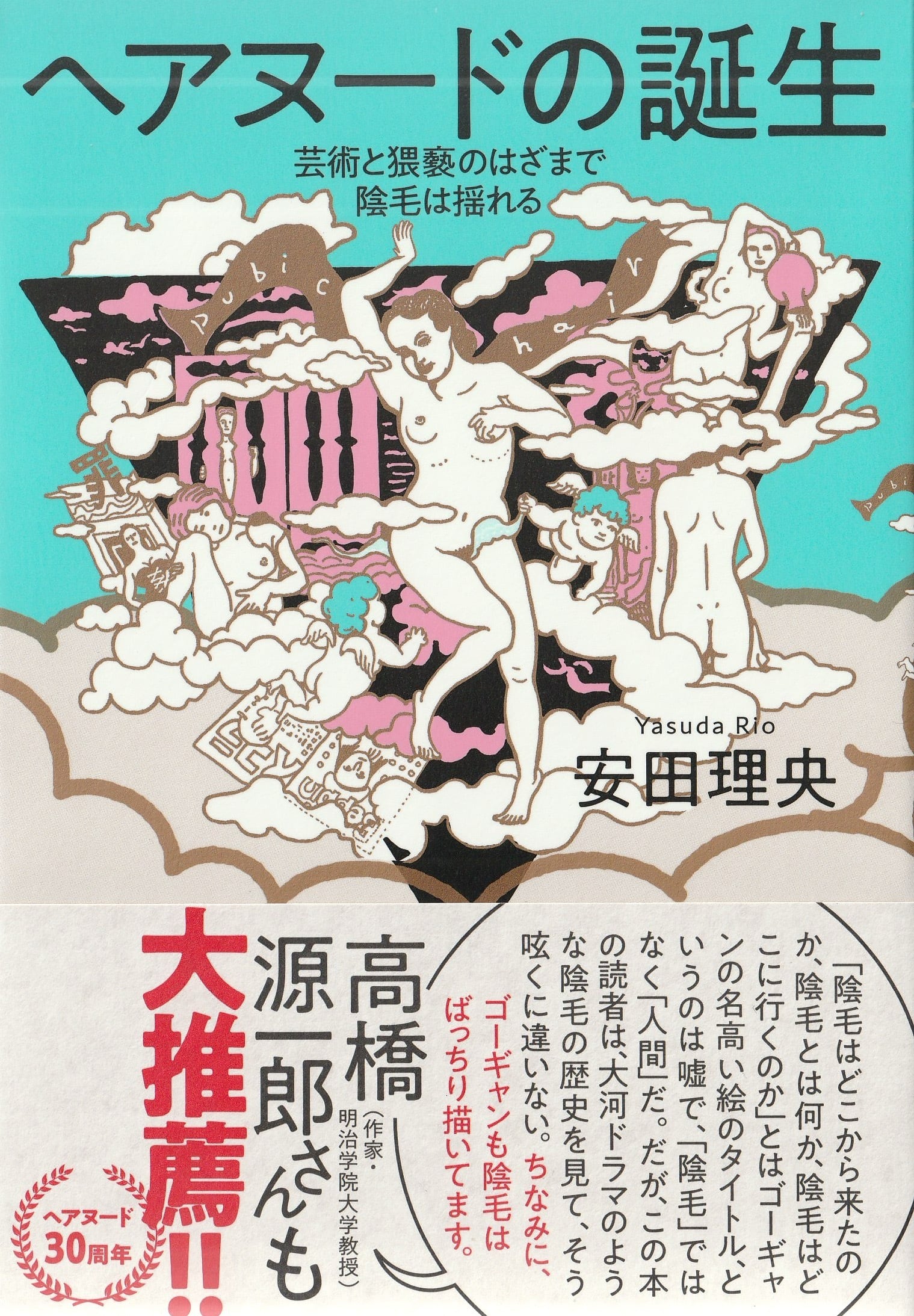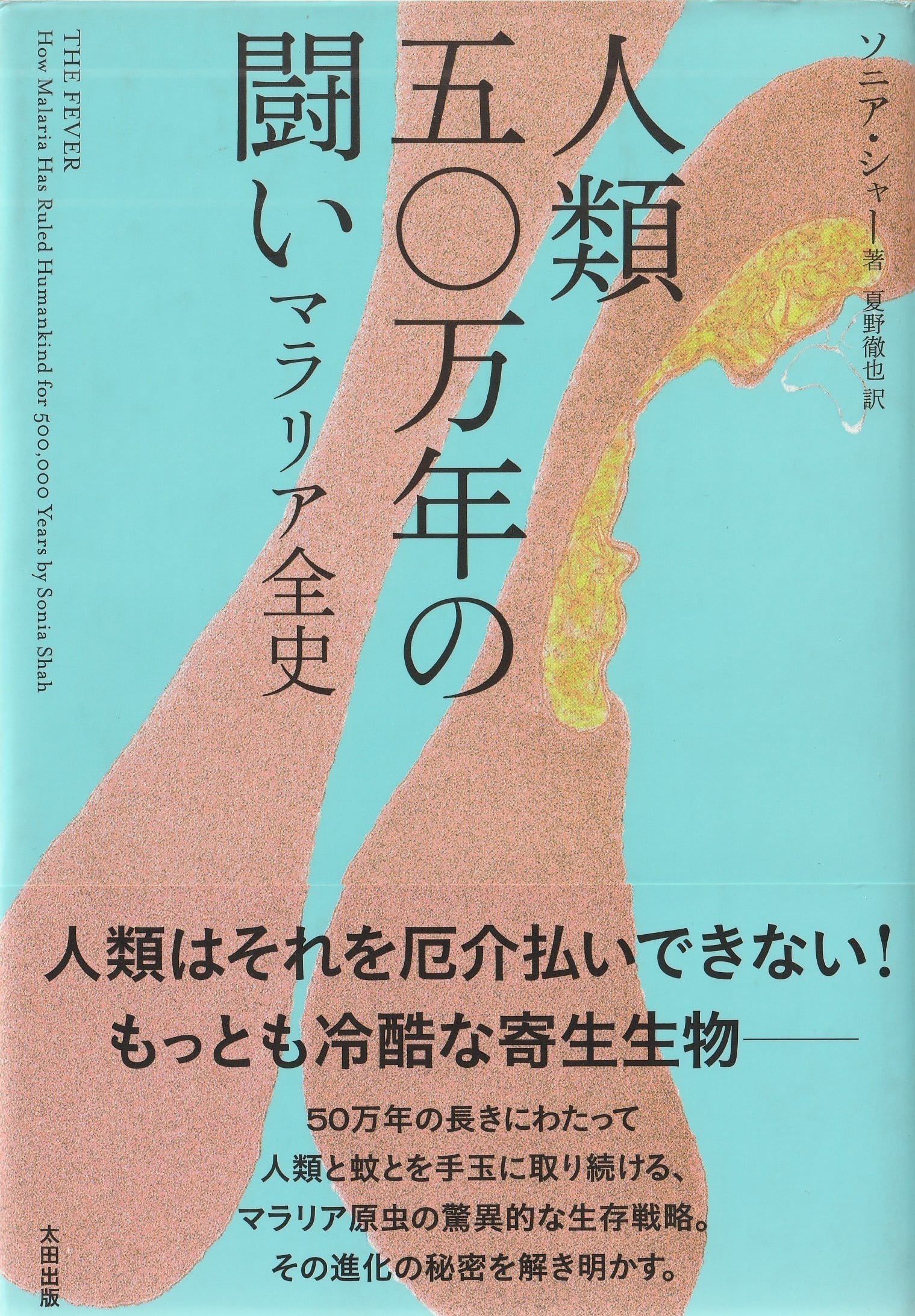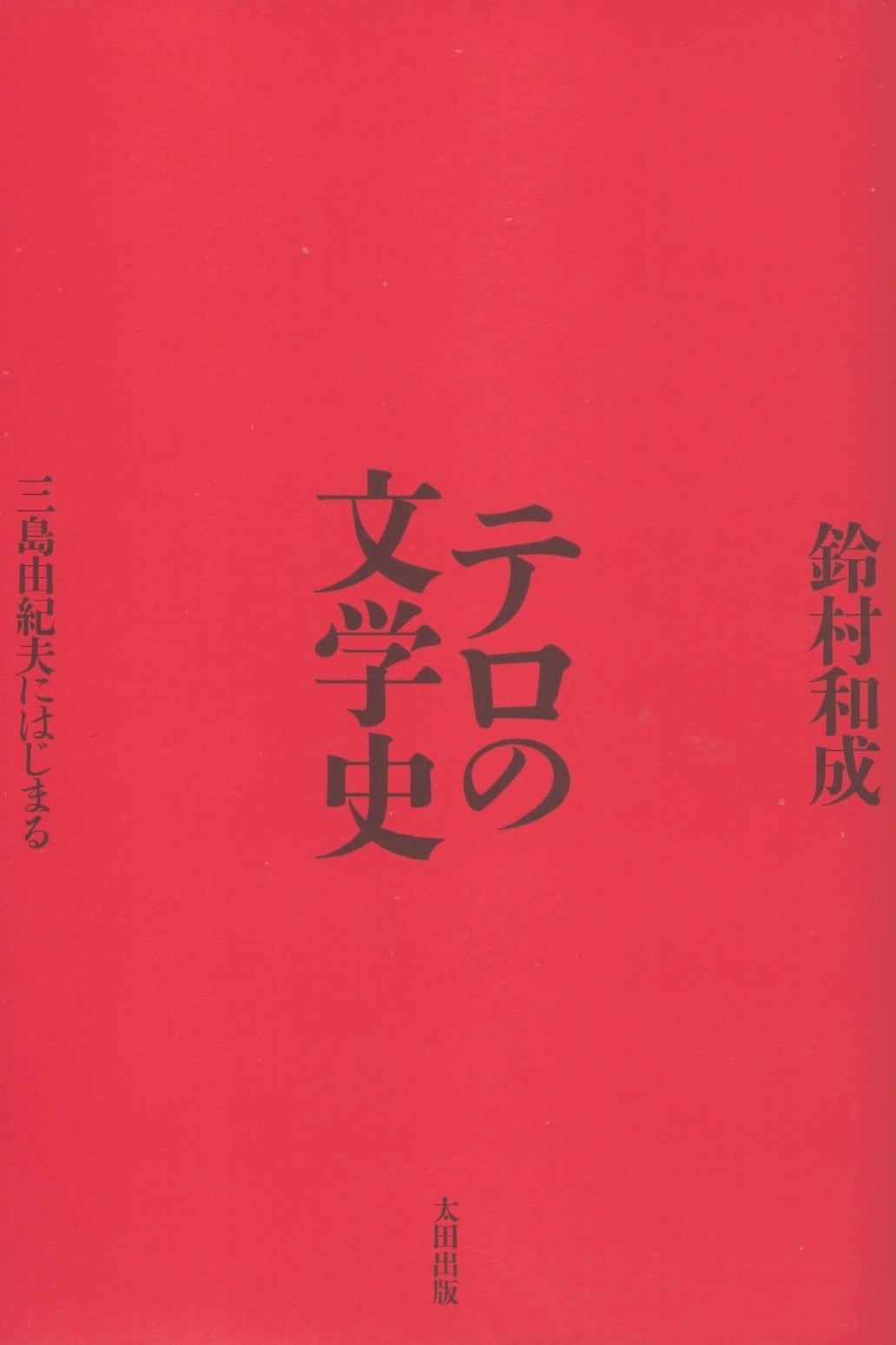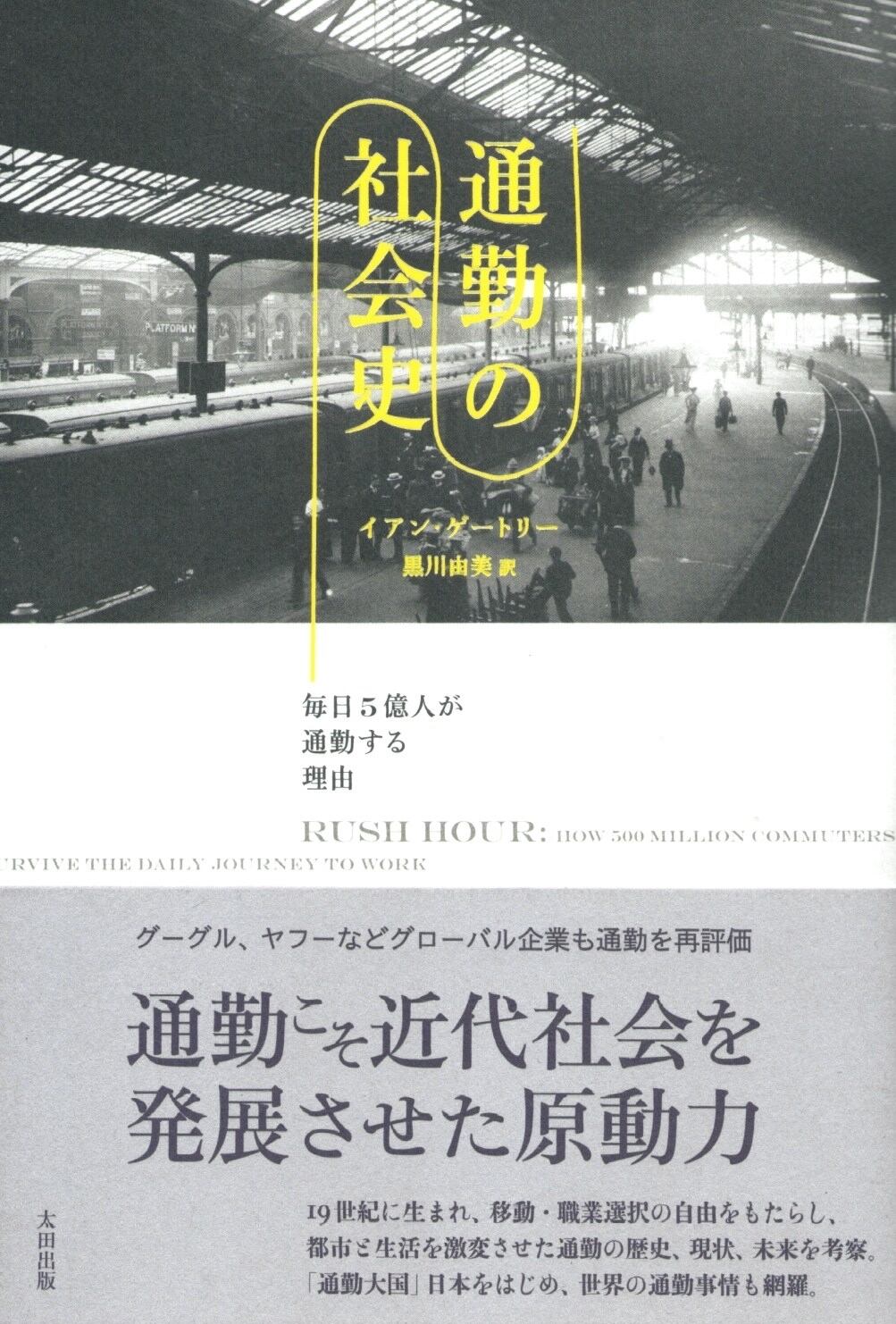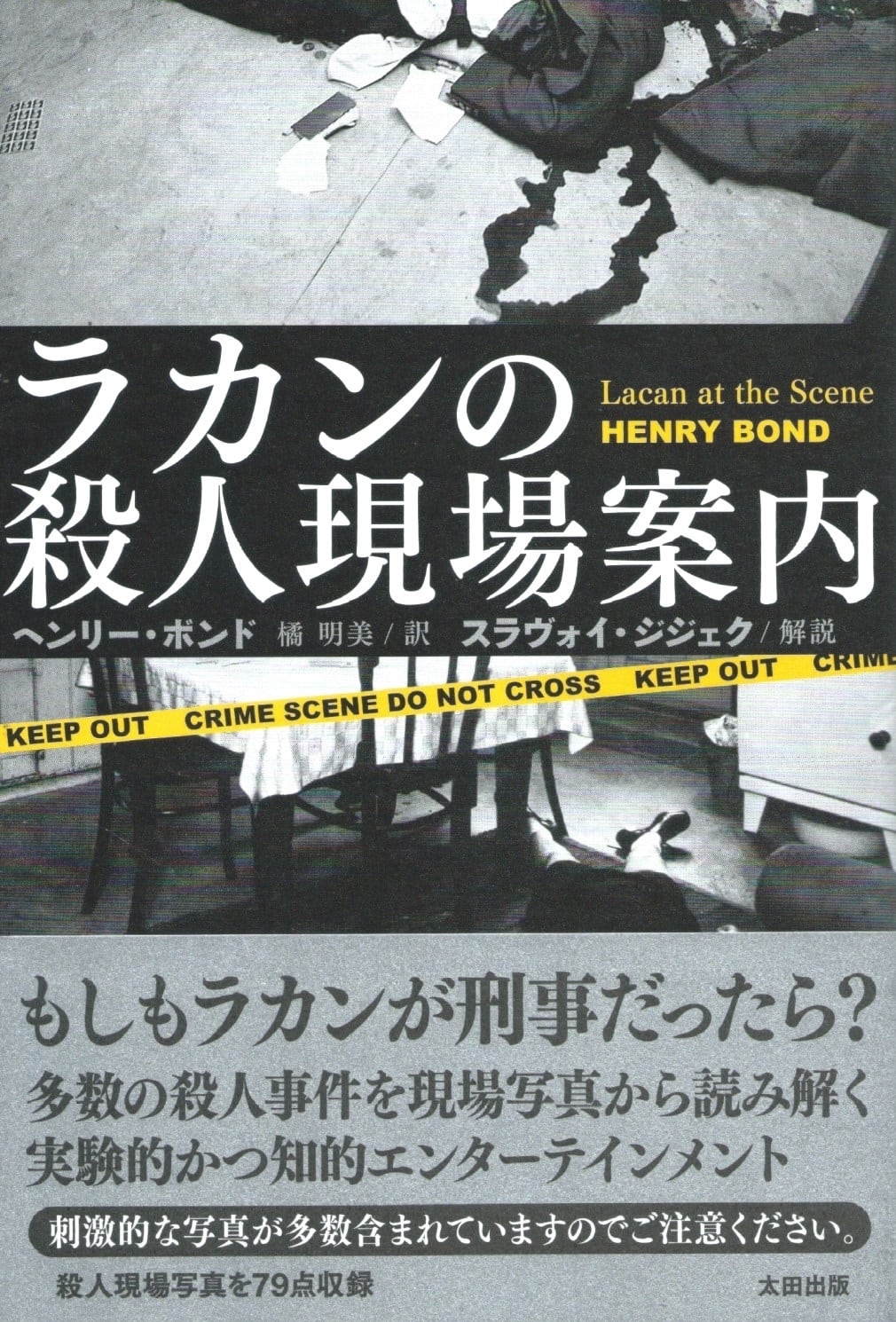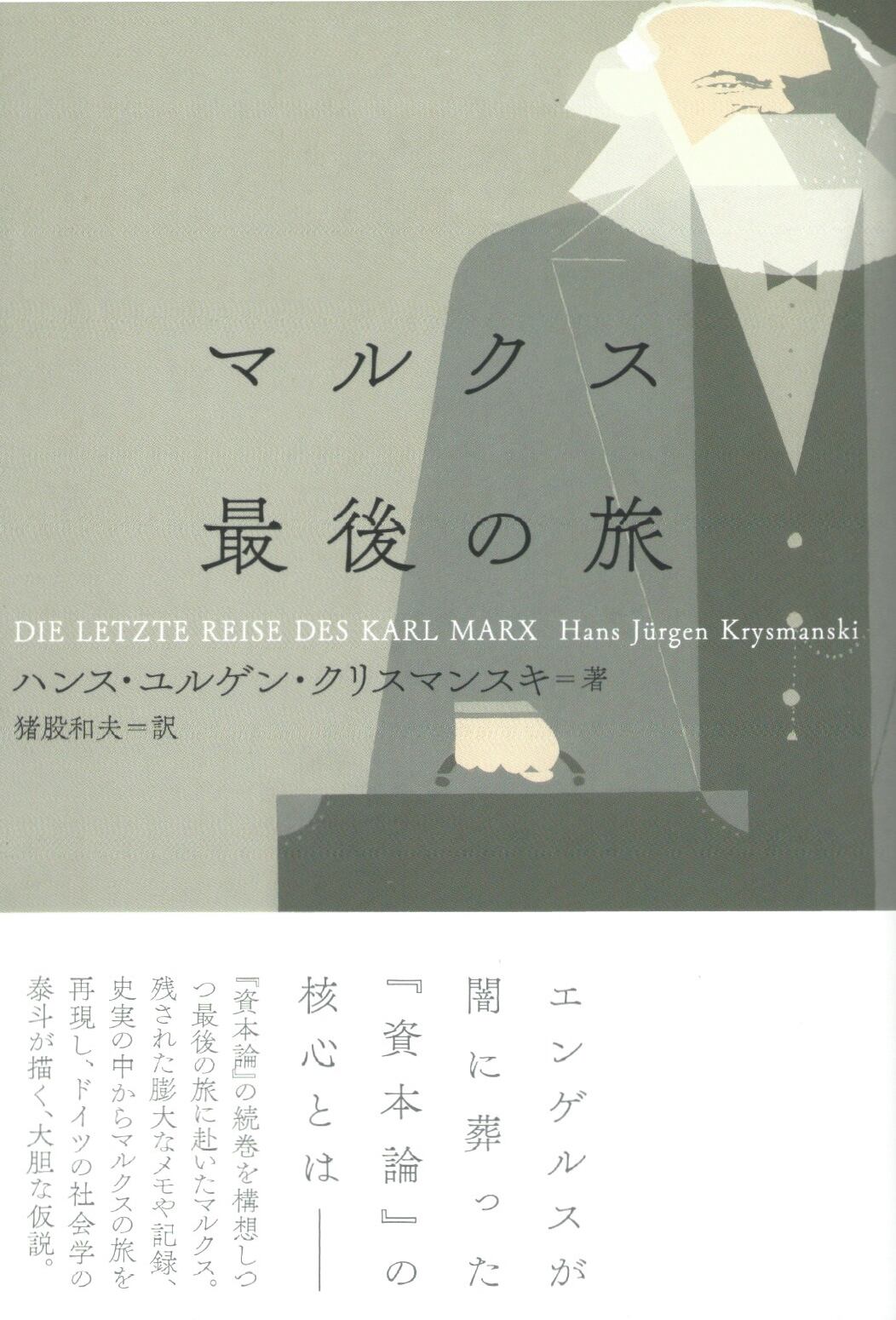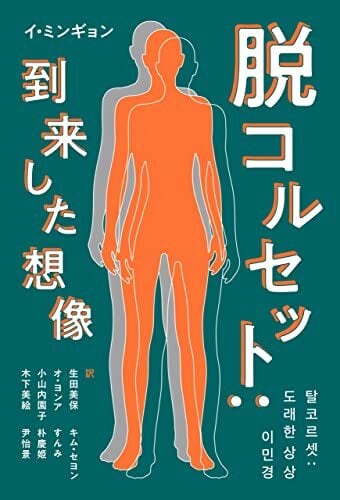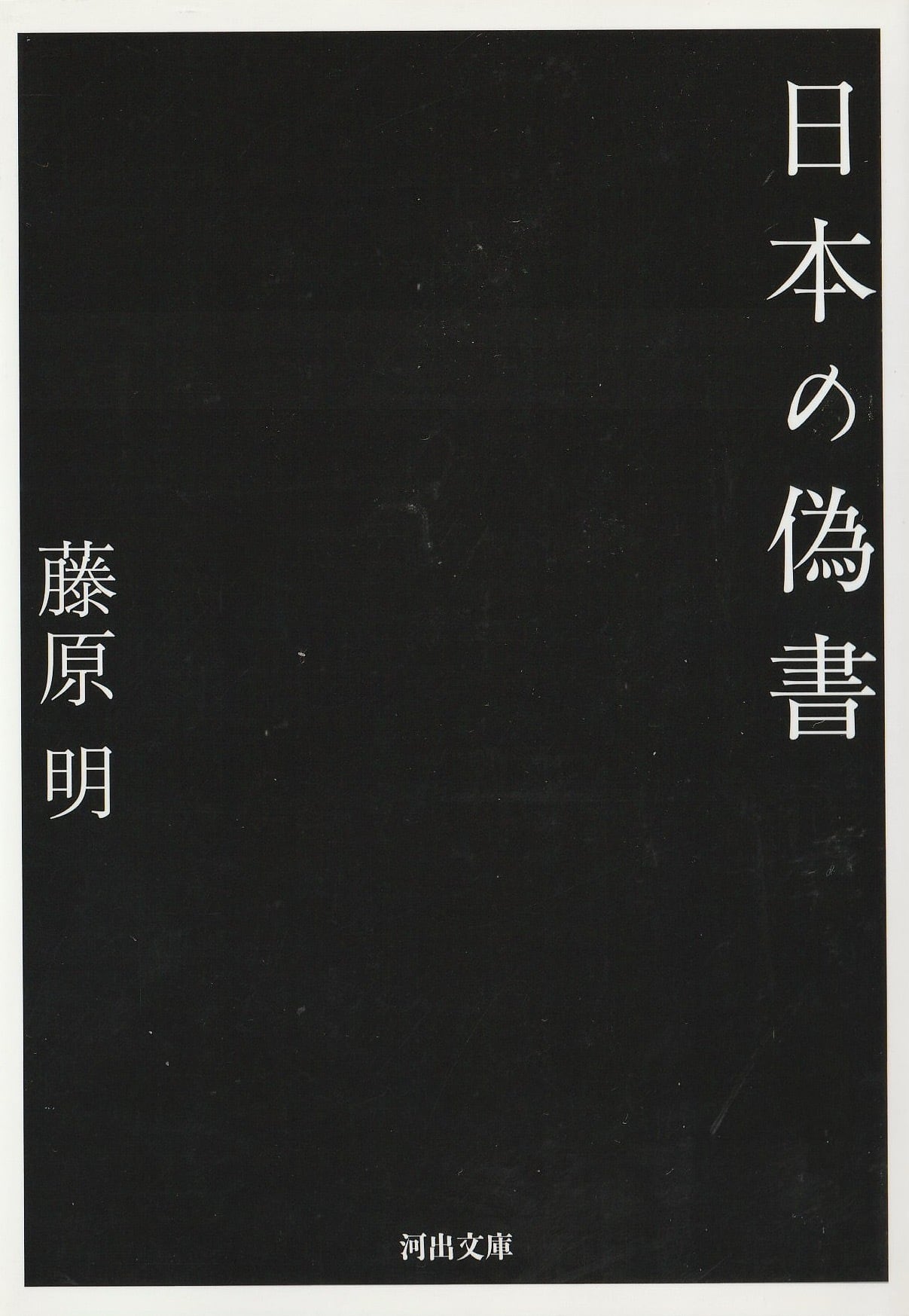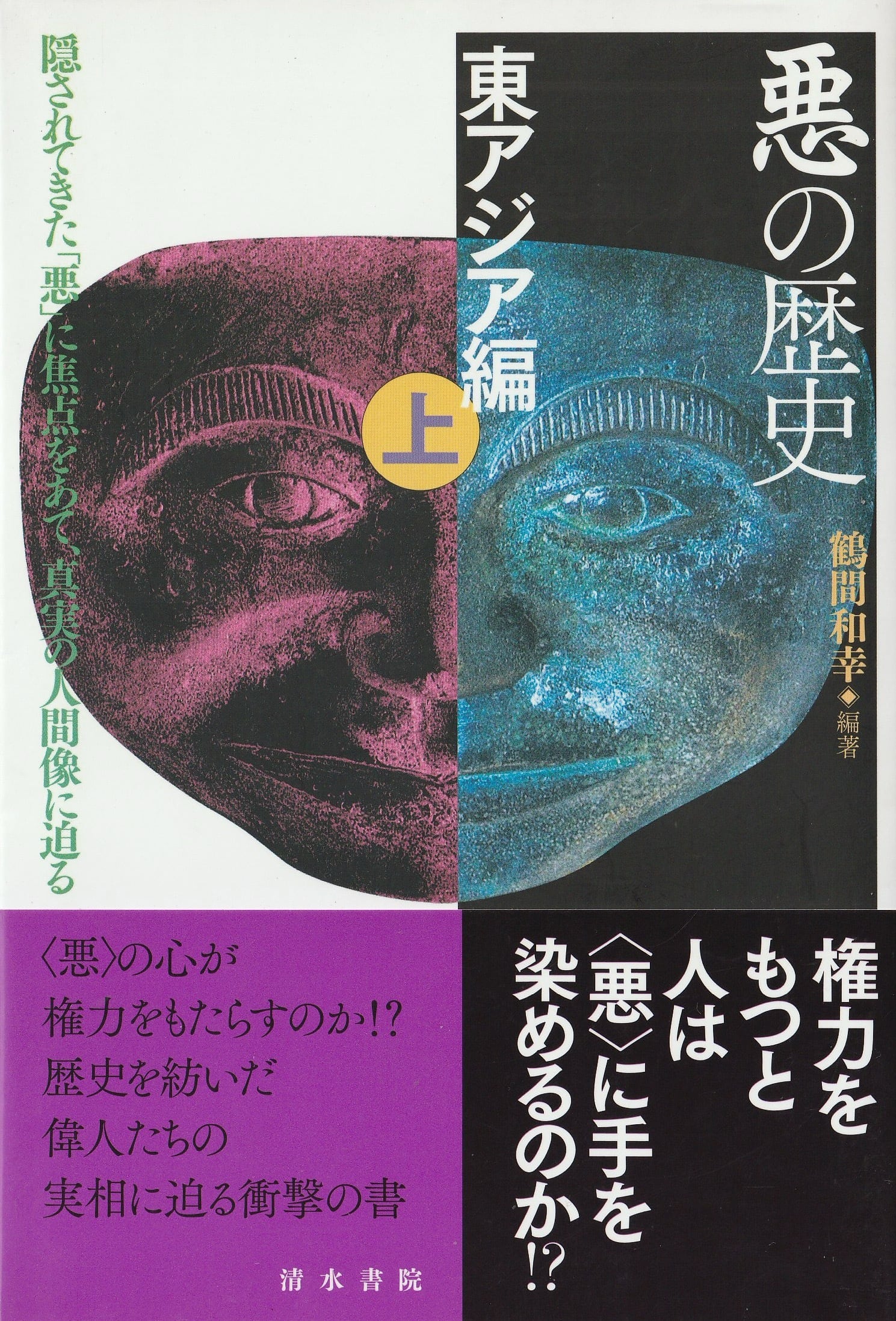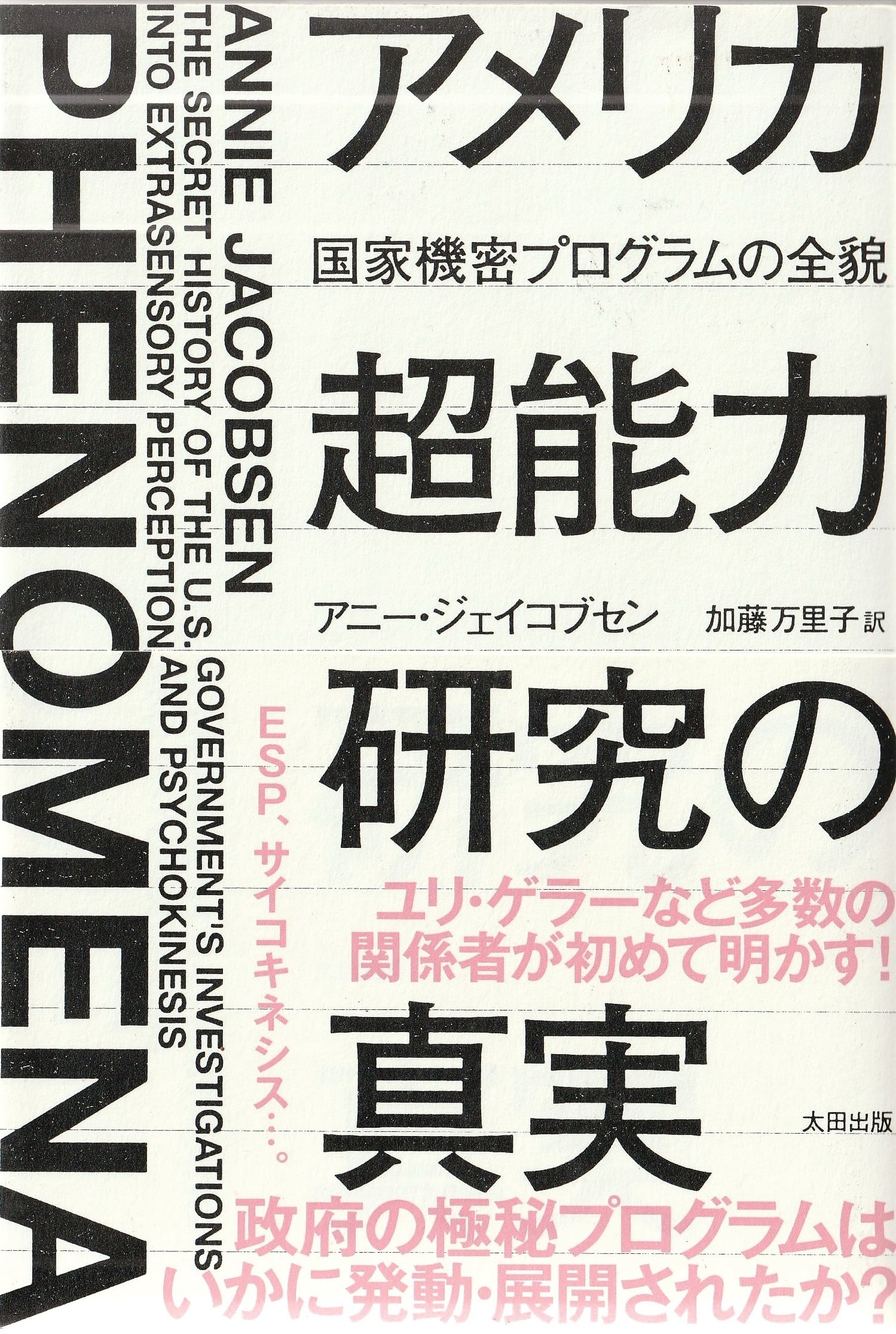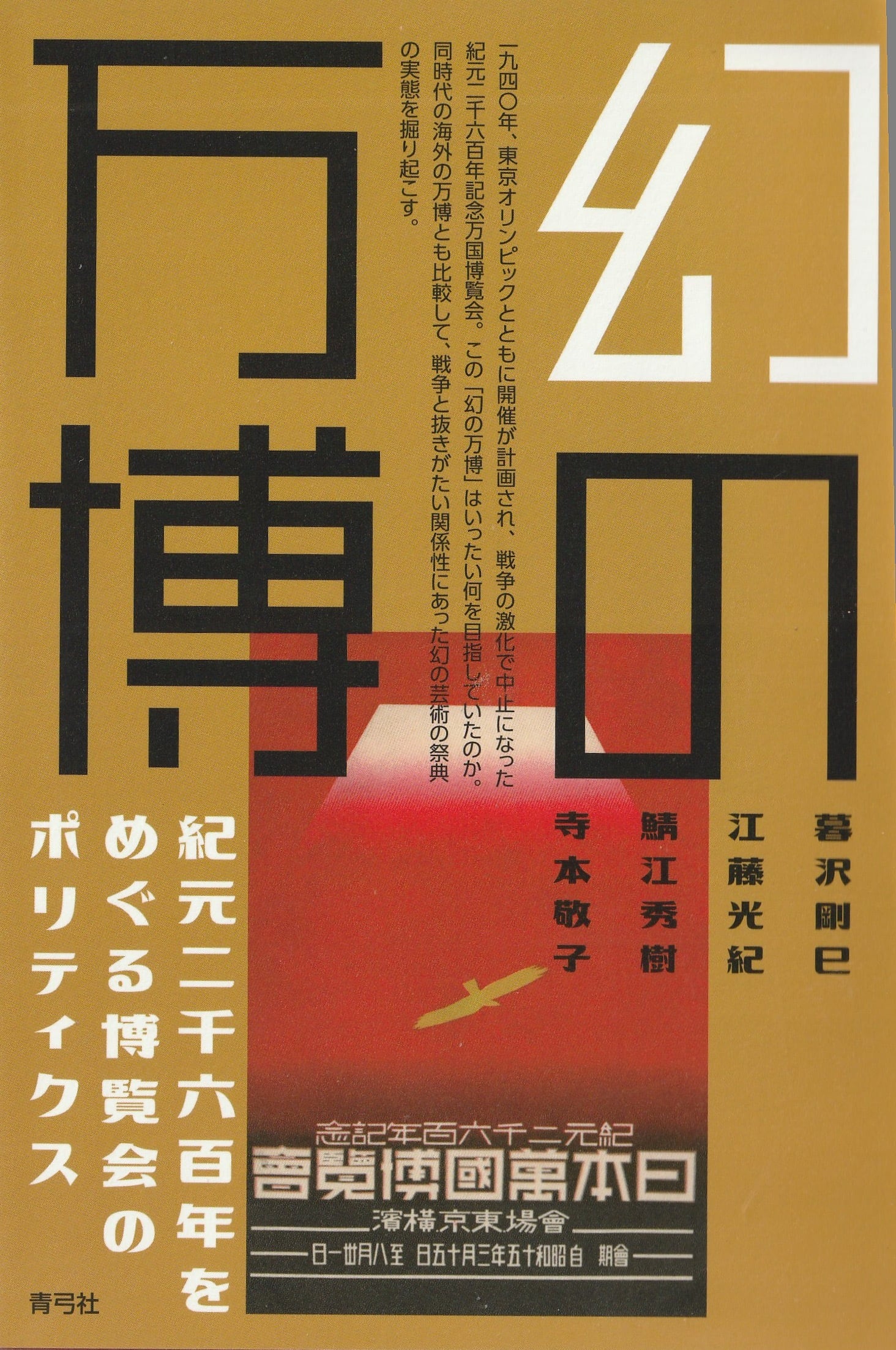調査する人生
¥2,530
長い年月をかけて対象となる社会に深く入り込み、そこで暮らす人びとの人生や生活を描くフィールドワーカーたちは、自分たちの人生もまた調査に費やしている。生活史調査で知られる著者が、打越正行、齋藤直子、丸山里美、石岡丈昇、上間陽子、朴沙羅の卓越した6人のフィールドワーカーたちと「調査する人生」を語り合う。
[出版社より]
著 者|岸政彦
出版社|岩波書店
定 価|2,300円+税
判 型|四六版/並製
頁 数|308
ISBN|9784000616720
発 行|2024年11月
Contents
序
第1回 打越正行×岸 政彦
相手の一〇年を聞くために、自分の一〇年を投じる
暴走族の中でパシリをはじめる
「大学生のくせによく頑張ってるじゃないか」
「地元」はどうやら優しい共同体ではない
ネットワーク全体の中に埋め込まれて関係性や作業が進んでいく
地元の実践感覚を数年かけて身に付けていく
パシリを引き継ぐ後輩が入ってこない
製造業は「書かれた言語」、建設業は「話し言葉」のコミュニケーションが中心
リスクを最小限にしてうまく生き残り続ける能力
暴走族が一〇年間で激減
ストレートな地元愛を聞くことはほとんどない
敬意を持つ相手は、妻や彼女を殴る男でもある
調査の初日にパクられる
いつまでたっても自分はよそもの
関わり続けたら完全に中立的ではいられない
本は燃えてもフィールドノートは燃えなかった
沈黙に耐えきれずカラオケで曲を入れてしまう
「別世界のビックリ話」で終わらせないためにどう書くか
暴力の問題を自分の問題として書く
調査対象でもフィールドワークでもなく、人生である
第2回 齋藤直子×岸 政彦
生活そのものを聞き取り続けて見えてくること
社会学との出会い
複数の「しんどさ」がつながったとき
生活史の第一人者たちから学ぶ
部落問題の調査でなにを聞くのか
生い立ちを肯定するための「自分史」運動
テーマだけを聞くのはもったいない
「何をされたか?」ではなく「どう思ったか?」 からの広がり
質的調査も量が大事
詳しくなるのはストーリーやインタビューの技術ではない
当事者と当事者でないところの接点
「社会問題が実在する」とは
差別する側のパターン化
部落問題と結婚・家制度
「結婚には反対だが差別ではない」の疑わしさ
差別する側の非合理的で過剰な拒否感
やればやるほど離れられなくなる
第3回 丸山里美×岸 政彦
簡単に理解できない、矛盾した語りを掘り下げたい
ホームレス研究から排除された女性
調査をお願いする勇気
畳の上で寝ることよりも大事なこと
「改善」より先に「理解」したい
人は矛盾を抱えて生きている
これまでの研究は「男性ホームレス研究」だった
問いの前の問い
社会学者が「責任解除」をすること
語りを理由に還元しない
語りの矛盾や飛躍こそもう一度聞く
理論がないと何十人聞いてもわからない
一つの行為に一つの理由、ではない
第4回 石岡丈昇×岸 政彦
生きていくことを正面に据えると、なかなか威勢よく言えない
「咬ませ犬」ボクサーに話を聞く
フィリピン、マニラのボクシングジムへ
なぜボクサーになるのか?
泣き真似、豪雨、ヘビ
立ち退きは「宿命」か
威勢よく言えることを可能にする条件
まだまだわかる部分があるはず
第5回 上間陽子×岸 政彦
調査する人生と支援する人生
沖縄の女性たちの調査をはじめる
インタビューって面白いな、と思った
「沖縄は絶対にやらない」と決心した院生時代
「強いコギャル」の話を書きたかったはずなのに
「話がまとまるまでいなきゃ」って思う
支援に振り切りシェルター開設
私がやっているのは、それぞれを特別扱いすること
加害者の語りをどう書けるのか
調査相手との距離・関わり方
しつこさが大事
第6回 朴 沙羅×岸 政彦
人生を書くことはできるのか
親族の生活史を聞く
テーマや問いを設定して……あれ、設定できなくない?
インタビューはコントロールできない
その場で言語化された言葉の解釈
一時間、二時間の人生、九〇年の人生
「酒がうまい」論文
「わかる」ことと「共感する」こと
「中の人」の体験の面白さ
歴史的事実と個人の語り
「歴史的な出来事」の拡張
ジャーナリズム、カウンセリング、社会学
相手が泣いてしまう経験
著者紹介
Author
岸 政彦 Masahiko Kishi
一九六七年生まれ。京都大学大学院文学研究科教授。社会学。専門は沖縄社会研究、生活史、社会調査方法論。主な著作に『同化と他者化――戦後沖縄の本土就職者たち』(ナカニシヤ出版、二〇一三年)、『街の人生』(勁草書房、二〇一四年)、『断片的なものの社会学』(朝日出版社、二〇一五年、紀伊國屋じんぶん大賞二〇一六受賞)、『質的社会調査の方法――他者の合理性の理解社会学』(石岡丈昇・丸山里美と共著、有斐閣ストゥディア、二〇一六年)、『はじめての沖縄』(新曜社、二〇一八年)、『マンゴーと手榴弾――生活史の理論』(勁草書房、二〇一八年)、『社会学はどこから来てどこへ行くのか』(北田暁大・筒井淳也・稲葉振一郎と共著、有斐閣、二〇一八年)、『100分de名著ブルデュー「ディスタンクシオン」』(NHK出版、二〇二〇年)、『地元を生きる――沖縄的共同性の社会学』(打越正行・上原健太郎・上間陽子と共著、ナカニシヤ出版、二〇二〇年)、『生活史論集』(編著、ナカニシヤ出版、二〇二二年)、『東京の生活史』(編著、筑摩書房、二〇二一年、紀伊國屋じんぶん大賞二〇二二受賞)、『沖縄の生活史』(石原昌家と共同監修、沖縄タイムス社編、二〇二三年、みすず書房)、『大阪の生活史』(編著、筑摩書房、二〇二三年)など。「岩波講座社会学」編集委員。
戦後沖縄の本土就職とUターンにおけるアイデンティティの歴史的構築、沖縄的共同性と階層格差という二つの大きな調査プロジェクトを終えて、現在は沖縄戦の生活史調査をおこなっている。あわせて『街の人生』『東京の生活史』などのスタイルで「生活史モノグラフ」を書いている。
打越 正行 Masayuki Uchikoshi
一九七九年生まれ。和光大学現代人間学部講師。社会学。専門は沖縄、参与観察法。主な著書に『ヤンキーと地元――解体屋、風俗経営者、ヤミ業者になった沖縄の若者たち』(筑摩書房、二〇一九年(ちくま文庫、二〇二四年)、第六回沖縄書店大賞・沖縄部門大賞受賞)、『最強の社会調査入門――これから質的調査をはじめる人のために』(前田拓也ほか編、ナカニシヤ出版、二〇一六年)、『地元を生きる――沖縄的共同性の社会学』(岸 政彦・上原健太郎・上間陽子と共著、ナカニシヤ出版、二〇二〇年)、『〈生活―文脈〉理解のすすめ――他者と生きる日常生活に向けて』(宮内洋・松宮朝・新藤慶と共著、北大路書房、二〇二四年)など。
沖縄を中心に暴走族・ヤンキーの若者を対象とした、参与観察調査をおこなっている。
齋藤 直子 Naoko Saito
一九七三年生まれ。大阪教育大学総合教育系特任准教授。社会学。専門は部落問題研究、家族社会学。主な著書に『結婚差別の社会学』(勁草書房、二〇一七年)、『入門家族社会学』(共著、新泉社、二〇一七年)、Educaciones y Racismos, Reflexiones y casos(共著、el Centro Universitario del Norte en Universidad de Guadalajara y Universidad Pedagógica Nacional, 2021)、『恋愛社会学――多様化する親密な関係に接近する』(共著、ナカニシヤ出版、二〇二四年)など、論文に「交差性をときほぐす――部落差別と女性差別の交差とその変容過程」(『ソシオロジ』第六六巻一号、社会学研究会、二〇二一年)など。
被差別部落出身者への結婚差別問題、部落女性をめぐる交差性、被差別部落へ/からの転入/転出、部落問題と「家」の関係性などについて研究している。
丸山 里美 Satomi Maruyama
一九七六年生まれ。京都大学大学院文学研究科准教授。社会学。専門はホームレス、貧困、ジェンダー研究、福祉社会学。主な著書に『女性ホームレスとして生きる――貧困と排除の社会学』(世界思想社、二〇一三年(増補新装版二〇二一年))、『質的社会調査の方法――他者の合理性の理解社会学』(岸 政彦・石岡丈昇と共著、有斐閣ストゥディア、二〇一六年)、『貧困問題の新地平――〈もやい〉の相談活動の軌跡』(編著、旬報社、二〇一八年)、Living on the Streets in Japan: Homeless Women Break their Silence(Trans Pacific Press, 2018)、『女性たちで子を産み育てるということ――精子提供による家族づくり』(牟田和恵・岡野八代と共著、白澤社、二〇二一年)などがある。「岩波講座 社会学」編集委員。
大学院在籍時から、女性ホームレスを対象に、ジェンダー化された貧困の様相をとらえる研究をおこなってきた。最近は、世帯のなかに隠れた貧困や、貧困の概念や把握の仕方について、ジェンダーの視点から研究している。
石岡 丈昇 Tomonori Ishioka
一九七七年生まれ。日本大学文理学部教授。社会学。専門は身体文化論、都市エスノグラフィー研究。主な著書に『ローカルボクサーと貧困世界――マニラのボクシングジムにみる身体文化』(世界思想社、二〇一二年(増補新装版 二〇二四年)、第一二回日本社会学会奨励賞・著書の部受賞)、Southern Hemisphere Ethnographies of Space, Place, and Time(共著、R. Rinehart eds., Peter Lang, 2018)、『タイミングの社会学――ディテールを書くエスノグラフィー』(青土社、二〇二三年)、『エスノグラフィ入門』(ちくま新書、二〇二四年)など。
フィリピン・マニラの貧困世界を事例に、ボクシングジムやスクオッター地帯を調査しながら、貧困を生きる人びとの生活実践を記述している。現在は、身体と時間の関係を「タイミングの社会学」という切り口から、理論的に考察する仕事をおこなっている。
上間 陽子 Yoko Uema
一九七二年生まれ。琉球大学教育学研究科教授。教育学。主な著書に、『裸足で逃げる――沖縄の夜の街の少女たち』(太田出版、二〇一七年)、『海をあげる』(筑摩書房、二〇二〇年、Yahoo!ニュース|本屋大賞2021ノンフィクション本大賞受賞、池田晶子記念わたくし、つまりNobody賞受賞、沖縄書店大賞受賞)、『沖縄子どもの貧困白書』(加藤彰彦・鎌田佐多子・金城隆一・小田切忠人と共編、かもがわ出版、二〇一七年)、『誰も置き去りにしない社会へ――貧困・格差の現場から』(平松知子ほかと共著、新日本出版社、二〇一八年)、『地元を生きる――沖縄的共同性の社会学』(岸政彦・打越正行・上原健太郎と共著、ナカニシヤ出版、二〇二〇年)、『復帰50年沖縄子ども白書2022』(川武啓介・北上田源・島村聡・二宮千賀子・山野良一・横江崇と共編、かもがわ出版、二〇二二年)など。
学校から逸脱する少年・少女や沖縄の貧困などについて学校内・学校外から調査してきた。現在は若年女性の特定妊婦の出産・子育ての応援シェルター「おにわ」の代表として支援もおこなっている。
朴 沙羅 Sara Park
一九八四年生まれ。ヘルシンキ大学文学部講師。社会学。専門はナショナリズム研究、社会調査方法論。主な著作に『外国人をつくりだす――戦後日本における「密航」と入国管理制度の運用』(ナカニシヤ出版、二〇一七年)、『家の歴史を書く』(筑摩書房、二〇一八年(ちくま文庫、二〇二二年))、『ヘルシンキ 生活の練習』(筑摩書房、二〇二一年(ちくま文庫、二〇二四年))、『ヘルシンキ 生活の練習は続く』(筑摩書房、二〇二四年)、『記憶を語る、歴史を書く――オーラルヒストリーと社会調査』(有斐閣、二〇二三年)ほか、論文に “Colonialism and Sisterhood: Japanese Female Activists and the ‘Comfort Women’ Issue”(Critical Sociology, 2019)など。
戦後日本における出入国管理政策の歴史を調査しつつ、歴史認識とオーラルヒストリー収集プロジェクトとの関係も調査している。
[出版社より]
著 者|岸政彦
出版社|岩波書店
定 価|2,300円+税
判 型|四六版/並製
頁 数|308
ISBN|9784000616720
発 行|2024年11月
Contents
序
第1回 打越正行×岸 政彦
相手の一〇年を聞くために、自分の一〇年を投じる
暴走族の中でパシリをはじめる
「大学生のくせによく頑張ってるじゃないか」
「地元」はどうやら優しい共同体ではない
ネットワーク全体の中に埋め込まれて関係性や作業が進んでいく
地元の実践感覚を数年かけて身に付けていく
パシリを引き継ぐ後輩が入ってこない
製造業は「書かれた言語」、建設業は「話し言葉」のコミュニケーションが中心
リスクを最小限にしてうまく生き残り続ける能力
暴走族が一〇年間で激減
ストレートな地元愛を聞くことはほとんどない
敬意を持つ相手は、妻や彼女を殴る男でもある
調査の初日にパクられる
いつまでたっても自分はよそもの
関わり続けたら完全に中立的ではいられない
本は燃えてもフィールドノートは燃えなかった
沈黙に耐えきれずカラオケで曲を入れてしまう
「別世界のビックリ話」で終わらせないためにどう書くか
暴力の問題を自分の問題として書く
調査対象でもフィールドワークでもなく、人生である
第2回 齋藤直子×岸 政彦
生活そのものを聞き取り続けて見えてくること
社会学との出会い
複数の「しんどさ」がつながったとき
生活史の第一人者たちから学ぶ
部落問題の調査でなにを聞くのか
生い立ちを肯定するための「自分史」運動
テーマだけを聞くのはもったいない
「何をされたか?」ではなく「どう思ったか?」 からの広がり
質的調査も量が大事
詳しくなるのはストーリーやインタビューの技術ではない
当事者と当事者でないところの接点
「社会問題が実在する」とは
差別する側のパターン化
部落問題と結婚・家制度
「結婚には反対だが差別ではない」の疑わしさ
差別する側の非合理的で過剰な拒否感
やればやるほど離れられなくなる
第3回 丸山里美×岸 政彦
簡単に理解できない、矛盾した語りを掘り下げたい
ホームレス研究から排除された女性
調査をお願いする勇気
畳の上で寝ることよりも大事なこと
「改善」より先に「理解」したい
人は矛盾を抱えて生きている
これまでの研究は「男性ホームレス研究」だった
問いの前の問い
社会学者が「責任解除」をすること
語りを理由に還元しない
語りの矛盾や飛躍こそもう一度聞く
理論がないと何十人聞いてもわからない
一つの行為に一つの理由、ではない
第4回 石岡丈昇×岸 政彦
生きていくことを正面に据えると、なかなか威勢よく言えない
「咬ませ犬」ボクサーに話を聞く
フィリピン、マニラのボクシングジムへ
なぜボクサーになるのか?
泣き真似、豪雨、ヘビ
立ち退きは「宿命」か
威勢よく言えることを可能にする条件
まだまだわかる部分があるはず
第5回 上間陽子×岸 政彦
調査する人生と支援する人生
沖縄の女性たちの調査をはじめる
インタビューって面白いな、と思った
「沖縄は絶対にやらない」と決心した院生時代
「強いコギャル」の話を書きたかったはずなのに
「話がまとまるまでいなきゃ」って思う
支援に振り切りシェルター開設
私がやっているのは、それぞれを特別扱いすること
加害者の語りをどう書けるのか
調査相手との距離・関わり方
しつこさが大事
第6回 朴 沙羅×岸 政彦
人生を書くことはできるのか
親族の生活史を聞く
テーマや問いを設定して……あれ、設定できなくない?
インタビューはコントロールできない
その場で言語化された言葉の解釈
一時間、二時間の人生、九〇年の人生
「酒がうまい」論文
「わかる」ことと「共感する」こと
「中の人」の体験の面白さ
歴史的事実と個人の語り
「歴史的な出来事」の拡張
ジャーナリズム、カウンセリング、社会学
相手が泣いてしまう経験
著者紹介
Author
岸 政彦 Masahiko Kishi
一九六七年生まれ。京都大学大学院文学研究科教授。社会学。専門は沖縄社会研究、生活史、社会調査方法論。主な著作に『同化と他者化――戦後沖縄の本土就職者たち』(ナカニシヤ出版、二〇一三年)、『街の人生』(勁草書房、二〇一四年)、『断片的なものの社会学』(朝日出版社、二〇一五年、紀伊國屋じんぶん大賞二〇一六受賞)、『質的社会調査の方法――他者の合理性の理解社会学』(石岡丈昇・丸山里美と共著、有斐閣ストゥディア、二〇一六年)、『はじめての沖縄』(新曜社、二〇一八年)、『マンゴーと手榴弾――生活史の理論』(勁草書房、二〇一八年)、『社会学はどこから来てどこへ行くのか』(北田暁大・筒井淳也・稲葉振一郎と共著、有斐閣、二〇一八年)、『100分de名著ブルデュー「ディスタンクシオン」』(NHK出版、二〇二〇年)、『地元を生きる――沖縄的共同性の社会学』(打越正行・上原健太郎・上間陽子と共著、ナカニシヤ出版、二〇二〇年)、『生活史論集』(編著、ナカニシヤ出版、二〇二二年)、『東京の生活史』(編著、筑摩書房、二〇二一年、紀伊國屋じんぶん大賞二〇二二受賞)、『沖縄の生活史』(石原昌家と共同監修、沖縄タイムス社編、二〇二三年、みすず書房)、『大阪の生活史』(編著、筑摩書房、二〇二三年)など。「岩波講座社会学」編集委員。
戦後沖縄の本土就職とUターンにおけるアイデンティティの歴史的構築、沖縄的共同性と階層格差という二つの大きな調査プロジェクトを終えて、現在は沖縄戦の生活史調査をおこなっている。あわせて『街の人生』『東京の生活史』などのスタイルで「生活史モノグラフ」を書いている。
打越 正行 Masayuki Uchikoshi
一九七九年生まれ。和光大学現代人間学部講師。社会学。専門は沖縄、参与観察法。主な著書に『ヤンキーと地元――解体屋、風俗経営者、ヤミ業者になった沖縄の若者たち』(筑摩書房、二〇一九年(ちくま文庫、二〇二四年)、第六回沖縄書店大賞・沖縄部門大賞受賞)、『最強の社会調査入門――これから質的調査をはじめる人のために』(前田拓也ほか編、ナカニシヤ出版、二〇一六年)、『地元を生きる――沖縄的共同性の社会学』(岸 政彦・上原健太郎・上間陽子と共著、ナカニシヤ出版、二〇二〇年)、『〈生活―文脈〉理解のすすめ――他者と生きる日常生活に向けて』(宮内洋・松宮朝・新藤慶と共著、北大路書房、二〇二四年)など。
沖縄を中心に暴走族・ヤンキーの若者を対象とした、参与観察調査をおこなっている。
齋藤 直子 Naoko Saito
一九七三年生まれ。大阪教育大学総合教育系特任准教授。社会学。専門は部落問題研究、家族社会学。主な著書に『結婚差別の社会学』(勁草書房、二〇一七年)、『入門家族社会学』(共著、新泉社、二〇一七年)、Educaciones y Racismos, Reflexiones y casos(共著、el Centro Universitario del Norte en Universidad de Guadalajara y Universidad Pedagógica Nacional, 2021)、『恋愛社会学――多様化する親密な関係に接近する』(共著、ナカニシヤ出版、二〇二四年)など、論文に「交差性をときほぐす――部落差別と女性差別の交差とその変容過程」(『ソシオロジ』第六六巻一号、社会学研究会、二〇二一年)など。
被差別部落出身者への結婚差別問題、部落女性をめぐる交差性、被差別部落へ/からの転入/転出、部落問題と「家」の関係性などについて研究している。
丸山 里美 Satomi Maruyama
一九七六年生まれ。京都大学大学院文学研究科准教授。社会学。専門はホームレス、貧困、ジェンダー研究、福祉社会学。主な著書に『女性ホームレスとして生きる――貧困と排除の社会学』(世界思想社、二〇一三年(増補新装版二〇二一年))、『質的社会調査の方法――他者の合理性の理解社会学』(岸 政彦・石岡丈昇と共著、有斐閣ストゥディア、二〇一六年)、『貧困問題の新地平――〈もやい〉の相談活動の軌跡』(編著、旬報社、二〇一八年)、Living on the Streets in Japan: Homeless Women Break their Silence(Trans Pacific Press, 2018)、『女性たちで子を産み育てるということ――精子提供による家族づくり』(牟田和恵・岡野八代と共著、白澤社、二〇二一年)などがある。「岩波講座 社会学」編集委員。
大学院在籍時から、女性ホームレスを対象に、ジェンダー化された貧困の様相をとらえる研究をおこなってきた。最近は、世帯のなかに隠れた貧困や、貧困の概念や把握の仕方について、ジェンダーの視点から研究している。
石岡 丈昇 Tomonori Ishioka
一九七七年生まれ。日本大学文理学部教授。社会学。専門は身体文化論、都市エスノグラフィー研究。主な著書に『ローカルボクサーと貧困世界――マニラのボクシングジムにみる身体文化』(世界思想社、二〇一二年(増補新装版 二〇二四年)、第一二回日本社会学会奨励賞・著書の部受賞)、Southern Hemisphere Ethnographies of Space, Place, and Time(共著、R. Rinehart eds., Peter Lang, 2018)、『タイミングの社会学――ディテールを書くエスノグラフィー』(青土社、二〇二三年)、『エスノグラフィ入門』(ちくま新書、二〇二四年)など。
フィリピン・マニラの貧困世界を事例に、ボクシングジムやスクオッター地帯を調査しながら、貧困を生きる人びとの生活実践を記述している。現在は、身体と時間の関係を「タイミングの社会学」という切り口から、理論的に考察する仕事をおこなっている。
上間 陽子 Yoko Uema
一九七二年生まれ。琉球大学教育学研究科教授。教育学。主な著書に、『裸足で逃げる――沖縄の夜の街の少女たち』(太田出版、二〇一七年)、『海をあげる』(筑摩書房、二〇二〇年、Yahoo!ニュース|本屋大賞2021ノンフィクション本大賞受賞、池田晶子記念わたくし、つまりNobody賞受賞、沖縄書店大賞受賞)、『沖縄子どもの貧困白書』(加藤彰彦・鎌田佐多子・金城隆一・小田切忠人と共編、かもがわ出版、二〇一七年)、『誰も置き去りにしない社会へ――貧困・格差の現場から』(平松知子ほかと共著、新日本出版社、二〇一八年)、『地元を生きる――沖縄的共同性の社会学』(岸政彦・打越正行・上原健太郎と共著、ナカニシヤ出版、二〇二〇年)、『復帰50年沖縄子ども白書2022』(川武啓介・北上田源・島村聡・二宮千賀子・山野良一・横江崇と共編、かもがわ出版、二〇二二年)など。
学校から逸脱する少年・少女や沖縄の貧困などについて学校内・学校外から調査してきた。現在は若年女性の特定妊婦の出産・子育ての応援シェルター「おにわ」の代表として支援もおこなっている。
朴 沙羅 Sara Park
一九八四年生まれ。ヘルシンキ大学文学部講師。社会学。専門はナショナリズム研究、社会調査方法論。主な著作に『外国人をつくりだす――戦後日本における「密航」と入国管理制度の運用』(ナカニシヤ出版、二〇一七年)、『家の歴史を書く』(筑摩書房、二〇一八年(ちくま文庫、二〇二二年))、『ヘルシンキ 生活の練習』(筑摩書房、二〇二一年(ちくま文庫、二〇二四年))、『ヘルシンキ 生活の練習は続く』(筑摩書房、二〇二四年)、『記憶を語る、歴史を書く――オーラルヒストリーと社会調査』(有斐閣、二〇二三年)ほか、論文に “Colonialism and Sisterhood: Japanese Female Activists and the ‘Comfort Women’ Issue”(Critical Sociology, 2019)など。
戦後日本における出入国管理政策の歴史を調査しつつ、歴史認識とオーラルヒストリー収集プロジェクトとの関係も調査している。
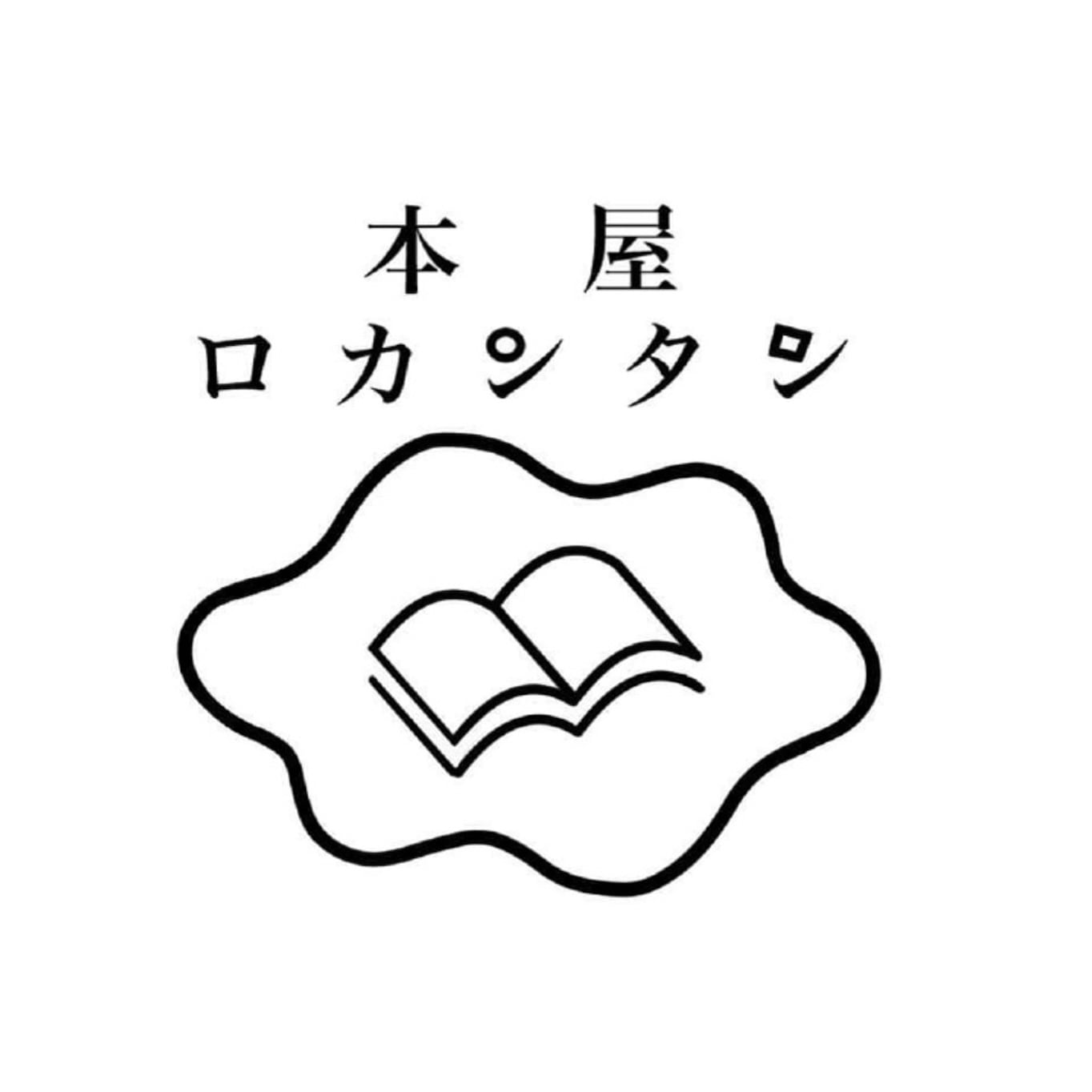



![23000 シン・論[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/82ea07ef161edff5abe260c379d78087.jpg?imformat=generic)
![感情化する社会[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/15d4f72af55aef451f9c1922b2de4f07.jpg?imformat=generic)
![シンコ・エスキーナス街の罠[OUTLET]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/384d0f51a1f69653449e2ff9fb76cf5f.jpg?imformat=generic)