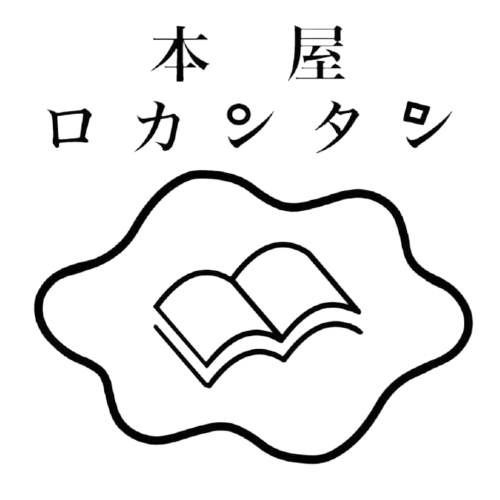-

名状しがたいもの ラヴクラフト傑作集17
¥1,034
その恐怖に、名前はまだない。 「人類の最古にして最強の感情は、未知への恐怖である」 ーーH.P.ラヴクラフト 未知への戦慄と憧憬を解き放つ、クトゥルフ神話の極地、完全漫画化。 【手塚治虫文化賞】マンガ大賞最終候補、【米国アイズナー賞】ノミネート、【仏国アングレーム国際漫画祭】公式セレクション選出、【仏国Prix Asie de la Critique ACBD】受賞、【仏国DARUMA】最優秀作画賞・最優秀デザイン賞受賞、【米国ハーベイ賞】ノミネートほか、数々の賞賛を呼ぶ「ラヴクラフト傑作集」シリーズ。 [出版社より] 著 者|田辺剛 原 作|H. P. ラヴクラフト 出版社|KADOKAWA[ビームコミックス] 定 価|940円+税 判 型|四六判[並製] 頁 数|282 ISBN|978-4047382763 発 行|2025年02月 Contents ・夢見人(ドリーマー)へ ・北極星(ポラリス) ・恐ろしい老人 ・霧の高みの不思議な家 ・ランドルフ・カーターの陳述 ・名状しがたいもの ・銀の鍵 ・断章 アザトース

-

ウルタールの猫 ラヴクラフト傑作集16
¥902
「猫を殺める事は許されぬ」ラヴクラフト傑作集シリーズ、新章突入。 スカイ河の彼方にあるウルタールの土地では、何人も猫を殺める事は許されぬと言う。 そのような法律が定められたのには、勿論理由がある――。 恐怖小説の王・H.P.ラヴクラフトが創造した異次元の世界・ドリームランド。その夢幻境を舞台とした「ウルタールの猫」「セレファイス」「蕃神」の3篇を、名状し難い「クトゥルフ漫画家」がコミカライズ。 [出版社より] 著 者|田辺剛 原 作|H. P. ラヴクラフト 出版社|KADOKAWA[ビームコミックス] 定 価|820円+税 判 型|四六判[並製] 頁 数|227 ISBN|978-4047379077 発 行|2024年05月 Contents ウルタールの猫 セレファイス 蕃神

-

クトゥルフの呼び声 ラヴクラフト傑作集10
¥1,034
『クトゥルフ神話』の原点、遂に漫画化。 星辰正しき刻、其れは永き夢から目覚める。 【手塚治虫文化賞】マンガ大賞最終候補、【米国アイズナー賞】ノミネート、【仏国アングレーム国際漫画祭】公式セレクション選出、【仏国Prix Asie de la Critique ACBD 2019】受賞、【仏国DARUMA2019】最優秀作画賞・最優秀デザイン賞受賞。 絶賛を呼ぶ【ラヴクラフト傑作集】シリーズは遂に、『クトゥルフ神話』の原点へ。名作『クトゥルフの呼び声』を、世界中から最高評価を受けるラヴクラフト描きが待望のコミカライズ! “Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn” “死せるクトゥルフ ルルイエの館にて 夢見るままに 待ちいたり” [出版社より] 著 者|田辺剛 原 作|H. P. ラヴクラフト 出版社|KADOKAWA[ビームコミックス] 定 価|830円+税 判 型|四六判[並製] 頁 数|289 ISBN|978-4047358539 発 行|2019年12月

-

異世界の色彩 ラヴクラフト傑作集2
¥748
ラヴクラフトの最高傑作、驚愕のコミカライズ。 “それ”は、隕石とともに、その村にやってきた……。そして、想像を絶する恐怖の幕が上がる。ホラー小説の巨星ラヴクラフトが「もっとも満足のいく作品」と自ら語った最高傑作に、『魔犬』で大きな話題を呼んだ気鋭の絵師が挑む。クトゥルフ神話の最深部、香気と戦慄が横溢する圧倒的な“煉獄”に、酔え、震えろ。 [出版社より] 著 者|田辺剛 出版社|KADOKAWA[ビームコミックス] 定 価|680円+税 判 型|四六判[並製] 頁 数|193 ISBN|978-4047308046 発 行|2015年09月

-

さみしくてごめん
¥1,760
ロングセラー『水中の哲学者たち』で颯爽とデビューした在野の若手哲学者・永井玲衣の最新エッセイ。世界の奥行きを確かめる。 「わたしはいつまでも驚いていたい。こわがっていたい。絶望して、希望を持ちたい。この世界から遊離せずに、それをしつづけたい。世界にはまだまだ奥行きがあるのだから」 今、もっとも注目される書き手、永井玲衣の最新刊。 [出版社より] 著 者|永井玲衣 出版社|大和書房 定 価|1,600円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|240 ISBN|9784479394532 発 行|2025年06月 Contents 1 やっぱりハリーポッタリ わたしが飲むとこ見ててよ タイツを履き忘れてすみませんでした ばかものよとかうざいんだけど シーサーには怖い顔をしていてほしい 箸、ごめんなさいね 夜に手紙を書くな 思ったより小さい あたらしい犬を提案する 2 念入りな散歩 1月1日の日記 思い出せないことが絶えず思い出される街、渋谷 見られずに見る 試みる 3 さみしくてごめん それ、宇宙では通用しないよ iPadを叩き割れ 後ろの風景を置き去りにすれば見える そうなのか これが そうなのか 身に覚えのない場合はご対応ください なんだかさみしい気がするときに読む本 考えるための場 4 この本はもう読めない 枕辺の足 きみの足を洗ってあげる 穴だらけの幸福 ただ存在するたけ運動 徹夜のための徹夜 ないがある 今は、知っている ただ、考えたい あとがき Author 永井 玲衣 Rei Nagai 1991年、東京都生まれ。哲学研究と並行して、学校・企業・寺社・美術館・自治体などで哲学対話を幅広く行っている。哲学エッセイの連載なども手がける。独立メディア「Choose Life Project」や、坂本龍一・Gotch主催のムーブメント「D2021」などでも活動。詩と植物園と念入りな散歩が好き。

-

本の美術誌——聖書からマルチメディアまで[OUTLET]
¥1,375
50%OFF
50%OFF
中世キリスト教絵画から現代美術、マルチメディアまで、美術の視点から「本とは何か?」をたどる書物論。古今東西の美術家の本にまつわる30作品余を収録。朝日「天声人語」でも紹介。 [出版社より] 著 者|中川素子 出版社|工作舎 定 価|2,500円+税 判 型|四六判/上製 頁 数|220 ISBN|978-4-87502-247-3 発 行|1995年01月 Contents 巻頭カラー:本の美術ギャラリー 第1章 一冊の本 パントクラトール像と聖書 本のかたち 呪物的な宝物 燃え落ちた本の幻 第2章 複数の本 聖母子像と聖書 「受胎告知」の舞台風景 所有熱 第3章 人間の時代 デューラー「四人の使徒」の時代精神 意識の図像学 きらめく思想の宇宙と印刷術 第4章 本の虫への皮肉 アルチンボルドの「法律家」と「司書」 魔術の帝国にて ルドルフ二世の肖像「ウェルトゥムヌス」 “目の人”が描く戯画 第5章 ヴァニタス メイプルソープとヴァニタス 空虚なる画布 日常的な死 西村陽平の燃えつきた本 第6章 読書する女 「源氏物語絵巻」と読書 浮世絵に描かれた母と子の読書 江戸の絵本文化 第7章 学問の道具 李朝の文房図:斬新な書架の絵 絵画への知的な思考 本が奏でる夢空間 ゆるやかな教育 第8章 アートワークとしての本 柏原えつとむの本とは何か? 加納光於と大岡信の本と箱 若林奮と吉増剛造の箱宇宙 河原温の数字本 第9章 記憶と創造力 ボルヘスの無限の本 星野美智子の溶解する本 第10章 大量消費生産物 デイヴィッド・マックの大量消費物アート 彫刻素材としての本 反個人的イメージの氾濫 現実のはざまで 第11章 滅亡のしるし 知の罪を暴くアンゼルム・キーファー 鉛の本の衝撃 滅びの時代 第12章 メディア マルチメディアへのターニング・ポイント ウェンヨン&ギャンブルのホログラム・イコン 山口勝弘の鏡の本 第13章 未来 ゲーリー・ヒルのビデオ・イメージ 河口龍夫の本と種子 本の“光年” 不死という未来 Author 中川 素子 Motoko Nakagawa 1942年、東京生まれ。東京芸術大学美術学部大学院修了。文教大学教育学部教授(造詣芸術論)。 著書に現代美術の視点から新しい絵本論を展開した『絵本はアート:ひらかれた絵本論をめざして』(教育出版センター)があるほか、新聞や雑誌の読書欄、文化欄などで絵本論、現代美術論を執筆している。

-

生きのびるための事務 全講義
¥1,650
SOLD OUT
10万部突破のべストセラー漫画『生きのびるための事務』、ついに原作テキスト版が書籍化。 あなたに足りないのは、才能や能力や運ではなく、《事務》でした。ピカソもやってた《夢》を《現実》にする具体的なヒントと方法を全11講で学べます。 書籍化にあたって新たに書き下ろされた「あとがき」や坂口さん本人が描き下ろした多数の挿絵に加え、巻末には坂口恭平さんと糸井重里さんによる5万文字にも及ぶ特別対談を収録。 糸井 坂口恭平という人のことは、僕ももともと、うすうす知っている状態で。 坂口 あ、ほんとですか。 糸井 でも「この人は天才だから、会わないほうがいいな」と思ってたの。 -- 中略 -- 坂口 僕自身やっぱり、糸井重里という人を参考にしているところが、たぶんあるんです。 糸井 ある……かもね(笑) [出版社より] 著 者|坂口恭平 出版社|マガジンハウス[マガジンハウス新書] 定 価|1,500円+税 判 型|新書判/並製 頁 数|368 ISBN|9784838775286 発 行|2025年06月 Contents 第1講 事務は「量」を整える 第2講 現実をノートに描く 第3講 未来の現実をノートに描く 第4講 事務の世界には失敗がありません 第5講 毎日楽しく続けられる事務的「やり方」を見つける 第6講 事務は「やり方」を考えて実践するためにある 第7講 事務とは「好きとは何か?」を考える装置でもある 第8講 事務を継続するための技術 第9講 事務とは自分の行動を言葉や数字に置き換えること 第10講 やりたいことを即決で実行するために事務がある 第11講 どうせ最後は上手くいく あとがき 特別講座 坂口恭平と糸井重里、はじめ Author 坂口 恭平 Kyohei Sakaguchi 1978年、熊本県生まれ。2001年、早稲田大学理工学部建築学科を卒業。作家、画家、音楽家、建築家など多彩な活動を行なう。2004年に路上生活者の家を収めた写真集『0円ハウス』(リトルモア)を刊行。著作は『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』(太田出版)、『独立国家のつくりかた』『苦しい時は電話して』(講談社)、『モバイルハウス 三万円で家をつくる』『TOKYO一坪遺産』(集英社)、『家族の哲学』(毎日新聞出版)、『継続するコツ』『幸福人フー』(祥伝社)、『TOKYO 0円ハウス 0円生活』(河出書房新社)、『躁鬱大学』(新潮社)、『発光』『よみぐすり』(東京書籍)、『自分の薬をつくる』『お金の学校』『中学生のためのテストの段取り講座』(晶文社)、『土になる』(文藝春秋)『まとまらない人』(リトルモア)など。 小説家として『幻年時代』(幻冬舎)、『徘徊タクシー』(新潮社)、『けものになること』(河出書房新社)を発表。ほか画集や音楽集、料理書など、多数の著作がある。 自ら躁鬱(そううつ)病であることを公言。2012年から死にたい人であれば誰でもかけることができる電話サービス「いのっちの電話」を自身の携帯電話(090-8106-4666)で続けている。2023年2月には熊本市現代美術館にて個展「坂口恭平日記」を開催。

-

朝のピアノ——或る美学者の『愛と生の日記』
¥2,420
SOLD OUT
「しばらく外国にいたとき、この本を1日いちど、3回読んだ。毎日読んでもいい本」 ーーハン・ガン[ノーベル賞作家] 余命を知ったとき、残りの日々をどう生きるか。 日常がシャッターを下ろすように中断されると知った時……残ったのは「愛」。 韓国の哲学アカデミー代表も務めた美学者キム・ジニョンは癌を宣告される。本書は天に召される3日前、意識混濁の状態に陥るまでの日々を記録した散文集だ。死に対する不安を率直に綴りながらも、世界のささやかな美を発見し、周囲の人たちを愛し、人間としての威厳を最後まで保ち続ける記録である。 [出版社より] 著 者|キム・ジニョン 訳 者|小笠原藤子 出版社|CEメディアハウス 定 価|2,200円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|272 ISBN| 9784484221274 発 行|2025年03月 Contents [抄録] 〈1〉 朝のピアノ。ベランダで遠くを眺めながら、ピアノの音に耳を傾ける。わたしはこれから何をもってしてピアノに応(こた)えられるのだろうか。この質問は妥当ではない。ピアノは愛である。ピアノに応えられるもの、それも愛あるのみだ。 〈3〉 いまわたしに必要なものは、病(やまい)に対する免疫力だ。免疫力は精神力。最高の精神力、それは愛である。 〈8〉 突として心がぽきぽき折れる。 秋日の枯れ木のように。 〈10〉 イウォンを会社に送り届けた帰り道、道端に車を停める。煙草をくゆらせながら朝の風景を眺める。駅前の駐車場はがらがらだ。毎日わたしの古びた車を停めていた場所。わたしを日常に送り出し、夜遅くまた戻ってくるのを待ってくれていた場所。その空っぽの場所で、心がまたもぽきっと折れる。 〈11〉 どうすればすべてを守れるだろうか。 自分を守れるだろうか。 〈12〉 昨晩、Cがメールを送ってきた。 「先生はいつもおっしゃっていましたよ。希望のない場所に希望はあるのだと」 〈15〉 今日はジュヨンがアトリエに行く日。外出をためらう彼女の背中を押す。わたしにせっつかれて、とうとう鏡の前に座ったジュヨンの姿を眺める。小さく丸い体つき。いつでも笑みを絶やさず、どんなときも大笑いして重い世の中を明るく一蹴する、笑いの塊のような体。 わたしは笑顔が素敵なこの女性から旅立つことができるのか。 Author キム・ジニョン 哲学者/美学者 高麗大学ドイツ語独文学科と同大学院を卒業し、ドイツのフライブルク大学大学院(博士課程)留学。フランクフルト学派の批判理論、特にアドルノとベンヤミンの哲学と美学、ロラン・バルトをはじめとするフランス後期構造主義を学ぶ。 小説、写真、音楽領域の美的現象を読み解きながら、資本主義の文化および神話的な捉えられ方を明らかにし、解体しようと試みた。市井の批判精神の不在が、今日の不当な権力を横行させる根本的な原因であると考え、新聞・雑誌にコラムを寄稿。韓国国内の大学で教鞭をとり、哲学アカデミーの代表も務めた。バルト『喪の日記』の韓国語翻訳者としても知られる。 Translator 小笠原 藤子 上智大学大学院ドイツ文学専攻「文学修士」。 現在、慶應義塾大学、國學院大學他でドイツ語講師を務める傍ら、 精力的に韓国語出版翻訳に携わる。 訳書にチョン・スンファン『自分にかけたい言葉 ~ありがとう~』(講談社)、 リュ・ハンビン『朝1 分、人生を変える小さな習慣』(文響社)、 イ・ギョンヘ『ある日、僕が死にました』(KADOKAWA)、 ケリー・チェ『富者の思考 お金が人を選んでいる』(CEメディアハウス)など多数。

-

パレスチナ、イスラエル、そして日本のわたしたちーー〈民族浄化〉の原因はどこにあるのか
¥2,750
パレスチナ/イスラエル問題を「自分のこと」として考えるために 国際法に明確に違反する虐殺であるにもかかわらず、「停戦」まで長すぎる月日を要し、さらにいまだ続くイスラエル軍によるガザ侵攻。 イスラエル建国を支持し、その筆舌に尽くし難い暴力を黙認し続けてきた欧米諸国の責任が問われる現在、かつて東アジア史におけるグレート・ゲームに名乗り出た帝国日本との関わりを起点に、国際的な植民地主義の負の遺産を検証する。そして、ユダヤ人国家・イスラエル建設の発想はどのように生まれ、知識人たちはどのように正当化/批判してきたのか、思想史の観点からも経緯を追う。 社会思想史研究者であり、パレスチナ/イスラエル問題にかかわってきた著者によるこれまでの主な対談のほか、また南アフリカ現代史の研究者・牧野久美子さんと植民地期および解放期における在日朝鮮人の生活史/ジェンダー史研究者・李杏理さんとの新規鼎談も収録。 [出版社より] 著 者|早尾貴紀 出版社|皓星社 定 価|2,500円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|344 ISBN|978-4-7744-0857-6 発 行|2025年04月 Contents まえがき 本書関連年表・地図 第Ⅰ部 東アジア史とパレスチナ/イスラエル問題の交差 はじめに/1帝国によるグレート・ゲーム/2パレスチナ一〇〇年戦争の起点/3セトラー・コロニアリズムの同時代性/4レイシズムによる同化と差別のダブルバインド/5民族浄化と「一九四八年体制」/6オスロ体制の欺瞞とハマースの台頭/7徐京植を読む(一)/8徐京植を読む(二)/9徐京植を読む(三)/おわりに 第Ⅱ部 欧米思想史から見たパレスチナ/イスラエル はじめに/1モーゼス・ヘスとテオドール・ヘルツル/2ダヴィド・ベングリオン/3コーエン、ローゼンツヴァイク、ショーレム、ブーバー/4ハンナ・アーレント/5エマニュエル・レヴィナス/6ジャック・デリダ(一)/7ジャック・デリダ(二)/8ハミッド・ダバシ(一)/9ハミッド・ダバシ(二)/10ボヤーリン兄弟とパレスチナ・フェミニスト・コレクティヴ/おわりに 第Ⅲ部 世界の矛盾が集約したパレスチナ ふたたび過ちを繰り返さないための日本・朝鮮・南アフリカ 牧野久美子×李杏理×早尾貴紀 第Ⅳ部 パレスチナ/イスラエル問題を語る 「大災厄」は過去ではない イラン・パペ『パレスチナの民族浄化』と米・エルサレム首都承認問題 臼杵陽×早尾貴紀 野獣の膨れた腹の中にサイードを解き放つ 批判的知性の再構築がどうできるのか 姜尚中×洪貴義×早尾貴紀 負の遺産として当時を知る 重信房子『戦士たちの記録 パレスチナに生きる』(幻冬社)から考える 小杉亮子×早尾貴紀 あとがき 幾重にも転倒した世界に抗して 索引 Author 早尾 貴紀 Takanori Hayao 一九七三年生まれ。東京経済大学教員。専門は社会思想史。二〇〇二〜〇四年、ヘブライ大学客員研究員として東エルサレムに在住し、西岸地区・ガザ地区・イスラエル国内でフィールドワークを行なう。 著書に『パレスチナ/イスラエル論』(有志舎、二〇二〇年)、『ユダヤとイスラエルのあいだ――民族/国民のアポリア』(青土社、二〇〇八年、新装版二〇二三年)、『イスラエルについて知っておきたい30のこと』(平凡社、二〇二五年)、訳書にジョー・サッコ著『ガザ 欄外の声を求めて』(Type Slowly、二〇二五年)、共訳書にサラ・ロイ『なぜガザなのか――パレスチナの分断、孤立化、反開発』(岡真理/小田切拓との共訳、青土社、二〇二四年)、イラン・パペ『パレスチナの民族浄化――イスラエル建国の暴力』(田浪亜央江との共訳、法政大学出版局、二〇一七年)、ハミッド・ダバシ『ポスト・オリエンタリズム――テロの時代における知と権力』(洪貴義ほかとの共訳、作品社、二〇一八年)など。

-

ロゴスと巻貝
¥1,980
小津夜景とは何者なのかが垣間見える40篇の読書エッセイ。 小津夜景さんはフランス・ニース在住の俳人です。綴る文章は言葉のつながりが瑞々しく、しなやかな連想に魅力があります。これまでの著作では谷川俊太郎さんなどから帯の推薦コメントをもらい、書籍が文庫化するなど注目が集まっています。本書は単なる読書エッセイではなく、これまでの小津さんの人生と、そこから結びつく本の記憶を手繰り寄せ、芳醇な言葉の群で紡ぎ合わせ、過去と現在、本と日常、本の読み方、人との交際などについて綴った一冊になっています。 [出版社より] 「細切れに、駆け足で、何度でも、這うように、本がなくても、わからなくても——。読書とはこんなにも自由なのですね、小津さん」 ——山本貴光[文筆家・ゲーム作家] 著 者|小津夜景 出版社|アノニマ・スタジオ 定 価|1,800円+税 判 型|四六判・上製 頁 数|256 ISBN|978-4-87758-855-7 発 行|2023年12月 Contents 読書というもの それは音楽から始まった 握りしめたてのひらには あなたまかせ選書術 風が吹けば、ひとたまりもない ラプソディ・イン・ユメハカレノヲ 速読の風景 図書館を始める 毒キノコをめぐる研究 事典の歩き方 『智恵子抄』の影と光 奇人たちの解放区 音響計測者(フォノメトログラフィスト)の午後 再読主義そして遅読派 名文暮らし 接続詞の効用 恋とつるばら 戦争と平和がもたらすもの 全集についてわたしが語れる二、三の事柄 アスタルテ書房の本棚 ブラジルから来た遺骨拾い 残り香としての女たち 文字の生態系 明るい未来が待っている 自伝的虚構という手法 ゆったりのための獣道 翻訳と意識 空気愛好家の生活と意見 わたしの日本語 ブルバキ派の衣装哲学 わたしは驢馬に乗って句集をうりにゆきたい そういえばの糸口 月が地上にいたころ 存在という名の軽い膜 プリンキピア日和 軽やかな人生 料理は発明である クラゲの廃墟 人間の終わる日 本当に長い時間 梨と桃の形をした日曜日のあとがき 引用書籍一覧 Author 小津 夜景 Yakei Odu 1973年北海道の生まれ。俳人。2000年よりフランス在住。2013年「出アバラヤ記」で攝津幸彦記念賞準賞、2017年『フラワーズ・カンフー』(2016年、ふらんす堂)で田中裕明賞、2018年『カモメの日の読書 漢詩と暮らす』(東京四季出版)、2020年『いつかたこぶねになる日 漢詩の手帖』(素粒社)、2022年『なしのたわむれ 古典と古楽をめぐる手紙』(素粒社)共著、『花と夜盗』(書肆侃侃房)、2023年11月『いつかたこぶねになる日』(新潮文庫)。

-

木ひっこぬいてたら、家もらった。
¥1,760
SOLD OUT
生きづらければ、つくるのだ。 尼崎「ガサキベース」の店主・足立さんは、300 坪の土地と2軒の家をほぼゼロ円でもらった。それは足立さんがどん底を経験しながらも、つくり続けたから生まれたお話。 「経済合理性」は、一つじゃない。 生きづらさを抱え「つくれる本屋」を開いた著者との対話から、生き方を探る一冊。 兵庫県尼崎市のガサキベース。工場をリノベーションしたその場所は、コーヒーも飲めるし、DIY を教えてくれる不思議な場所。店主の足立繁幸さんはガサキベースの縁で島根の家を1 軒タダで譲り受け、その家の木を引っこ抜いていたら、うしろのもう1 軒ももらうことに。 どうしてそんなできごとが起こったのか? 足立さんの幼少期からの生きづらさ、家族・DIY・仕事・お金……現代人に共通する悩みとともに紐解いていきます。つくれば人とモノの縁がつながる。 [出版社より] 著 者|足立繁幸・平田堤 出版社|DIY BOOKS 定 価|1,600円+税 判 型|四六版/並製 頁 数|144 ISBN|978-4-9914014-0-4 発 行|2025年03月 Contents はじめに 『わらしべ長者』みたいなできごとはなぜ起こった? なぜ空き家が増えるのか 経済合理性って何だ? 疲弊の果てのDIY BOOKS 人生はDIYでしかない ガサキベース=「オムツの履き替え場所」 焼け野原のあとの、島根で モテるために始まったDIY道 DIYと愛と「巣」 カクカクしていたあのころ ガサキベースの誕生と変化 買うことで自分を高める機会と縁が切れる メイカームーブメントと、ブリコラージュ、そして編集 作為的でない美しさと「普通」 いろんなかたちがあっていい 新しい家族との出会い 里親という家族のかたちと「波紋」 ガサキベースをちゃんと死なせたかった 「アマ」ではなく「ガサキ」なのはなぜか 手を動かすと昔と繋がる 子どもにはDIYをさせよ(まず大人から) 二項対立と秩序 生命はエントロピー増大に抗い「系」をつくる 人は自分の「系」をつくる存在 木を引っこ抜いてみた 愛のあった家と、ルーツへ 親心と戦争と百姓 根っこを逆に帰る それぞれの論理へ つくるから縁ができる 論理的思考は一つではない 根を張って生きる 終わりにかえて。文とつくること あとがき Author 足立 繁幸 Shigeyuki Adachi 島根県生まれ。尼崎でガサキベースを開き、DIYをデリバリーで行い、つくり方を教える。2025年以降はもらった島根の2 軒の古民家を改造して新しい拠点をつくる予定。 平田 提 Dai Hirata 秋田県生まれ。Web 編集者・ライター。尼崎に「つくれる本屋」DIY BOOKS を2023 年10 月に開店。その際に足立さんと出会う。ZINEの作り方のスクールなどを開催。

-

あなたの肌を描く とし総子詩集
¥2,200
花の色の爪が はがれた 花弁の中に 埋もれてしまう 鮮やかすぎる 赤を残して ますます 肌は青くなる [「彩」より] 「世界のまっ心をつかみ ひかりをまぜたことばたち。とし総子の詩にはこの世界のほんとう、そのかけらだけがとどめられている」 ——茉莉亜まり[川柳人] 「海も 山も 空も 全ての宇宙を内包している とし総子さん」 ——福永祥子[詩人] 著 者|とし総子 出版社|澪標 定 価|2,000円+税 判 型|13mm*21.5mm/上製 頁 数|58 ISBN|978-4860785963 発 行|2024年11月 Author とし 総子 Souko Toshi 1987年生まれ。詩人。2024年11月澪標社より第一詩集『あなたの肌を描く』を上梓。 https://note.com/akitukiyuka/ https://www.instagram.com/akituki0530/
-

インドラネット
¥946
SOLD OUT
おまえのために死んでもいい。危険な目に逢い続ける男が最後に見たものは。 平凡な顔、運動神経は鈍く、勉強も得意ではない――何の取り柄もないことに強いコンプレックスを抱いて生きてきた八目晃は、非正規雇用で給与も安く、ゲームしか夢中になれない無為な生活を送っていた。唯一の誇りは、高校の同級生で、カリスマ性を持つ野々宮空知と、美貌の姉妹と親しく付き合ったこと。だがその空知が、カンボジアで消息を絶ったという。空知の行方を追い、東南アジアの混沌の中に飛び込んだ晃。そこで待っていたのは、美貌の三きょうだいの凄絶な過去だった……。 [出版社より] 著 者|桐野夏生 出版社|KADOKAWA[角川文庫] 定 価|860円+税 判 型|文庫判/並製 頁 数|432 ISBN|9784041143209 発 行|2024年07月 Contents 第一章 野々宮父の死 第二章 シェムリアップの夜の闇 第三章 ニェットさんの青唐辛子粥 第四章 さらば青春 第五章 冷たい石の下には 第六章 インドラの網 解説 高野秀行 Author 桐野 夏生 Natsuo Kirino 1951年生まれ。93年『顔に降りかかる雨』で江戸川乱歩賞を受賞。99年『柔らかな頬』で直木賞、2003年『グロテスク』で泉鏡花文学賞、04年『残虐記』で柴田錬三郎賞、05年『魂萌え!』で婦人公論文芸賞、08年『東京島』で谷崎潤一郎賞、09年『女神記』で紫式部文学賞、10年、11年に『ナニカアル』で島清恋愛文学賞と読売文学賞の二賞を受賞。1998年に日本推理作家協会賞を受賞した『OUT』は04年エドガー賞候補となる。15年紫綬褒章を受章。
-

純喫茶図解
¥1,650
『銭湯図解』で話題の画家・塩谷歩波が建築の図法で描く、唯一無二の空間。都内近郊の“純喫茶図解”18軒をオールカラーで収録!眺めて、読んで楽しいイラストエッセイ集。 アンティークの調度品にシェードランプの薄明り、個性あふれる床タイル、妖しく微笑むトーテムポール……。都心には、建築やインテリア、メニューの隅々にまで店主のこだわりが詰まった魅力あふれる純喫茶がひしめき合っています。 そんな純喫茶の魅力を、画家・塩谷歩波さんが建築の図法で描き、実際に足を運んで食べたメニューや店主へのインタビューなど、イラストと写真、文章でお届けします。著者の緻密で温かい絵に思いを巡らせながら、純喫茶に足を運んでみませんか? [出版社より] 著 者|塩谷歩波 出版社|幻冬舎 定 価|1,500円+税 判 型|新書判 頁 数|128 ISBN|9784344044258 発 行|2025年04月 Contents 第1章 ノスタルジックな純喫茶 西荻窪 それいゆ/蔵前 らい/渋谷 茶亭羽當/神保町 ラドリオ/津田沼 珈琲屋からす/高円寺 珈琲亭七つ森 第2章 豪華絢爛な純喫茶 上野 Coffee Shopギャラン/銀座 トリコロール 本店/上野 喫茶 古城 第3章 音を楽しむ純喫茶 渋谷 名曲喫茶ライオン/阿佐ヶ谷 ヴィオロン/吉祥寺 バロック/新宿 らんぶる 第4章 ひとクセ光る純喫茶 神保町 さぼうる/阿佐ヶ谷 gion/吉祥寺 くぐつ草/御茶ノ水 穂高/都立家政 Coffee&Lunch つるや Author 塩谷歩波 Honami Enya 1990年東京都生まれ。早稲田大学大学院(建築学専攻)修了。設計事務所、高円寺の銭湯・小杉湯の番頭を経て、2021年より画家として独立。設計事務所休職中に通い始めた銭湯に救われ、銭湯の建物内部を俯瞰で描く「銭湯図解」をSNS上で発表し、話題に。2019年に『情熱大陸』(TBS)に出演、2022年には自身の半生をモデルにしたドラマ『湯あがりスケッチ』(ひかりTV)が配信されるなど注目を集める。現在は、飲食店、ギャラリー、茶室など、様々な建物の図解を制作するほか、入浴施設などのデザイン監修も手がける。著書に『銭湯図解』(中央公論新社)、『湯あがりみたいに、ホッとして』(双葉社)、『塩谷歩波作品集』(玄光社)がある。

-

働きたいのに働けない私たち
¥2,090
女性は投資の対象外? 女性は好きでパートをしている!? 韓国の子持ち高学歴女性は労働市場から退場していく。社会は有能な人材を失い続け、母親たちは代わりにわが子の教育で競争に参戦する。男性本位の職場、個人化されたケアを解体するために何が必要か。スウェーデン、アメリカとの比較から考える。解説=中野円佳。 [出版社より] 「女が仕事も夢も子どもや家庭も持ちたいと願うことって、図太いからなんかじゃないよね?! とことん論理的な分析の向こうに涙が滲み出る。」 ――小林エリカ[作家・アーティスト] 「ガラスの天井、L字カーブ、ケアの個人化。労働と出産をめぐる性差別が蔓延するこの国で、〈男たち〉はずっと透明のままでいいのか」 ――清田隆之[文筆家] 著 者|チェ・ソンウン 訳 者|小山内園子 出版社|世界思想社 定 価|1,800円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|160 ISBN|9784790718000 発 行|2025年05月 Contents プロローグ 図太い女の社会 1 「平等な競争」という幻想 2 女性に「学歴プレミアム」はあるか 3 母になるのは拒否します 4 より多くの女性が働けるように エピローグ 機会の平等を論じる 補論 日本の「働けない女たち」へ(チェ・ソンウン) 解説 手を取り合える日韓の女性たち(中野円佳) 訳者あとがき ブックガイド/参考文献 Author チェ・ソンウン 行政学博士。延世大学行政学科で修士号、博士号を取得後、国会立法調査処児童保育立法調査官補を経て、淑明女子大、延世大、明知大などで教鞭をとる。現在は大田世宗研究院世宗研究室の責任研究委員として、世宗特別自治市の女性、子ども、少子化政策の課題を研究。キャリア女性の雇用対応政策、子どもの遊ぶ権利を保障した公共の遊び場の活性化、ワーキングママ支援センターの運営などについて提言を行ってきた。合計特殊出生率0.75と深刻な少子化に悩む韓国にあって、世宗特別自治市は1.03を記録(韓国統計庁、2024年の合計特殊出生率〔暫定値〕)。特別市・広域市の中で唯一1を超える自治体であり、その実践が注目を集めている。 Translator 小山内 園子 Sonoko Osanai 韓日翻訳家、社会福祉士。NHK報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書にク・ビョンモ『破果』『破砕』(岩波書店)、チョ・ナムジュ『耳をすませば』(筑摩書房)、『私たちが記したもの』(すんみとの共訳、筑摩書房)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)、イ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ』『失われた賃金を求めて』(すんみとの共訳、タバブックス)など、著書に『〈弱さ〉から読み解く韓国現代文学』(NHK 出版)がある。

-

湯気を食べる
¥1,760
最注目の著者による「自炊」エッセイ集。 幅広い分野で活躍する注目の作家・くどうれいんによる「食べること」にまつわるエッセイ集。「オレンジページ」の人気連載と河北新報での東北エッセイ連載に書き下ろしを多数加えた、心にひびく48編。 [出版社より] 著 者|くどうれいん 出版社|オレンジページ 定 価|1,600円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|212 ISBN|9784865937039 初 版|2025年03月 Contents 【第一章】湯気を食べる 湯気を食べる ディル? それはまかない 南国の王様 愛妻サンド アイスよわたしを追いかけて 福岡のうどん 鍋つゆ・ポテトチップス 棚に檸檬 白いさすまた すいかのサラダ くわず女房 ぶんぶん 庭サラダバー 手作りマヨネーズ おどろきの南蛮漬け かに玉ごはん いい海苔 すだち 寿司はファストフード シェーキーズってすばらしい ピザは円グラフ 醤油はいずれなくなる 【第二章】風を飲む 萩の月 ほや 菊のおひたしと天ぷら せり鍋 わかめ うーめん 笹かまぼこ お米は貰うもの きりたんぽ たらきく 風を飲む 【第三章】自炊は調律 自炊は調律 たまご丼 パン蒸し 好きな食べもの 献立は大行列 つくりおけぬ ねぎとろ ナッツと言いたかった 柿ピーの短刀 自炊の緑白黒赤 くる スナップえんどう 渡したいわたし お花見弁当 おわりに 初出リスト Author くどう れいん Rein Kudo 作家。1994年生まれ。岩手県盛岡市在住。著書にエッセイ集『わたしを空腹にしないほうがいい』『うたうおばけ』『虎のたましい人魚の涙』『桃を煮るひと』『コーヒーにミルクを入れるような愛』、歌集『水中で口笛』、小説『氷柱の声』、創作童話『プンスカジャム』、絵本『あんまりすてきだったから』などがある。
-

コーヒーについてぼくと詩が語ること[文庫版]
¥1,650
コーヒーを語ることは、世界を語ること。 中世イスラームの地で生まれたコーヒー飲用文化の起源から、21世紀の新潮流までを詩、映画、宗教、戦争を通して語ったコーヒー本が、このたび文庫本として再編されました。巻末には「コーヒーの基礎知識」「注釈」「参考文献一覧」のほか、今回の文庫化にあたり、文筆家・喫茶写真家の川⼝葉子さんの解説文も添えられています。 「街角のカフェで何気なく一杯を口にするとき、たちのぼる湯気とともに、コーヒーが背負う光と影、コーヒーに思いを託した詩人たちの詩が浮かび上がってくる」——解説文より。 [出版社より] 著 者|小山伸二 出版社|書肆梓 定 価|1,500円+税 判 型|文庫判・並製 頁 数|312 ISBN|978-4-910260-07-5 発 行|2025年05月 Contents コーヒーを愛する未知のあなたへ 第1章 旅するコーヒー 1 はじめに、あるいは道草から始まる物語 2 ニコのコーヒーをめぐる冒険 3 眠りたくない夜のために 4 「カフェ的」なるものの誕生 イスタンブールの「コーヒーの家」・パリの初期カフェ 5 日本でのコーヒー文化の進化 西欧化と日本のコーヒー受容・日本独自のハンド・ドリップ文化 6 手のひらの時代のコーヒー 第2章 ソクラテスのカフェ 1 哲学カフェ 2 詩とコーヒー 3 スーフィーのコーヒー 4 移動と変容 5 ふたたび、戦争 6 戦争と映画 7 最後のコーヒー 第3章 コーヒー文化論一九六八/二○一八 1 明治維新から 2 学生たちの「反乱」 3 食の総合出版社のこと 4 コーヒーをめぐる書籍 5 コーヒーの雑誌『blend』 6 異彩を放った著者 7 二十一世紀のコーヒー文化 8 新しい雑誌の登場 第4章 「詩とコーヒー」試論 1 禁酒法の国のコーヒー アラビア・フランス・イタリア・ウィーン・イギリス・アメリカ 2 ユーカーズにおける「コーヒーの詩」 3 朝に一杯のコーヒーを 4 コーヒーは詩を響かせるか コーヒー基礎知識・注釈・参考文献一覧・本書に登場した映画 解説 川口葉子 Author 小山 伸二 Shinji Oyama 鹿児島県出身。書肆梓、Cloud Nine Coffee代表。東京都立大学卒業後、出版社勤務を経て、辻調理師専門学校に転職。2024年退職後も食文化概論の授業を非常勤講師として担当。日本コーヒー文化学会・常任理事。詩人としても活動。詩集に『きみの砦から世界は』(思潮社)、『ぼくたちはどうして哲学するのだろうか。』『雲の時代』『さかまく髪のライオンになって』(書肆梓)。共著に『専門家が語る! コーヒーとっておきの話』(旭屋出版)。
-

月の本棚 under the new moon
¥2,420
先が見通せず、前に一歩も進めないとき、しばし立ち止まって本を開き、ほかの人生を生きてみました——。月を眺めるように読んだ58作品のブックレビュー。パン店「Le Petitmec」のオウンドメディア連載に加筆。 先の見えない新月の夜にも、いつも美しい言葉がそばにあった。 月はやがて満ちていく。新しい時代への希望を綴る「読書日記」。小説から哲学、エッセイ、人類学の本まで、月を眺めるように読んで、果てしない気持ちになった58作品を紹介。 「先が見通せず、前に一歩も進めないとき、しばし立ち止まって本を開き、ほかの人生を生きてみました。そこでたくさん旅をしました。過去へも旅をして、小学校の図書室で本を読む自分にも出会いました 」——「あとがき」より。 [出版社より] 著 者|清水美穂子 出版社|書肆梓 定 価|2,200円+税 判 型|B6変型判・上製 頁 数|288 ISBN|978-4-910260-03-7 発 行|2023年04月 Contents 1 魅力的な図書室/見えないものに導かれる感覚/月を眺めるように読む/ルールとゲーム。お伽噺の娯楽/パンデミックの時代に 2 過去に属している場所/パティ・スミスの本棚/遊歩者の小説 3 ジュンパ・ラヒリの第三の言語/瞬間の連なりのアート/茶道の稽古/一杯の白湯のような本 4 それはもう遠い国ではなかった 5 本棚の写真を撮った日/小説と日記のあわいに遊ぶ 6 無声映画とキャッツテーブル/マイ・ブックショップとブラッドベリ/アメリカの路上で 7 台風に閉じ込められた日に/名もなき人たちのささやかな生と死/見つける/いとおしきもの 本書に登場する作品 『マザリング・サンデー』グレアム・スウィフト、『雲』エリック・マコーマック、『オーバーストーリー』リチャード・パワーズ、『アップルと月の光とテイラーの選択』中濵ひびき、『月の立つ林で』青山美智子、『アディ・ラルーの誰も知らない人生』V・E・シュワブ、『断絶』リン・マー、『そのひと皿にめぐりあうとき』福澤徹三、『土星の環 イギリス行脚』『アウステルリッツ』W・G・ゼーバルト、『Mトレイン』パティ・スミス、『優しい鬼』レアード・ハント、『インディアナ、インディアナ』レアード・ハント、『ネバーホーム』レアード・ハント、『オープン・シティ』テジュ・コール、『わたしのいるところ』ジュンパ・ラヒリ、『べつの言葉で』ジュンパ・ラヒリ、『いちばんここに似合う人』ミランダ・ジュライ、『あなたを選んでくれるもの』ミランダ・ジュライ、『おるもすと』吉田篤弘、『日日是好日』森下典子、『一日一菓』木村宗慎、『まなざしの記憶 だれかの傍らで』植田正治・鷲田清一、『ガザに地下鉄が走る日』岡真理、『西欧の東』ミロスラフ・ペンコフ、『テヘランでロリータを読む』アーザル・ナフィーシー、『消失の惑星(ほし)』ジュリア・フィリップス、『夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く』奈倉有里、『さよならまでの読書会』ウィル・シュワルビ、『夜の舞』イサアク・エサウ・カリージョ・カン、『解毒草』アナ・パトリシア・マルティネス・フチン、『雑貨の終わり』三品輝起、『すべての雑貨』三品輝起、『冬の日誌』ポール・オースター、『トゥルー・ストーリーズ』ポール・オースター、『ケンブリッジ・サーカス』柴田元幸、『無声映画のシーン』フリオ・リャマサーレス、『名もなき人たちのテーブル』マイケル・オンダーチェ、『華氏451度』レイ・ブラッドベリ、『たんぽぽのお酒』レイ・ブラッドベリ、『アメリカの〈周縁〉をあるく 旅する人類学』中村寛・松尾眞、『語るに足る、ささやかな人生』駒沢敏器、『ボイジャーに伝えて』駒沢敏器、『彼女たちの場合は』江國香織、『庭とエスキース』奥山淳志、『ある一生』ローベルト・ゼーターラー、『ザリガニの鳴くところ』ディーリア・オーエンズ、『使者と果実』梶村啓二、『奇跡も語る者がいなければ』ジョン・マグレガー、『こびととゆうびんやさん」カレル・チャペック、『きみがぼくを見つける』サラ・ボーム、『おやすみ、リリー』スティーヴン・ローリー、『友だち』シーグリッド・ヌーネス、『ある小さなスズメの記録』クレア・キップス。 Author 清水 美穂子 Mihoko Shimizu 文筆家。ブレッドジャーナリスト。1965年東京生まれ。All About、Yahoo! ニュース、食の専門誌など各種メディアでパンとそのつくり手を取材・執筆。趣味は茶道と毎朝の公園でのごみ拾い。著書に『月の本棚』(書肆梓)、『BAKERS おいしいパンの向こう側』(実業之日本社)、『日々のパン手帖 パンを愉しむ something good』(メディアファクトリー)他。
-

殺戮の宗教史[OUTLET]
¥1,210
50%OFF
50%OFF
SOLD OUT
NYの9.11同時多発テロ、シャルリー・エブド社襲撃事件、パリの同時多発テロ。日本に目を向けても、『悪魔の詩』訳者殺害の謎、オウム真理教による地下鉄サリン事件など、宗教にもとづくテロが国内外で頻発している。なぜ神の名の下における「殺戮」は止まないのか?また、イスラム教は危険な宗教なのか? 十字軍や「聖戦」、魔女狩り、異端諮問から、イスラム国(IS)やアルカイダなどイスラム過激派による近現代のテロまで世界の宗教にみられる「殺戮の歴史」をたどり、その背景や宗教の教義、神の役割を徹底分析。「宗教的テロの時代」の本質を理解するための必読書。 [出版社より] 著 者|島田裕巳 出版社|東京堂出版 定 価|2,200円+税 判 型|四六判/上製 頁 数|288 ISBN|9784490209341 発 行|2016年03月 Contents はじめに 第1章 宗教的テロリズムの二一世紀 テロの時代の幕開け/増え続ける犠牲者の数/危険視されるイスラム教/九・一一の実行犯はどんな人物か/ 実行犯グループとアルカイダの関係/『九・一一委員会報告書』の真偽/九・一一はアルカイダが仕組んだものではない?/ 「アルカイダ」の意味すること/組織化されたテロ集団といえるのか/「組織」なのか「ネットワーク」か/ インターネットの活用による新たな問題、ほか 第2章 イスラム教は危険な宗教なのか 頻発する宗教を背景としたテロ/シャルリ―・エブド襲撃事件の衝撃/イデオロギーの対立から「文明同士の衝突」の時代へ/ イスラム文明vs西欧を中心とした他の文明という構図/「剣かコーランか」という偏ったイメージ/ 「世界の三大宗教」発生と拡大のプロセス/政治的指導者としてのムハンマドの役割/イスラム教拡大には武力も用いられた/ それぞれの宗教の「違い」を知ること、ほか 第3章 知られていないイスラム教の根本原理 イスラム教発祥をたどる/偶像崇拝禁止の根拠/ムハンマドに求められた「調停者」という役割/イスラム教誕生の社会的必然性/ 多神教徒を殺せと神は命じた/同時に与えられた「赦し」/歴史的・社会的文脈の中で神のことばを理解する/ イスラム教の本質的性格/戒律を実行するかどうかは個人に任せられる/イスラム教全体が危険であるとみなされがちな理由、ほか 第4章 原理主義の背後にある神の絶対性 「原理主義」ということばの広がり/はじまりはキリスト教から/アメリカ社会での福音主義の台頭/ イスラム教が政治の表舞台に/宗教間の対立のはじまり/イスラム教に強く見られる「原理主義」の傾向/ 「シャリーア」とは何か/一神教は不寛容か/多神教と一神教の本質的な違いとは/神社はいつから存在したのか/ 一神教において絶対的存在である神/「再誕」という経験、ほか 第5章 神による殺戮と終末論の呪縛 神が直接手を下すとき/ユダヤ教の神の存在は絶大/「創世記」に描かれた神の非道さ/神と人類の複雑な関係/ キリスト教の「十戒」と仏教の「五戒」の共通点と違い/人類全体を滅ぼしうる一神教の神/ 「絶対神」の観念を生んだユダヤ人の苦難の歴史/善悪二元論はイラン宗教の影響/ 最後の審判とキリストの再臨――キリスト教を世界宗教とした考え方、ほか 第6章 異教や異端との戦い――十字軍について キリスト教を世界宗教にした「伝道活動」/アメリカで盛んだった「リバイバル」(信仰復興)/聖人崇拝はこうして始まった/ 三宗教にとっての聖地、エルサレム/十字軍のはじまり/聖地を目指す人々のさまざまな思惑/殉教が尊い行為とされる/ 伝道において「殺戮」はやむを得ぬもの/ローマ教皇の権威確立と「正統」「異端」という判断/異教徒や異端に対する戦い、ほか 第7章 善悪二元論という根源 日本で見られた「異端」とは/「正統」が明確に確立されなかった日本の仏教界/ カトリックで行われた異端追放の動き――「異端審問」「魔女狩り」/カタリ派が異端とされた最大の理由――「善と悪の二元論」/ 異端の代名詞「マニ教」とは/聖職者に課せられた厳しい生活の戒律/一神教の抱える根本的な矛盾と悪の存在/ 「悪」が存在する限り殺戮の歴史は終わらない、ほか 第8章 聖戦という考え方 「殺せ」か「殺すな」なのか/恐怖の神から、慈愛深き神へ/異なる信仰をもつ人間と共存するために/ 互いを受け入れ難いユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教/「ジハード」の解釈をめぐって/カリフの役割とは/ 「ジハード」は「聖戦」ではない/後世に影響を与えたタイミーヤの思想/ムハンマドの時代の信仰への回帰/ 次々と出現した過激なイスラム集団、ほか 第9章 殺戮の罪は許されるのか 「一神教」または「多神教」という観点から/神道における武装した神々/『古事記』に描かれた天照大神の怒り/ 「武神」八幡神の信仰/神社に託された戦勝への願い/密教と陰陽道による呪詛の広がり/日本における「殺戮の宗教史」/ 悪人正機説の危険性/殺戮を行った者は救済されないのか/許すということの難しさ/ 宗教は殺戮を肯定するものか、否定するのか、ほか おわりに Author 島田 裕巳 Hiromi Shimada 1953年東京生まれ。東京大学文学部宗教学宗教史学専修課程卒業、東京大学大学院人文科学研究課博士課程修了。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、NPO法人葬送の自由をすすめる会会長を歴任。現在は作家、宗教学者、東京女子大学非常勤講師。
-

パウル・クレー作品集——詩と絵画の庭
¥3,740
生前から、日本人に愛され続けてきた画家、クレー。その芸術世界を特徴づける6つの視点に沿って、選りすぐりの作品約140点を紹介。A4判の大画面でクレーの世界を満喫できる作品集。 [出版社より] 著 者|黒田和士 出版社|東京美術 定 価|3,400円+税 判 型|A4判/並製 頁 数|192 ISBN|9784808713126 発 行|2025年01月 Author 黒田和士 Kazushi kuroda 慶應義塾大学文学研究科修了。専門はドイツ近代美術。東京藝術大学大学美術館学芸研究員、Bunkamura ザ・ミュージアム学芸員を経て、現在、愛知県美術館学芸員。「エリック・サティとその時代」(2015年)、「ミニマル/コンセプチュアル:ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70年代美術」(2021年)などの展覧会に関わったほか、「パウル・クレー展 創造をめぐる星座」(2025年)を企画。また、愛知県美術館所蔵の西洋美術作品の来歴調査を進め、特集展示「『名品』はどこからきたのか?」(2023年)を企画。論文に「パウル・クレー《回心した女の堕落》 イメージと言葉の弁証法的な関係をめぐって」など。

-

お砂糖ひとさじで
¥1,760
小さなことへの喜びや楽しみ。それこそが、自分。 メアリー・ポピンズの映画に出てくる歌「お砂糖ひとさじで」。そこでは、小さな工夫で日常がどれだけ楽しくなるかが歌われる。ひとさじのお砂糖で、苦い薬も飲めるようになる――。 そんなふうに気持ちを軽くしてくれる、魔法の呪文のようなエッセイ。お気に入りのアイテムやちょっとした発見、ずっと変わらず好きなこと、新たに好きになったもの、時には疑問や怒りも。あらゆるもので日々は織り成されている。 『PHPスペシャル』の好評連載を書籍化。 [出版社より] 著 者|松田青子 出版社|PHP 定 価|1,600円+税 判 型|四六判・並製 頁 数|280 ISBN|978-4-569-85712-1 発 行|2024年06月 Contents ●服を買わなくても平気だった ●お茶の時間を取り戻す ●私、参加してる! ●秘密の森に分け入って ●心躍るジャンクフード ●ファンシーに夢中 ●読書は心にいい ●運命のペンとノート ●副反応のシルバニア ●敏感肌の冒険 ●必要なものですんで! ●リップモンスターを探して ●それもまたよし ●タクシーへの怒り ●オックスフォードの晩餐 ●セボンスターとパンとバラ Author 松田 青子 Aoko Matsuda 1979年、兵庫県生まれ。同志社大学文学部英文学科卒業。2013年、デビュー作『スタッキング可能』が三島由紀夫賞及び野間文芸新人賞候補に、14年にTwitter文学賞第1位となり、19年には『ワイルドフラワーの見えない一年』収録の「女が死ぬ」(英訳:ポリー・バートン)がアメリカのシャーリィ・ジャクスン賞短編部門の候補となった。

-

幸あれ、知らんけど
¥1,870
神戸の街で40歳から子育てを始めた作者の、平凡だけどかけがえのない日常。集団登校を見守り、50歳を前にラーメン漬け生活を捨て肉体改造に励む。カレーうどんの汁を捨てる妻と大喧嘩、公園に恐竜がやって来る? 全人類の心に沁みる珠玉のエッセイ集。朝日新聞の人気連載を書籍化。 [出版社より] 著 者|平民金子 出版社|朝日新聞出版 定 価|1,700円+税 判 型|四六判・並製 頁 数|240 ISBN|9784022520418 発 行|2025年03月 Contents 第一章 その向こう あほんだら、なにしてくれとんねん 日々を肯定する言葉、探しに 10年前、いまも残る細部の記憶 ほか 第二章 普段着で町へ 離任式 一両編成の電車 減量を決意する ほか 第三章 今いる世界に ドラえもんの王国へ ちょっとトイレに(石垣島日記1日目) ハッピーマート(石垣島日記2日目) ほか Author 平民金子 HeiminKaneko 1975年大阪生まれ。文筆家・写真家。中国、メキシコ、北海道、沖縄、東京などを転々とする。

-

バンクシー 壁に隠れた男の正体[OUTLET]
¥1,100
50%OFF
50%OFF
バンクシーの半生を描く待望の評伝。 緻密な取材が人物像を浮き彫りにする世界でも貴重なルポルタージュ。 ー バンクシーをイギリスの新聞記者が追った評伝。 世の中の常識を軽やかにひっくり返す覆面芸術家・バンクシー。 故郷のこと、お金のこと、協力者のことなど、ひとりの少年がどのように匿名のまま世界的なアーティストになっていったのか、その実像に迫る。緻密な取材を元に書かれた、世界でも貴重なルポルタージュの日本語版。 [出版社より] 著 者|ウィル・エルスワース=ジョーンズ 翻 訳| 「バンクシー 壁に隠れた男の正体」翻訳チーム 出版社|PARCO出版 定 価|2,000円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|484 ISBN|978-4-86506-334-9 初 版|2020年6月
-

美女と拳銃[OUTLET]
¥1,100
50%OFF
50%OFF
カトリーヌ・ドヌーヴ主演 ジャン=リュック・ゴダール監督。カンヌを舞台に、フランス映画界の超セレブ総登場で撮影敢行——。 リュック・ベッソンに映画とは何たるかを教えられ、ジェラール・ドパルデューにのせられ、あおられ、スマホ以外は何も持っていない兄弟が、映画をつくり始めた。彼らは若きサギ師なのか? 天才なのか? カンヌを舞台にした、虚実入り交じる撮影現場を実況中継。奇想天外、妄想力大爆発のフランス文学の新しい波。 ー 2人の兄弟、アリョーシャとディミトリには、1つの望みがあった。映画を作ることだ。彼らは映画学校の学生で、一文なしで、ちょっとしたワルだった。どん底で生まれて、そこに戻る気はなかった。2人はスマホと大胆さだけを武器に、カンヌ映画祭に乗りこみ、大ばくちを打つ。共犯に引きずりこまれたのは、2大国際スターのカトリーヌ・ドヌーヴとジェラール・ドバルデュー。それに謎の監督ジャン=リュック・ゴダール。2人の兄弟がただのサギ師に終わるか、それとも若き天才になるか?この物語が教えてくれる。 [出版社より] 著 者|オリヴィエ・プリオル 訳 者|中条省平・中条志穂 出版社|TAC出版 定 価|2,000円+税 判 型|四六判/並製 頁 数|312 ISBN|978-4813271574 発 行|2018年10月 Author オリヴィエ・プリオル Ollivier Pourriol 1971年生まれ。フランスのエリート校、リコール・ノルマル・シュペリユール(高等師範学校)を卒業。専攻は哲学、哲学の教師として教壇に立ったこともある。作家としては2001年に『メフィスト・ワルツ』を発表し成功をおさめ、2005年には『ナイフを持った画家』、2006年には共著『ポラロイド』などを発表。また、映画会社MK2とパリ・フィルハーモニー・ホールによる映画講演会の創始者でもある。 2015年には『スターウォーズ』シリーズに関する本『ヨーダかく語りき』を上梓した。 Translator 中条 省平 Shohei Chujo 1954年生まれ。学習院大学文学部フランス語圏文化学科教授。東京大学大学院博士課程修了。パリ大学文学博士。主な著書に『反=近代文学史』(文藝春秋/中公文庫)、『クリント・イーストウッド-アメリカ映画史を再生する男』(朝日新聞社/ちくま文庫)、『フランス映画史の誘惑』(集英社新書)、『小説家になる!』(メタローグ/ちくま文庫)、『マンガの教養-読んでおきたい常識・必修の名作100』(幻冬舎新書)、訳書にジュネ『花のノートルダム』、バタイユ『マダム・エドワルダ/目玉の話』(ともに光文社古典新訳文庫)など。 中条 志穂 Shiho Chujo 1970年生まれ。翻訳家。学習院大学フランス文学科卒。映画制作会社勤務を経て、パリ大学へ留学。雑誌「ふらんす」にて新作フランス映画の紹介・解説を10年以上続けている。共訳書に『フェリーニ・オン・フェリーニ』(キネマ旬報社)、フロマン『ロベルト・スッコ』(太田出版)、ロメール『四季の愛の物語』(愛育社)、フィエロ『パリ歴史事典』(白水社)など。